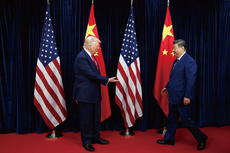自分自身のコピーロボ「ジェミノイド」を作った石黒浩・大阪大学教授は、ロボット研究を通じて「人間とは何か」を追究している。ケータイの先には、ロボットを通じた新しいコミュニケーションの時代がやってくると断言する石黒氏は、科学者でもあり、哲学者でもある。
 石黒浩教授と自身のコピーロボ「ジェミノイド」
石黒浩教授と自身のコピーロボ「ジェミノイド」(c)ATR知能ロボティクス研究所
高井ジロル(以下、●印) 映画「サロゲート」では、人々が精巧な代理ロボットに乗り移り、安全な部屋から遠隔操作する世界が描かれていましたが、ああいう世界は本当にやってくるんでしょうか。
石黒浩(以下「——」) よく聞かれるんですが、私は評論家ではないので、答えようがないです。自分が思い描いた未来を作るのが私の役目。私自身は情報化社会の次には情報ロボット化社会が来ると思ってやっています。全世界がそうなるとは言いませんが、部分的には必ずこういう世界がくると思います。いや、必ずきます。
(参考:『サロゲート』の未来は近い:ロボット学者・石黒浩教授インタビュー〔WIRED VISION〕)
●「やってくる」んじゃなくて、「やってこさせる」と。
——そのためには、人とロボットはどう関わればいいのか、ロボットをどういうふうに開発すればいいのか、人の行動を認識するセンサネットワークをどう作ればいいのか。そういうことを10年以上研究してきて強く思ったのは、人と関わるロボットを作るには人を知らないといけないということ。ロボットを作ることは、人とは何かを知ることなんです。
 インタビューに答える石黒浩教授
インタビューに答える石黒浩教授
非常に基本的なこの疑問において、まず最初に直面した問題は、見かけについて。10年ほど前、「ロボビー」というロボットをベースに、三菱重工業が「ワカマル」という市販ロボットを作ったんです。有名デザイナーが手がけたこの外見が、私はあまり好きではなかったんですね。人間にこだわる私にとっては,もっと人間らしくあってほしかった。でも、私がそう言っても、三菱重工の人を説得できなかった。
そこでよく考えてみると、ロボット研究者というのは、動きについてばかりやってきて、見かけについてはこだわってこなかったんですね。でも、人と関わるロボットでは、見かけはかなり大事。遠くから歩いてくるきれいな人を見れば注意が向くし、毎朝鏡でチェックするのは動きじゃなくて見かけです。なのに見かけを研究してこなかった。これは大きなミスだと気づいたんです。