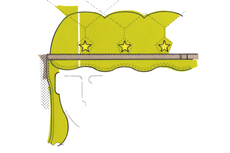1937年に始まった日中戦争は、当初は局地紛争に過ぎなかった。日本政府も陸軍もこの紛争を全面戦争に発展させる意思はなかった。まして米国との全面戦争につながることを期待した人間はいなかった。なぜ多くの政治家や軍人の意思とは裏腹に、極東の小紛争は対米全面戦争へと発展していくのだろうか。
後追いで設定された戦争目的
戦争が政治行動である以上、そこには達成すべき政治目的がある。まず何らかの目的があり、その達成手段として戦争が選択され、必要な戦争の形態や規模が決定される。もちろんこれは理想的モデルである。戦争には相手があるし、戦争が人間の営みであり、人間が感情の生き物である以上、戦争は往々にして非合理的な軌跡をたどる。
日中戦争はこの典型事例である。日中戦争の特徴は、徹頭徹尾、現実としての戦争が先行し、その戦争を正当化するために戦争目的が追従して立案された点である。
そもそも日中戦争の発端となった盧溝橋事件(1937年7月7日)はアクシデントに近いものだった。夜間演習中の日本軍に銃弾を撃ち込んだのは誰なのか今も分かっていない。日本側の謀略説もあるが、日本軍が組織的に関与していた可能性は低い。したがって戦争目的が、戦争行為の後追いで設定されたのはある意味では当然であった。
当初、日本政府は戦争目的を治安回復、謝罪、再発防止などに置いていた。最も強硬な態度を示していたのは陸軍の「拡大一撃派」であったが、彼らの想定する戦争目的も、基本的には華北の日本勢力圏を確認・強化し、紛争原因の除去を目指す程度であった。
そもそも彼らの認識では日本が断固たる態度を示せば中国はすぐに降伏すると考えていたから、「拡大」とはいっても華北での局地戦を想定していたに過ぎない。状況によって全面戦争に移行することがあったとしても、それは一時的な事象であって、いずれにせよ中国軍はすぐに屈服すると判断していた。
早々に瓦解する日本軍の甘い見通し
日本側の想定は、しかし早々に覆される。原因は蔣介石の徹底抗戦にあった。満州事変において、蔣介石は無抵抗を選択した結果、国際社会からモラル・サポート以上の支援を得られなかった。その反省から、今度は徹底抗戦を選択することで国際社会の援助を得ようとする。
蔣介石が反撃の舞台に選んだのは華北ではなく華中の国際都市上海であった。日本政府や軍は紛争のエスカレーション・ドミナンス(主導権)は日本側にあると認識していたが、それは中国の抵抗意志と能力を過小評価した結論だった。拡大・不拡大の選択権は中国側にあったのである。