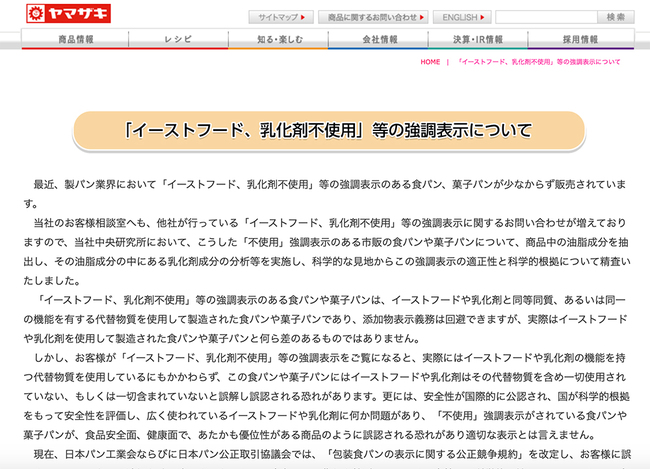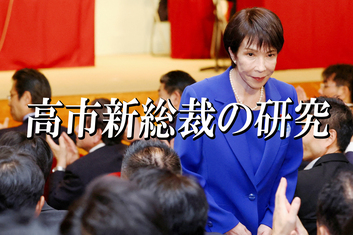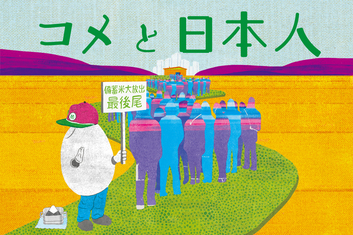イーストフード、乳化剤は不使用、無添加……。パッケージに大きく書かれているパンがあるのをご存知ですか?
添加物嫌いの人たちには歓迎されています。私の入っている生協は、組合員がウェブサイトで商品に対するコメントを書き込めるのですが、「添加物まみれの食品が溢れ返る中、少しでも自然に近いものを選びたい」と大絶賛されていました。
でも、からくりがあるようです。不使用、無添加表示のパンには実際には、「添加物」とは呼ばれない同一、同等の成分が入っている、というのです。
製パン業界1位の山崎製パン(株)が3月、『イーストフード、乳化剤不使用等の強調表示について』と題するページを公開し、そのノウハウを解説しました。
強調表示というのは、商品の独自の特徴をアピールするもので、法律で決まっている食品表示項目とは別にパッケージに記載します。飲料の「糖類ゼロ」や菓子の「カルシウムたっぷり」などがおなじみですが、パン類では近年、イーストフード・乳化剤不使用や無添加の強調表示が目立ちます。
山崎製パンは行っていませんが、業界2位の敷島製パン(株)、3位のフジパングループ(株)、神戸屋(株)、(株)タカキベーカリーなどが、この強調表示をしています。これに対して山崎製パンは、ライバル企業の具体名こそ挙げていませんが、「強調表示は、消費者の誤認を招くものであり、直ちに取りやめるべきだ」と、主張しました。
企業としては異例の見解表明。食品業界に波紋が拡がっています。この騒動の背景には、パンに限らず昨今もてはやされている「不使用食品」「無添加食品」を巡る複雑な話があります。保存料やうま味調味料などさまざまな添加物で、同様のからくりが用いられ、消費者が勝手に「無添加だから体に良い」「自然に近いから安全」などと信じ込んで食べているのです。
本コラムでこれから何回かにわたって、このからくりを解説したいと考えています。まずは第1回、イーストフード・乳化剤のお話です。
イーストフードは、酵母の栄養源
そもそも、パンに用いられるイーストフードと乳化剤が何なのか、ご存知ですか?
イーストフードは、塩化アンモニウム、炭酸カルシウム、塩化マグネシウム、リン酸三カルシウム等、18種類の物質を指しており、食品表示基準で一括して「イーストフード」として表記することが認められています。
そのために、「隠されている」「危険」などと言われがちで、インターネットを検索するとそうした情報が山のように出てきます。が、化学を少し学んだ人ならわかるとおり、実は、人や動物、植物の中にいくらでもあるごく一般的な元素の化合物ばかりです。
その物質自体を大量に食べれば有害ですが、食品に大量に入れてしまうと味がひどく悪くなりますから、入れることはありません。「化学物質のリスクは摂取量によって大きく異なる」「添加物は、使い方や使う量が決められて、安全が確保されている」と知っていれば懸念はないはずなのですが、悪者扱いされやすい添加物です。