しかし、これだけ多くの国と地域が参加するとなると莫大な運営費がかかります。現在のオリンピックの運営費は2000億円以上と言われています。参加国の中には当然裕福でない国もあります。そういった国々は、開催都市への往復の旅費や滞在費をまかなえない。そこで、オリンピックの商業的価値に対してスポンサーになった企業に協賛金を出してもらうのです。それにより、200以上の国と地域の人たちが参加できるようになりました。
――そういった企業のお金が入るようになり商業化の道を歩む中で、1976年のモントリオール五輪はひとつの転機になったということですが。
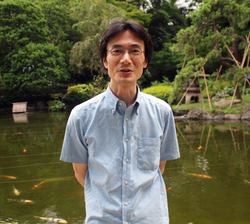 著者の小川勝氏 (撮影:編集部)
著者の小川勝氏 (撮影:編集部)
小川氏:この大会では約10億ドルという巨額の赤字が出てしまったのです。当時のモントリオール市長であったジャン・ドラポーが中心となり大会招致が行われました。市長は大会組織委員会の委員長に役人を据えたため、非常に官僚的な運営となり、コスト意識の低い、非効率な運営となってしまった。
10億ドルの赤字のうち2億ドルをモントリオール市が負担することとなり、同市は不動産税の増税でこれを賄いました。残りはモントリオール市のあるケベック州が、たばこ税増税などをしなければならなくなった。オリンピックの赤字の補填のために地元の住民に税負担が強いられるということが報道されました。
――その後の84年ロサンゼルス五輪は商業的に大成功だったと言われています。
小川氏:76年のモントリオールやデンバーの返上という経験から、税金を使わずにオリンピックを開催しなければならなくなった。そういった事情もあり、ロス五輪は史上初の完全民営化以外道はなかったのです。また、地元であるカリフォルニア州だけなく、連邦政府も一切運営費の協力はしませんでした。ただし、大会組織委員長を務めたピーター・ユベロスも自著で「税金の投入は政治の介入を許す」と語っています。この大会で一躍注目を浴びたユベロスは、通常のオリンピックでは運営費を集めるために宝くじや寄付を集めますが、そういったことを一切しませんでした。
――アメリカだと寄付は集まりそうなイメージがあります。
小川氏:アメリカのオリンピックスポーツは寄付で成り立っています。日本のJOCにあたるアメリカのUSOCは、世界でも稀な寄付と企業のスポンサー収入で成り立っている組織です。連邦政府や地元からの税金を一切もらっていません。スポーツにお金を出す企業というのは限られています。もし、オリンピック組織委員会が寄付を集めようとすればUSOCと取り合いになってしまうことが予想されたので寄付を集めませんでした。そのためにスポンサー収入や放映権料だけで運営した。

















