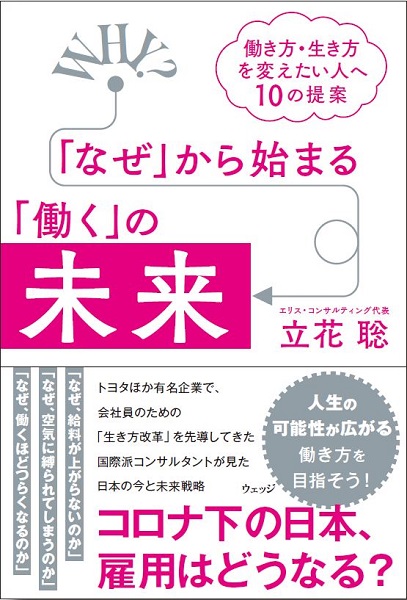採算ラインの圧倒的な低さ
諸問題の根源は、財務的費用構造だ。ビジネスの採算性にかかわる「固定費」と「変動費」を考えてみよう。
変動費とは、売上高に比例して発生する費用である。仕入れた原材料や部品などが代表的な例であり、売上が増えるほど仕入れも増え、売上が減ると仕入れも減らしていくわけである。固定費とは、売上高に関係なく発生する費用のことである。「販売費および一般管理費」ともいわれ、賃借料や水道光熱費、保険料、通信費などがそれに該当する。そして何よりも最大のウエイトを占めるのが人件費である。
損益分岐点とは、その名前の通り経営上の赤字と黒字の境目となるポイントのことを指す。事業を継続していくうえで発生する支出と、事業の売上高が拮抗するポイントと考えることもできる。損益分岐点は固定費、変動費と、売上高を用いて算出することができる。
固定費が大きい場合、損益分岐点に到達しなかったときの損失は大きくなる。売上が伸びなくても、出ていく固定費は一定だからである。したがって収益性を上げるためには、一般的に「固定費を下げる」という手法が用いられる。固定費を下げれば損益分岐点も小さくなり、少ない売上でも利益が出るようになる。
特に市場の競争が激しく先行き不透明だったりする場合、固定費の削減は経営リスクを低減するうえで大変有効な手段となる。しかし、いったん上がってしまった人件費は下げられない、解雇やリストラもできないということになると、固定費がただひたすら膨張していくことになる。
最終の手段としては、固定費の変動費へのシフト、つまり固定費であるはずの人件費を変動費にもっていくよりほかない。あるいは固定費の占める比率を最小限に抑えることだ。
騎楼モデルは、まず主たる固定費であるはずの賃貸料と人件費を固定費の枠から外し、見事にこの難題をクリアしてしまう。損益分岐点をゼロに近い、もっとも低いレベルに設定した時点で、極端な話、売り上げゼロでも何とか乗り越えられるのだ。
雇用調整にはコストがかかる
ここで、一般的な危機対応コストの項目明細をみてみよう。コロナ禍のような不況が生じると、雇用調整が必要になる。業務減少や人員過剰、賃金原資不足などの原因が挙げられる。雇用調整とは、実際雇用量と最適雇用量のギャップを埋めることを指す。
雇用調整のコストはおおむね次の5種類に分類できる。
(1)解雇コスト。「実際雇用量>最適雇用量」の際、余剰人員の解雇・リストラが必要になってくる。その際、リストラのコストが発生する。
(2)雇用不足コスト。「実際雇用量<最適雇用量」の場合、本来ならば、ギャップを埋める分の雇用をすればいいのだが、上記のような事情があって解雇が難しい場合、将来「実際雇用量>最適雇用量」になった場合を想定し、企業は往々にして必要な雇用を思い切ってできない。
(3)教育訓練コスト。業務技能が長期にわたる企業内教育訓練で形成される場合、これらの教育訓練コストの「減価償却」完了前(投資回収完了前)の解雇は企業に損失をもたらす。逆に、増員の際に必要な技能をもった労働者を即時に外部から調達することが難しい。
(4)事務コスト。雇用調整の実施にあたって、増員雇用も解雇も、計画や募集、採用、配置、解雇など一連の企業内事務が発生し、これに対処するためのコストがかかる。これらの調整が頻繁に行われる場合、制度運営上、慢性的な疲弊化が生じやすい。
(5)モラルコスト。頻繁な雇用調整は、雇用基盤の不安定化を意味する。いつ解雇されるか分からないという不安が募り、従業員のモラル低下や労使関係の悪化につながりかねない。これに伴う業務効率の低下や人材の流出など、いずれもコストという形になって跳ね返ってくる。
雇用調整は、実際雇用量と最適雇用量の相互関係を調整するものである。その本質は、要するに変動する業務量に対する適正なリソースの確保であり、業務処理リソースの配置適正化ともいえる。財務的にいうと、変動費であるべき業務処理コストを、固定費にあたる雇用コストで対処するから、どこかで必ずバランスが崩れるわけだ。
よくみると、5つのコスト問題はいずれも、騎楼モデルにより解決される。やや理想化されたモデルであり、一般の事業現場においても、必ずしも通用するとはかぎらないが理念を理解し、派生的に運用するには、よい学習素材になるはずだ。
続きは本書『「なぜ」から始まる「働く」の未来』をご覧ください。