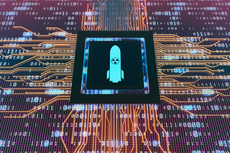「このままでは 国家財政は破綻する」と題した矢野康治・財務省事務次官の論文が月刊誌『文藝春秋』に掲載され、各方面に波紋を広げている。自民党総裁選や衆院選をめぐる政策提案を「ばらまき合戦のようだ」と批判、数十兆円規模の経済対策や消費税率引き下げが主張されることについて「国庫には、無尽蔵にお金があるかのような話ばかりが聞こえてくる」と指摘した。
筆者は社会保障の専門家であり、特に市民生活を守るための財政出動は不可欠とする立場である。しかし、2020年の新型コロナウイルス感染拡大以降の政策動向をみていると、矢野氏が指摘するように「ばらまき合戦」と評価せざるを得ない現状もある。
その代表格が、コロナ禍における国による「生活困窮者向け特例貸付」である。21年10月時点で貸付額は1.2兆円を超え、生活保護費の年間予算に匹敵する規模となっており、暴力団組員による詐欺事件も続発している。
本連載の初回では特例貸付について、なぜ「ばらまき合戦」と評価するのか、必要な人に支援の手は届いているのかという二つの側面から考えてみたい。
「実質給付!?」対面審査なしで進められる貸付
特例貸付の総額1.2兆円は、リーマン・ショックの影響を受けた09年の50倍以上である。とはいっても、その規模は多くの人にとってイメージのつきにくい数字であろう。事態の深刻さを理解していただくために、生活困窮者への支援の代表である生活保護制度と比較してみよう。
18年度の国の生活保護費負担金は、住宅や教育、医療・介護といった費用も含まれており、その総額は実績ベースで約3.6兆円。このうち、生活費に相当する生活扶助は1.1兆円である。つまり、コロナ禍の約1年半の間に、国の生活保護費の年間予算に匹敵する規模の財政支出が行われたことになる。
特例貸付の制度は二つある。一つは、緊急かつ一時的な生計維持のための①「緊急小口資金」で貸付額は20万円以内である。もう一つは、生活立て直しのための一定期間の生活費を貸し付ける②「総合支援資金」であり、2人以上の世帯だと毎月20万円以内で、最大9カ月。①・②合わせて200万円まで無利子で借りることができる。