もしあなたが東海道新幹線の車内でこの記事を読んでいたら、前方・後方の扉の両脇にある広告を見てほしい。それは日常生活でなじみのある企業の広告かもしれない。あるいは、社名は知っているけど、どんな商品やサービスを提供しているかはわからないという企業の広告もあるのかもしれない。
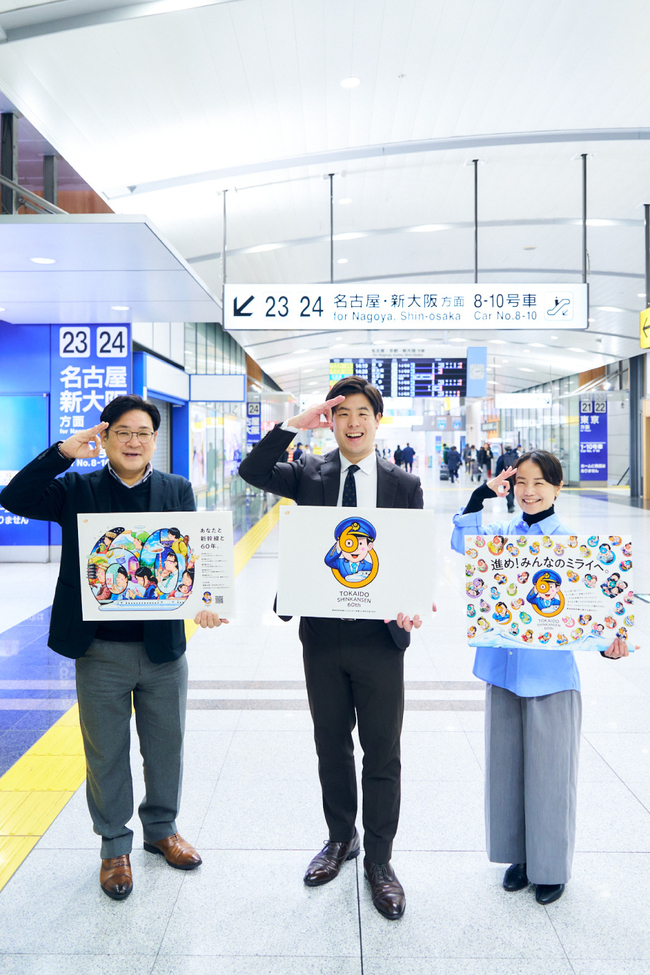
後者の企業の場合、法人相手の取引(BtoB)が中心で、一般消費者向けのビジネスはあまり行っていないケースが多い。ではなぜ、そのような企業が新幹線に車内広告を出すのか。
「東京─名古屋─大阪という経済の大動脈を結ぶ東海道新幹線のお客さまは、主に出張などビジネスでのご利用が多いからです。だからこそ、車内ではBtoB広告がより効果的なのです」
こう話すのはJR東海エージェンシー(JTA)・JR部第一アカウントチームの谷稔乃亮さん(32歳)。JTAはJR東海グループの広告会社で、新幹線の車内のほか、JR東海の新幹線駅17駅、在来線395駅で広告事業を行っている。
「ビジネスパーソンの多さは、東海道新幹線の強みでもあります。でも、改札から一歩外に出ると、一般消費者の方々に向けた広告も増えます。駅では新幹線には乗らないお客さまも広告を見ますから」
JTAは一般企業だけでなく、JR東海の広告宣伝も担当しており、その一つに「そうだ 京都、行こう。」のキャッチコピーで知られる京都キャンペーンがある。2020年には東京駅八重洲中央コンコースに本物の白砂や擬石を使って京都の石庭を再現し、話題を呼んだ。
もっとも、京都から一歩足を延ばせば、もう一つの古都・奈良があり、JR東海では奈良キャンペーンにも取り組んでいる。首都圏から奈良に向かう場合、京都でJR在来線か近鉄線に乗り換えるのが一般的な交通手段だ。つまり、新幹線を利用して、京都と奈良の魅力を最大限味わってほしいという思いがある。
05年にスタートしたキャンペーン名は「うましうるわし奈良」だったが、22年からは「いざいざ奈良」に変わった。JTA・制作部でクリエイティブディレクターを務める佐々木理恵さん(41歳)が変更の理由を説明してくれた。
「『うましうるわし奈良』は日本の歴史・文化の原点である奈良の魅力を紹介する目的で開始し、50代以上の方々を中心に浸透しました。もっと裾野を広げて幅広い世代の方にも奈良にお越しいただけるようにと、食などの多面的な魅力を発信し始めたのが『いざいざ奈良』です」
22年といえば、新型コロナウイルス感染症の流行により移動の自粛が求められていた時期である。「まだコロナ禍は続いていたので不安もありましたが、分散型の旅行など新しい旅のスタイルが登場していたこともあり、いまだ!」と一歩前に踏み出した。
コロナ禍が収束し、再び人々は旅行に出かけるようになった。「『今まで奈良に関心がなかったが行ってよかった』といったSNSの投稿を読むと、やってよかったと思います」。
一般企業の広告の制作も担当する佐々木さんだが、ほかの会社と比べるとJR東海の広告にはどんな特徴があるのだろうか。尋ねてみたら少し考えて、こう話してくれた。
「まず安心・安全をベースにして広告を作っていくということです。消費財の広告なら『どうすればより売れるか』を考えればいいのですが、JR東海の場合、『ただ単に売る』ということではなく、安心・安全を常に意識しながら制作することを心掛けています」



















