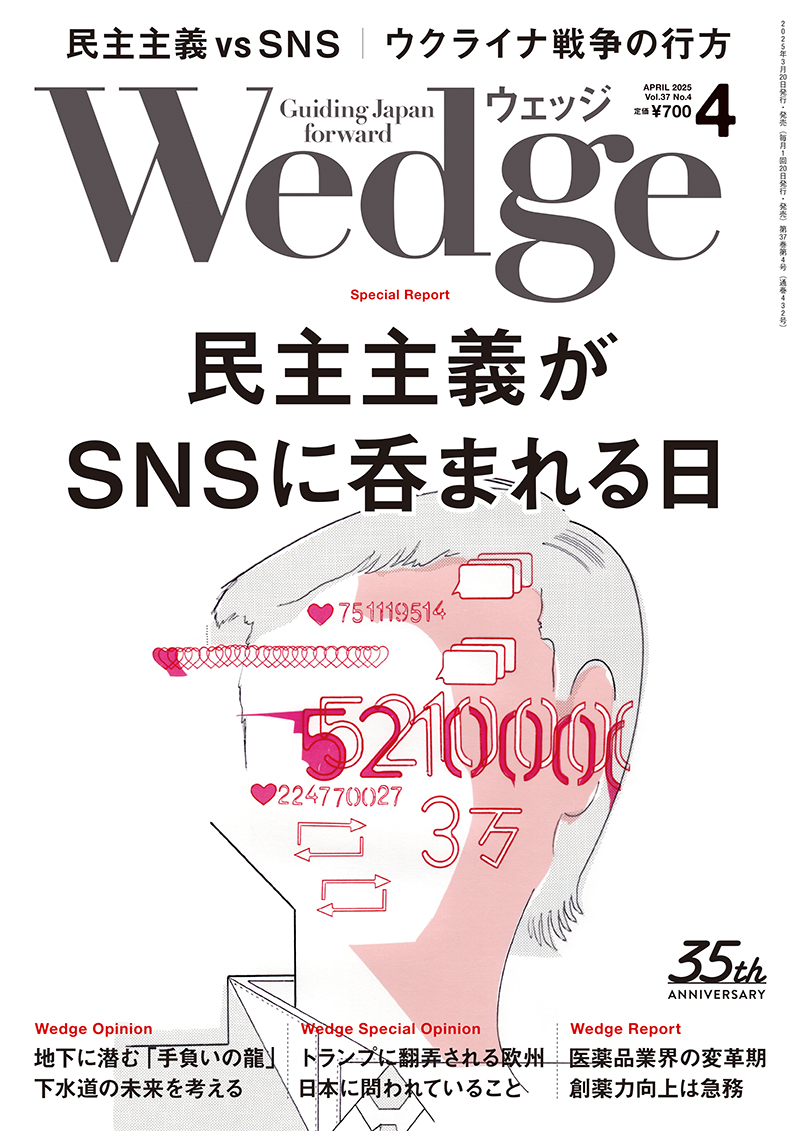新幹線の重要な情報を
世の中に伝えるのも役目
「最近のJR東海は柔らかくなった」。筆者はこんな声をあちこちで聞くようになった。「のぞみ」を号車単位で貸し切りにして販売し、プロレスなどのイベントを行ったり、アニメやアーティストなど外部コンテンツと連携した推し旅キャンペーンを始めたり。24年には東海道新幹線の60周年を記念し、『大ピンチずかん』(小学館)で知られる鈴木のりたけ氏のイラストをモチーフにした企画を展開している。
「10年前には考えられなかった企画が、コロナ禍を経て、今ではどんどん実現しています」と話すのはJTA・JR部第二アカウントチームの加藤聖二さん(50歳)。コロナ禍で新幹線の利用が激減したことも一つのきっかけになり、需要掘り起こしにつながる企画が積極的に採用されるようになったのだ。
こうした企画は主にJR東海・営業本部をはじめとする社内の営業担当部門が中心となって担う。JR東海とJTAの役割分担はどうなっているのか。加藤さんがこう答えてくれた。
「JR東海の営業部門の役割は東海道新幹線・在来線のさらなる需要喚起やエクスプレス予約サービスの充実などですが、そのための広告宣伝プランを考えるのが我々の役割です。もちろん、我々だけではなく、営業部門の若手社員から『こんな企画をやりたい』と手が挙がることもあります。だから、役割分担というよりもJR東海とは〝二人三脚〟という関係です」
これらの仕事以外にもJTAには重要な任務がある。それは、新幹線に関わる重要な情報を世の中に伝えることである。ダイヤ改正はその代表例だ。ゴールデンウイーク、お盆、年末年始の三大ピーク時、23年12月から「のぞみ」は全車指定席になったが、その告知もJTAが担当した。今春からは自由席だった「のぞみ」の3号車が指定席になるが、混乱が起きないようにするためには、告知活動が欠かせない。
広告にも「安心・安全」が息づく
JR東海の「奥底」を知る彼らの強み
海外への情報発信強化も担っている。新幹線を運営するJR各社、台湾高速鉄路、メーカー、総合商社などで構成される国際高速鉄道協会(IHRA)という一般社団法人がある。日本の高速鉄道システムに関心を持つ国々に、新幹線システムの情報を正確に提供するため、14年に設立された。新幹線のみが走行する専用軌道と自動列車制御装置(ATC)の導入による衝突回避の原則など、新幹線の優位性を世界にどう伝えるべきか、加藤さんは腐心した。
「IHRAはオールジャパンの団体ですから、日本代表になったような気持ちでした」
この話題に触れたときの加藤さんの表情は、どこか誇らしげに見えた。
広告業界には電通、博報堂といった大手も含め様々な企業がある。グループ企業だから自動的にJR東海の仕事を担うという世界ではない。では、JTAの強みは何か。3人に尋ねると、まず加藤さんが口を開いた。
「JR東海が奥底に持つ課題を私たちが最も理解しているということではないでしょうか」
奥底に持つ課題とはまさに、同社の使命でもある安全最優先の姿勢を指すのだろう。続いて、谷さんがこう答えた。
「クリエイティブの部分では各社それぞれに魅力や強みがあると思いますが、僕らが絶対的に強いのは〝進行力〟です」
進行とは作業の進め方だ。広告会社の仕事は華やかに見えて、地味で地道な仕事が極めて多い世界でもある。その上で谷さんはこう続けた。「東海道新幹線のブランディングを最大化するために、安全最優先の姿勢を基軸にしながら、クリエイティブな発想を掛け合わせて実践していくのが私たちの最大の強みです」。
鉄道とはまるで違う広告の仕事にも安心・安全という新幹線の基本理念が息づいている。