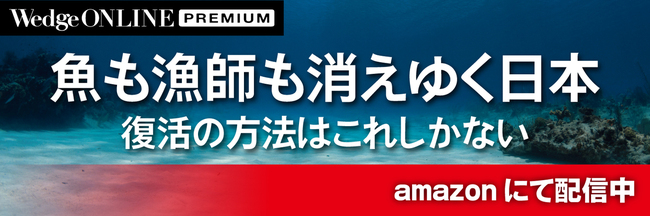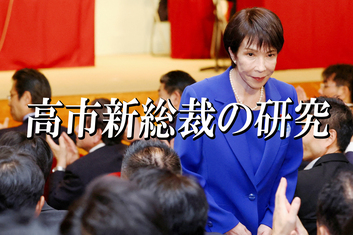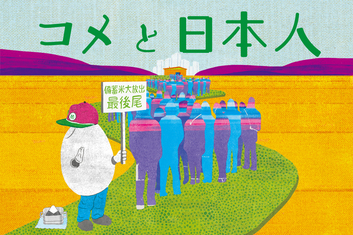太平洋のゴマサバも太平洋のマサバと同様、資源量は乱獲水準にある。水研機構によると、親魚の資源量は11年をピークに下降を始め、3年後の14年には望ましい資源水準を割り込んだ乱獲状態となり、資源量は以降も低迷したままとなっている。
3月のサバ漁業者等が参加した会合で漁業者から内諾が得られたことから採用されるであろう25年漁期の太平洋のサバ類漁獲枠のうちゴマサバ分としてカウントされているのは5.2万トンだが、これは水研の科学者たちが推奨した1.8万トンの3倍に近い。政府関係者からも「(ゴマサバの)枯渇もある得る内容だ」との懸念の声が上がったと報じられている。
そもそも、ゴマサバとマサバを分けて管理していない以上、例え実際にゴマサバが5.2万トンに達したとしても、漁獲実績が太平洋さば類の総枠に達していない限り、漁獲は続けられることになる。
水研機構が22年に開催した資源評価会議の場においても、外部有識者として招聘された研究者から「マサバとゴマサバを合わせたTACなのでゴマサバの漁獲量は制御できていない。ステーク・ホルダーや行政にしっかり伝えることが大事である」と指摘されている。残念ながら、こうした科学者の指摘は伝わっていないと言えよう。
自ら範を示し、サバの乱獲を防げ
公海の水産資源に関する枠組み条約的な役割を果たしており、日本も批准している「国連公海漁業協定」の柱の一つが、「一貫性の原則」である。公海での水産資源の規制措置が、沿岸国がEEZ内に関して定めた規制措置と一貫性を持たせるための規定である。
この一貫性の原則の一つとして定められているものが、サバの資源管理に重要な意味を持ってくる。すなわち、いずれの国も、複数の国のEEZや公海に跨って回遊する資源(「ストラドリング魚類資源」と言う)に関して沿岸国がEEZにおいて定めた漁獲枠などの保存管理措置を考慮しなければならず、また、こうした資源に関して公海で定めた措置が沿岸国によって定められたEEZ内の保存管理措置の実効性を損なわないようにしなければならない、と規定している(第7条2項(a))。
水産庁で当時サバに関して漁獲枠設定を主導した担当官は、規制を導入する際に上記規定の主旨を漁業者に紹介するとともに、「一貫性のあるものを確保するというのは何かというと、先に沿岸国がしっかりした措置を決めれば、それと同じ効果がある措置を公海でも決めないといけないということなんです」と説明、「先に日本のほうできっちりした措置をとることが大事なんです」と力説している。筆者はこれに完全に合意する。
しかし残念ながら、この目標は未だ達成されてはいない。短期的な観点からとにかく漁獲枠が一番大きなものを選ぼうとすることは、資源の持続可能な利用という観点からも支持し得ないし、一貫性の原則の下に他国に対して厳格な規制措置を求めることにも資するものではないのである。
では解決策は何か。それについては、我が国の水産資源科学者たちが既に示している。科学者たちの推奨する漁獲枠に則り、例え短期的には痛みを伴うかもしれないが、漁獲規制の強化を図ることである。そしてそれをもとに、他国に対しても「一貫性の原則」を根拠として、厳しい規制を迫ればよいのである。
なお、漁獲の削減は漁業者に取り漁獲収入の減少につながる。これについては資源管理に取り組む漁業者に対して減収分を補填する「積立ぷらす」という制度がすでにある。資源の減少に伴い強い漁獲規制を導入した太平洋クロマグロでもこの制度を通常よりも優遇的な条件で適用し、救済に当たっている。解決策は、既に用意されているのである。
サバを末永く利用するため必要なのは、持続可能な利用という原則に基づく率先した資源管理である。世界有数の魚食文化を持つ我が国こそ、その先頭に立つべきである。サバの枯渇を座視するべきではないのだ。