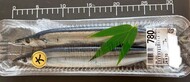日本の漁業 こうすれば復活できる
海に囲まれた日本にとって重要な産業である漁業の危機が続いている。国連が定めた「持続可能な開発目標(SDGs)」の一つである「海の豊かさを守ろう」を果たしながら、産業としてどう復活させていくのか。その処方箋を示していく。

-
 2025/12/24 片野 歩
2025/12/24 片野 歩イクラがサケの大不漁で史上最高価格になっている。温暖化による資源の減少が原因とされるが、世界に目を向けると、サケの資源管理について根本的な違いがあることが分かる。現実を直視してみましょう。
-
 2025/11/28 片野 歩
2025/11/28 片野 歩日本の食卓に浸透しているノルウェーサバの価格に異変が起きている。資源管理のために漁獲量を減らしたためで、日本は国産でまかなうこともできない厳しい状況となっている。
-
 2025/11/06 真田康弘
2025/11/06 真田康弘11月末から開催されるワシントン条約締約国会議でウナギを附属書に掲載して条約の規制対象とする提案がEUから上程されるのに、日本の業界団体と水産庁は提案阻止に全力を挙げている。そこでは、「ウナギが増えている」という主張も展開する。
-
 2025/10/06 真田康弘
2025/10/06 真田康弘資源が激減しているスルメイカについて、水産庁が漁獲枠の拡大を急遽検討し、実施に踏み切った。この夏豊漁というのが主な理由で、科学的根拠がないと資源の現状を知る関係者を驚愕させた。
-
 2025/10/02 片野 歩
2025/10/02 片野 歩秋の風物詩サンマは近年、不漁が続いていたが、今年は近年になく好調で、48時間の休漁も行われた。なぜ漁が上向いているのか? その理由を理解していないと、また獲れなくなる事態を繰り返してしまう。
-
 2025/09/02 真田康弘
2025/09/02 真田康弘夏の風物詩としても親しまれる「ウナギ」。日本では、香港からの〝密輸入〟を事実上黙認し、世界からの取り締まり強化への動きに対しても、官業総出で「反対」する姿勢を見せている。今一度、トレーサビリティ強化を進める必要がある。
-
 2025/09/01 真田康弘
2025/09/01 真田康弘夏の暑さを乗り切る食べ物として好まれてきたウナギ。その取引は様々な闇が覆う。日本の水産物はトレーサビリティが担保されているものは多くないのが実情だが、ウナギほど問題まみれの水産物も珍しい。「中国産」と言われる輸入品の実情を見ていきたい。
-
 2025/08/18 片野 歩
2025/08/18 片野 歩秋の味覚サンマ。生サンマの刺身を味わう機会はめっきり減ってしまいました。おいしさの指標である脂ののり具合が今一つで、安くておいしい大衆魚から、細くて高い高級魚に変わってしまったサンマは今後どうなっていくのでしょうか?
-
 2025/08/05 真田康弘
2025/08/05 真田康弘ここ数年の夏の暑さが異常である中、水産庁は水産資源の悪化を温暖化に全て負わせるような「獲るものを変える」というアプローチばかりが重視している。これは、資源の減少に対する乱獲要因を軽視していると言える状況だ。
-
 2025/07/30 片野 歩
2025/07/30 片野 歩「失われた30年」と日本の漁業について、共通の問題があります。それは「事実や問題の本質」が社会に正しく伝わっていないということです。日本で魚が減っている本当の理由を知り、伝えることが必要です。
-
 2025/06/26 片野 歩
2025/06/26 片野 歩人口増加により水産物の需要が世界的に増え続けてる中、漁業を成長産業にしている国々は資源管理をしているため、漁獲量の増加はあまり期待できない。需要を補うのは養殖物。中でも、環境に配慮された陸上養殖に注目が集まる。陸上養殖は供給を補うのか。
-
 2025/05/28 片野 歩
2025/05/28 片野 歩日本の漁獲量減少の原因を「黒潮大蛇行の影響」が挙げられている。環境要因を責任転嫁するのは簡単だが、もっと広い視野で日本の海の周りを眺めると、黒潮大蛇行の影響と漁獲量の関係で様々な矛盾が浮き出てくる。
-
 2025/04/30 片野 歩
2025/04/30 片野 歩魚売り場、外食などで提供できる魚の種類も量も減り続けています。日本の生産量(漁業と養殖)が減り続け、世界の水産物の需要が増加して輸入量も減少しているからです。そして、水産物の生産量が驚くことに、韓国に抜かれそうなのです。
-
 2025/04/07 真田康弘
2025/04/07 真田康弘太平洋で漁獲されるサバが近年不漁に喘いでいる。資源の減少が一つの要因で、北太平洋漁業委員会で、マサバ漁獲枠を一定程度削減する合意が成立したが、削減幅は十分と言うには程遠く、資源状態とは大きなギャップが存在している。
-
 2025/03/31 片野 歩
2025/03/31 片野 歩北太平洋漁業委員会(NPFC)が開催され、サンマの北太平洋全域での漁獲枠を2025年は現行から10%削減で合意した。資源回復へ向けた動きではあるが、資源管理としても、日本としても大きな問題をはらむ。解説していきたい。
-
 2025/03/13 真田康弘
2025/03/13 真田康弘卵が明太子の原料にもなるスケトウダラの資源状態が非常によくない。要因の一つが90年代以降の海洋環境変化により卵の生き残る確率が減少したことであるが、同様に強調しなければならないのが取り過ぎ、乱獲である。
-
 2025/02/28 片野 歩
2025/02/28 片野 歩マサバが獲れない状態が深刻化しています。水産庁が来シーズンの漁獲枠を8割減らすことも伝えられている。これは資源量の実態に合った漁獲枠でなかったことが、本質的な問題で、幼魚に至るまで過剰な漁獲が進み、激減してしまっている。
-
 2025/02/21 真田康弘
2025/02/21 真田康弘スルメイカが極端な不漁に喘いでいる。2023年漁期には1万5705トンと、最盛期に比べ97%以上減らし過去最低を記録。漁業法の改正、施行によって資源管理を進めているが、最近、水産庁がこれに逆行する決定を下した。
-
 2025/01/28 片野 歩
2025/01/28 片野 歩世界全体で水産物の生産量が増え続けているのに対し、日本では減っている。理由はTACの意味や効果が関係者に正しく理解されていないからだ。TACは設定されても実際の漁獲量より多く、資源管理に効果がないという事態が起きてしまっている。
-
 2024/12/27 片野 歩
2024/12/27 片野 歩年末を迎え、売り場にたくさん並ぶズワイガニのパックに貼られている「バルダイ種」との表示に気づいた人もいるのではないか。ズワイガニの一種なのだが、その表示には深い意味がある。また、日本でも今、たくさん獲れており、好機を生かす必要がある。
|
|
|