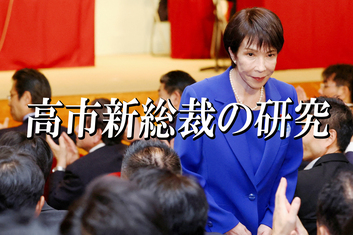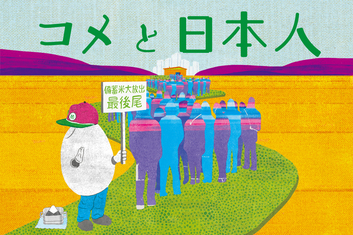ウクライナ館は、「Not for Sale(非売品)」をテーマに、戦争下での市民生活や復興の様子を18の象徴的な展示物を通じて紹介している。これらの展示物には、戦地で使用されたヘルメットや被弾したサイレンなどが含まれ、来場者に深い感情的な体験を提供する。
特に2発の弾丸に被弾してもその機能を維持したというサイレンのメッセージ性は強い。このようなストーリーのある象徴的な展示は、地域の歴史や困難を乗り越えた物語を印象的な観光資源として活用する際の参考になる。
ウルグアイ館は、「53.86% Uruguay, Land of Water」というテーマで、水資源と建築の関係性を探求している。展示では、ウルグアイの海洋領域が国土の53.86%を占めることを強調し、水の管理と保存の重要性を訴えている。
このアプローチは、地方自治体が持つ自然資源をどのように観光資源として活用できるかだけでなく、その“ウリ”を数字とともにブランディングする手法として参考になる。
アゼルバイジャンは日本ではなじみが薄いかもしれないが、パビリオンの7つのアーチによるエントランスの造形は日本人にはドラえもんの“ガリバートンネル”を思わせる。7つのアーチと7体の彫像は7つの美としてアゼルバイジャンのウリを象徴している。
ブランディングを1つに絞り込むことに悩む観光担当者は多いかと思うが、アゼルバイジャンのようにウリを「●つの」という形で複数提示するオプションもありだろう。数としては7つが最大で、できれば3つ程度とするほうが心に刺さりやすいだろう。
地域観光も取り入れられる7つの潮流
このように各国が自国の魅力を存分に伝える展示を展開しており、その多くが観光誘致を意識した構成となっている。この万博の海外パビリオン群を総覧すると、近年の国際観光プロモーションにおける新たな潮流が鮮明に浮かび上がってくる。
第一に注目されるのは、テーマの深化と社会的意義の訴求である。従来の観光誘致が自然や都市の魅力に焦点を当てていたのに対し、現代の展示では、社会課題や人間の物語を観光資源として前面に出している点が特徴だ。
ウクライナ館では「Not for Sale」というメッセージのもと、戦時下における市民の尊厳と回復力を展示し、観光の対象を「記憶」や「人間性」に拡張している。フィジー館では、気候変動に直面する小島国家としての現状を伝え、環境問題と観光を統合した体験を提供している。さらにコスタリカ館では、国民の幸福度と自然保護を軸としたウェルビーイング観光を訴求し、物質的魅力に依存しない持続可能な観光の可能性を提示している。
第二に挙げられるのは、没入体験型の演出の台頭である。プロジェクションマッピング、AR/VR、さらには音・香り・触感といった五感すべてを活用した展示が多くのパビリオンで採用されている。
欧州連合(EU)のパビリオンでは、3つの事業分野の担当者がその等身大画像とともに、日本語と英語で訪問者と対話する双方向性のある展示があった。インドネシア館は、まさに360度の映像と床の振動を組み合わせた没入型空間を構築し、訪問者に強烈な印象を与えている。タイ館は、大型映像とタイ舞踊のインタラクティブな融合でライブ感のある展示を実現。イスラエル館では、防災や医療といった革新的技術を体験形式で紹介し、観光における実用的価値の訴求がなされている。
第三に、生活文化や価値観の観光資源化が進展している点が挙げられる。北欧パビリオンでは、自然との共生や質素で豊かな暮らしを展示の軸に据え、消費に偏らない幸福観を体現。モナコ館では、美と静けさ、自然調和という「小国の美学」を強調し、非日常性を求める旅行者の心を惹きつけている。また、ラトビア館では森林とデジタル社会の融合が展示され、都市と自然のバランスをテーマとする観光のあり方を示している。