哲学問題を、額に汗して考え抜いた師・大森荘蔵を継承して、
“哲学的思考とは何か”を実践的に探求し続ける野矢茂樹氏。
著書『新版 論理トレーニング』は、哲学分野で異例のロングセラー。
本気で考えることの快楽を語らせたら、右に出る者はない。
⇒前篇はこちらから
高井ジロル(以下、●印) 先生は、どうして哲学を続けているのですか?
野矢茂樹教授(以下、「――」) どうして哲学をやるのかと言われたら、考えて議論して少しでも何かわかるその瞬間がものすごくうれしいから、というのが一つ。それから、何かの問題が自分の中で気になって、問題が解決しないとどうにも気持ちが悪いからやる、という感覚もある。
たとえば、意識を持ったロボットは作れるのかという問題。僕はこれに答をもっていません。どんなに精巧複雑なロボットを作っても、そのロボットが物を見ているのか、痛みを感じているのかというのは、どう考えればいいかわからない問題です。殴ったら痛そうな振る舞いをするロボットは作れるし、モニターが目の位置にあって刺激によって行動を変えるロボットも作れる。でもそれは、いってみれば手のこんだ自動ドア。自動ドアがものを見ているとは言わない。じゃあどうなればものを見ていると言えるのかというと、わからない。それが気になって、ものすごく気持ちが悪い。
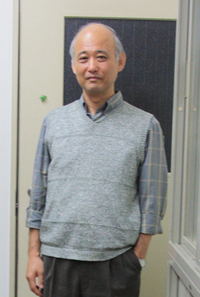 野矢茂樹教授
野矢茂樹教授
こうした問題がいくつもトゲがささるように謎として自分の中に残る。もし人間が自由だとわかったからといって、生活が変わるわけじゃない。人間関係に変化が生じるわけでもない。今まで同じように生きて行くんだけれども、でもやっぱり気になるものはなんとかしたい。
この前、高校生相手に自由について講演したときに、自由の象徴として鳥を出しました。鳥は自由に空を飛んでいると思うか、と聞いてみたんです。「自由に飛んでいる」と答える人が多いと思って。そうしたら、「鳥は自由じゃない」と答えた人が過半数で、びっくりしました。聞いてみるもんだなあと思いましたね。
●悲しみのない自由な空で翼はためかせている鳥が自由じゃないとは、意外です。
——それは言葉が鍵になっていると思う。言葉を持たない動物には自由も心もないんじゃないかと感じています。厳密にいえば、現実とは違うことを表現できる言葉をもっていないといけない。鳥のさえずりには、相手を動かす力はあるけれども、非現実の思考を展開できる力はない。敵がきたぞ、とサルがわめくのは、現実の刺激に対して反応しているわけです。

















