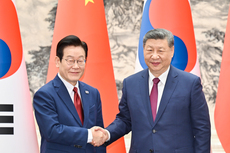「ワシントンの究極のインサイダー」は有利か不利か
バイデンは現在立候補表明している民主党候補の中でも間違いなく大物であり、大統領となるための準備をとりたててする必要がないほどの経験と経歴を持っている。だが、ウォーターゲート事件以後、ワシントン政治の素人を大統領に選出することで、連邦政界の膠着状況を打破してもらいたいとする風潮が強くなっている。また、バイデンの76歳と言う年齢も問題になりうる。高齢なワシントンの究極のインサイダーの言葉や政策が、変革を求める若者の心に届くのかは予想が困難である。
彼の長いワシントン経験も、彼の選挙にとって不利に働く可能性がある。彼が連邦政界にいるこの40年間に、アメリカ社会の価値観は大きく変化した。当時の文脈では許容範囲内に収まると考えられていた行動や発言も、アイデンティティ・ポリティックスが高まり、人種やジェンダーをめぐって大きな価値変容が発生している中では、問題となる可能性がある。例えば、バイデンは1994年の犯罪政策立案の立役者である。当時の民主党ではニューデモクラットと呼ばれる穏健派が影響力を増し、共和党に対抗する関係上、厳格な犯罪対策が求められていた。だが今日では、この犯罪対策強化が、アメリカの刑罰国家化、とりわけ黒人の収監率の高さの原因を作ったと批判されている。
バイデンのジェンダーに対する態度も問題となっている。例えば、ネヴァダ州の州議会議員であったルーシー・フローレスは、バイデンがパーソナル・スペースを守らなかったと批判している。ハグをしたり、髪の毛の匂いを嗅いたり、頭頂部にキスをしたとして批判されているのである。また、かつてバイデンが司法委員会委員長を務めていた1991年、クラレンス・トーマスが連邦最高裁判事に指名された際に、かつての部下であったアニタ・ヒルがセクシャルハラスメントを受けたと問題提起したが、それに対する対応が今日の観点からすると十分でなかったとの批判もある。
バイデンは、2008年の大統領選挙におけるオバマ勝利の立役者の1人である。黒人大統領が世論に受け入れられるかどうかが不明だった当時、労働者階級出身者が多いペンシルヴェニア州出身のカトリックで、外交経験も豊富であり、犯罪対策強化法案を提出したこともあるバイデンが副大統領候補になった事は、反戦左派とも評されたオバマに疑念を持っていた人々を安心させる上で大きな意味を持っただろう。だが、そのようなバイデンの立場が、リベラル派の影響力が増大する今日では、むしろ問題とされる可能性があるのである。
ワシントン政治の素人を支持する風潮を反映して、2020年大統領選挙でもサンダースに対する支持が強まるのだろうか。それとも、ワシントンに対する不満は渦巻くとはいえ、物事をかき乱す人物を大統領に選んでは政治が不安定化するとの観点から、政界勢力と結びつきが強く、安定感のあるバイデンを選んだ方が良いとする立場が強まるのだろうか。今後の展開に注目する必要があるだろう。
![]()
![]()
![]()
▲「WEDGE Infinity」の新着記事などをお届けしています。