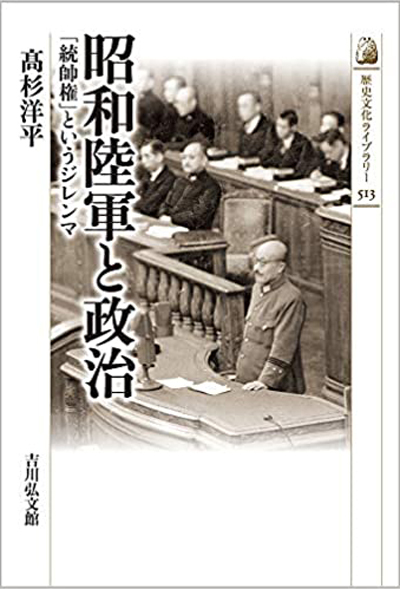第1回として「昭和陸軍と政治」というテーマを扱った表題書を選んだ。需要が多いのにもかかわらず、蓄積のある執筆者は少ないというアンバランスのため、怪しげな書物がまかり通っているとくに是正が必要なジャンルだからである。それだけに本書の意義は大きい。
本書の優れている点として、まず昭和陸軍を理解する上で重要な〝統制派と皇道派の正確な評価〟ということがある。1933年秋ごろに永田鉄山陸軍省軍務局長を中心に統制派が成立、荒木貞夫・真崎甚三郎らの将軍達と青年将校からなる皇道派との激しい抗争が続けられる。統制派の優位下、圧迫された皇道派の反撃として永田鉄山軍務局長斬殺事件がまず起き、そしてさらに皇道派青年将校が起死回生の企図として行ったのが二・二六事件であった。
二・二六事件後、クーデターを起こした側の皇道派は、陸軍から一掃される。ところが、“その結果、それ以前の陸軍で皇道派と対立抗争していた統制派が陸軍を支配することになった”という類の叙述をよく見かけ、教科書的なものに書かれていることすらある。これが問題なのである。
これは、資料も少なく実情がよくわからなかった戦後の一時期の間違った叙述を、昭和陸軍派閥史を研究したことのない人がなぞっただけのものである。私は基本的資料に基づいてそれが間違いであることを指摘してきたが(拙著『二・二六事件と青年将校』吉川弘文館、2014年)、相変わらずそうしたものが出る困った状況が続いていた。
この点を著者は、永田鉄山の死と二・二六事件による皇道派の衰退により「統制派は派閥としての実態を徐々に失い、非政治的な単なる陸軍マジョリティへと解消されていった」(128頁)と的確に叙述している。そしてその上で、石原莞爾・梅津美治郎・武藤章などの活動が叙述されている。
資料的研究から出てくる当然の帰結だが、前述のようにこうした正確な見方が必ずしも広がっていなかったから、これが本書の大きな意義となるのである。資料的根拠なき説をもはや維持することはできないから、本書によって統制派支配説は最終的に消滅するものと思われる。
次にその昭和陸軍の源流ともいうべき重要な存在である永田鉄山のことがある(94~97頁)。陸海軍大臣は武官でなければなれないとする軍部大臣武官制という制度があった。これが、近代日本のガンだという人もあったくらいで、文官からなる政党の内閣ができても軍部をコントロールできない根拠になる制度と見られたものであった。
それが、大正初期にはまず現役でなければならなかったものが、現役でなくてもなれる制度になり、さらに政党の進出により文官制になる可能性すら議論されるようになっていった。これに関する陸軍内部の資料があり、そこに軍部大臣文官制に対する対策が書かれたものがあった。誰が執筆したのかもわからない、全体の文書中のほんの一部の文書であった。
繰り返すが、それは軍部大臣文官制実現を否定するためにその対策として書かれた文書であった。これを取り上げたある研究者が、これは軍部大臣文官制を実現するための文書で、しかも永田が書いたものだと何の根拠もなく言い出した。永田を肯定的に評価する目的のためらしい。しかし、軍部大臣文官制否定のための文書を軍部大臣文官制実現の文書とするのだから、正反対の主張であり手の込んだ間違いである。著者はこの資料を検討し間違いを明確に指摘している。
この研究者は、この主張をする書物で大正初めの軍部大臣武官制改革の際の経緯と実行した陸軍大臣を間違えており、正確性の信頼を失っているのにかかわらず、この間違いの方も認めていない。今からでも遅くはないから謙虚になってその間違いを認め、訂正されてはどうだろう。そうしないのであれば、本書への反批判を書いてから次の研究発表・著作執筆を行うようにしてもらいたい。こうした相互批判によってのみ研究は着実に進んでいくのであるから。
なお、著者の書く永田の人物像は立体的で陰影が深く、ここからも研究の確かさが感じられるのである。