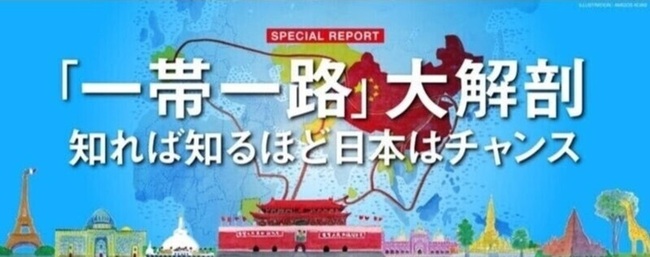対中依存を避けたいミャンマー
国軍を取り込もうとする中国
90年代からの欧米諸国の経済制裁下で孤立していたミャンマーの軍事政権に援助の手を差し伸べてきたのが中国である。しかしながら、11年に軍事政権の流れを組む連邦団結発展党(USDP)の代表として政権を担ったテイン・セイン大統領は、ミャンマー北部カチン州で中国が進めていたミッソン・ダムの建設を、地元住民の反対の声に配慮して凍結している。
このダムが建設されれば、中国の三峡ダムに匹敵する発電が行われ、その9割が中国に輸出されることになっていた。これがミャンマーのためになったかというと首をかしげたくもなるが、テイン・セイン政権にとりミッソン・ダムの建設凍結が欧米諸国から歓迎され、経済制裁解除の1つのきっかけになったとも考えられる。
スー・チー氏率いるNLD政権も、中国への債務依存が強まり、インフラの管理権が中国に渡る「債務の罠」への懸念が根強い。一例として、中国の国営企業である中国中信集団(CITIC)を中心とするコンソーシアムが予定していたチャオピュー経済特区では、大型船が着岸し積荷の積み降ろしが可能な深海港のバースの数を10から2まで削減し、総工費を73億㌦から13億㌦まで交渉により縮小させている。
実際、国内総生産(GDP)に占める対中債務の割合は、減少傾向を示している(2月7日付日本経済新聞)。また、中国とインドが新型コロナウイルス感染症のワクチン外交を展開する中、同政権はインドからも中国からも供給を受ける約束を取り付けており、ロヒンギャ問題で国際的に孤立する中でも極端な対中依存は避けていた。
こうした中、習近平政権は、CMECを実現すべく、クーデターにより孤立したミャンマーをどうやって手繰り寄せようとするのであろうか。政権の先行きが不透明な中で、中国側から軍事政権に一方的に肩入れすることはないだろう。それでも、ミャンマーの国軍が何を望んでいるのかは慎重に検討していることであろう。懸念されるのは、連日のデモに対し国軍がさらなる強硬策に出てもデモが鎮まらない事態が起きたときのことである。国軍が中国側に、香港やウイグルの反政府デモの鎮圧方法、さらには監視カメラによる行動統制の導入を求めたとすれば、恐ろしい話となる。
日本政府としては、欧米諸国と同様に国軍の姿勢を非難しつつも、NLDと国軍双方の対話の窓口を閉ざさないことが求められる。
他方、ミャンマー向け援助については、現時点で新規援助は行わない方向性が示されている。しかし、状況の進展如何によって、援助のさらなる自粛措置が採られる可能性も否定できない。日本政府が官民で取り組んできたティラワ経済特区もさることながら、改修中のヤンゴン・マンダレー間鉄道が仮に停止となった場合、中国が高速鉄道建設を掲げて割り込んでくる可能性も否定できない。
2013年、中国の習近平国家主席が突如打ち出した「一帯一路」構想。中国政府だけでなく、西側諸国までもがその言葉に“幻惑”された。それから7年。中国や沿線国は何を残し、何を得て、何を失ったのか。現地の専門家たちから見た「真実」。それを踏まえた日本の「針路」とは。
特集はWedge Online Premiumにてご購入することができます。
▲「WEDGE Infinity」の新着記事などをお届けしています。