今から半世紀上ほど昔、日本では中国語を学ぼうとする若者の数は微々たるものだった。
筆者は当時、大学の第2外国語で中国語を学んだが、授業の合間に「先輩」を名乗る連中が教室に顔を出し、「国際歌(インターナショナル)」「我愛北京天安門」「東京・北京」などを歌いながら、当時燃え盛っていた文化大革命を「人類史上前例なき“魂の革命”」と熱く語ってくれたことを懐かしく思い出す。今にして振り返れば、拙い政治宣伝の一環だったに違いない。
最近では欧米各国で逆風を受けているものの、中国は海外での孔子学院開設にこだわり続ける。孔子学院を拠点にした対外宣伝活動にあることは言うまでもない。中国語教育をテコに、海外における中国のイメージアップを図ろうというのだ。
今年3月初旬の全国人民代表大会(全人代=国会)における内モンゴル自治区分科会に出席した習近平国家主席は、漢語(=標準中国語)の普及などによる「中華民族」の一体化推進を指示している。昨秋、同自治区でモンゴル語教育縮小の動きに対し、「民族文化を抑圧する『同化政策』だ」との激しい反発が起こったことは記憶に新しい。
やはり内外における言語教育は、中国政府が一貫して推し進める国策遂行上の重要な柱と言えるだろう。
そこで興味を持つのが、中国国内では日本語教育を通じてどのような日本イメージが描かれていたのか、である。
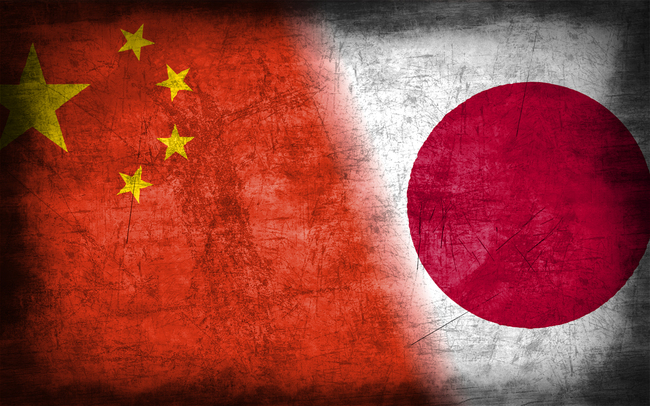
かつて中国は誰もが気軽に観光旅行に出掛けられるわけはなく、国交がなかったゆえに現在のように直航便で簡単に往来することなどできはしなかった。中国政府の招待を受けた「日中友好人士」だけが、香港を経て入国を許されたのである。
そんな時代の中国旅行を題材に、「日本語の口頭通訳工作者と学習者に日本語会話の規範を示し、同時に一般の日本語学習者と教授者の参考に供する」ことを目指して、『日語会話』(周浩如編 商務印書館 1963年)が出版されている。
『日語会話』出版の1963年前後に、中国は1958年に毛沢東が掲げた大躍進政策の失敗から立ち直りを見せるとうになる。政策失敗の責任を取って政治の第一線から後退した毛沢東に代わって国家主席に就いた劉少奇が鄧小平と手を組んで、毛沢東の唱えた急進的社会主義化路線を緩和することで国家的危機を脱することに一先ずは成功した。
その結果、劉少奇が国民的支持を集めたことから毛沢東の“嫉妬”を招き、やがて文革発動へと繋がった――『日語会話』の出版は、劉少奇の影響力が毛沢東のそれを上回る勢いを持ち始めた時期に当ることになる。
冒頭の「(1)深圳の橋の袂で」の「失礼ですが、日本××代表団の皆さんでしようか?」との出迎えの挨拶から始まり、入国手続きを経て各地を旅行した後、北京で帰路の香港行き列車に乗り込むまでの「日本語会話の規範」には、当時の両国を包む政治情勢が色濃く反映されている。会話教科書ではあっても、飽くまでも政治教育の手段なのだ。
「(中国国内の至る所で)スローガンを拝見して、こうしてお話をうかがっていますと、なんですか新しい社会に来たのだという感じで、身が引締まるようですわ。“共産主義は楽園だ”――希望に満ちた、とても明るい感じですわ!……忘れないうちにノートしていかないと」と口にしたのは日本からの「婦人外賓」である。
日本人男性の「外賓」は中国を移動中の列車の中で第三世界からの訪問客を眼にし、「アジア・アフリカの方たちのようですね。こんど北京に参りましてから、人民中国の成立が、民族独立のために闘っている、特にアジア・アフリカの各国人民にとつて、どのように大きな意味を持っているかということを痛切に感じさせられました」。
極め付きは、天安門広場における次の会話だろう。
「日本の方達の新安保条約反対を支持する百万人を越えた集会もここで催されたのです」と「通訳」が語り掛けると、日本からの「婦人外賓」は「ええ、聞きました。中国の皆さんの力強い声援で、私達どれだけ勇気づけられたか知れませんわ。王さん、天安門は、もう新中国の象徴なばかりでなく、今では私達日本人の、いえ、平和を愛する世界中の人々の心の中のシンボルになっていますよ」。
中国は「新しい社会」で「希望に満ちた、とても明るい感じ」であり、「“共産主義は楽園”」であり、「人民中国成立」は世界史的意義を持ち、天安門は「平和を愛する世界中の人々の心の中のシンボルになって」いる。「中国の皆さんの力強い声援」によって、日本における反米闘争(=「新安保条約反対」)が「どれだけ勇気づけられたか」――これが、当時の中国が自国民に植え付けようとしていた日中関係に関するイメージではなかったか。
当時の日本では国会における圧倒的議席差を背景にした自民党単独政権によって、内政面では高度経済成長路線を推し進め、外交面では「新安保条約」を柱に親米・反中路線を掲げていた。
それだけに、『日語会話』の行間から中国政府の対日姿勢が窺うことができるだろう。親米・反中を反米・親中に、である。
やがて中ソ国境で大掛かりな武力衝突が勃発し(1969年3月)、毛沢東が第9回共産党全国大会で文革の勝利を宣言し(1969年4月)、毛沢東が「中国のフルシチョフ」と仇敵視した劉少奇が河南省で横死し(1969年11月)、毛沢東との権力闘争に敗れた林彪が夫人と共にモンゴルで“不審死”を遂げ(1971年9月)、ニクソン米大統領が訪中し北京の毛沢東邸の書斎で米中首脳会談が行われ(1972年2月)、田中首相訪中によって日中国交正常化へと進む(1972年9月)――中国をめぐる内外情勢に激変の兆しが見え始めた。
そして北京に日本大使館が開設された同じ1973年1月、『日語』(北京大学東語系日語教研室編 商務印書館)が出版されている。
『日語』の内容を見ると、「毛主席は にこにこしながら、よく 勉強して、党と 人民に忠誠を つくす のだよと 言われた」など時代を反映させた例文と共に、「わたしたちは 中日両国人民の 友好と 経済・文化交流の 働き手と なる ために、日本語の 勉強に 全力を つくす 決心です」と日本語学習の目的が記されている。
同じ年、上海ではラジオ講座用の『日語 にほんご 上海市業余外語広播講座 第一、二、三、四冊(試用本)』(復旦大学日語教研組編 上海人民出版社 1973~74年)が出版された。
ところで、どれほどの人々がラジオ講座で日本語を学んだのか。同書には、出版部数は最多が50万冊で、最少は第四冊の11万部と記録されている。さすがに第四冊となるとグッと少なくなるが、それでも11万部は決して少ない数でないはずだ。因みに、1976年出版の朝鮮語独習書『朝鮮語自学読本』(延辺人民出版社)の出版部数は3万部である。ここからも、当時の上海における日本語学習熱がある程度は想像できそうだ。
『日語 にほんご 上海市業余外語広播講座』の出版元が文革派出版メディアの総本山と目される上海人民出版社であるだけに、例文には北京の商務印書館『日語』とは比較にならないほどに過激な文革イデオロギー色に染め上げられている。
第一冊の冒頭には、「外国語は人生の闘争における一種の武器である」(マルクス語録)が、次いで「教育は無産階級の政治に服務し、生産労働と結びつかなければならない」「日本人民と中国人民は共に好き友人である」(毛主席語録)が並ぶ。
発音練習の最初が「あかはた アカハタ 赤旗 紅旗」。しばらく進むと「どくさい ドクサイ 独裁 専政」。
第十三課まで進むと、難しそうな表現が加わる。たとえば「あなたがたも 大きな 意気込みで 『農業は 大寨に 学ぶ』運動を 繰り広げて いますね」。
ところどころに歌が入るのは、息抜きのためだろう。たとえば「『あいうえお』の歌」の歌詞は「あいうえお かきくけこ〔中略〕わいうえを 革命のために 日本語を習いましょう」。ということは、飽くまでも「革命のために 日本語を習いましょう」なのである。
二冊目に入ると難易度は増す。
「第九課 毛主席万歳」では「毛主席は 中国人民の 偉大な 指導者です。毛主席は わたしたちの 救いの星です。わたしたちは ほんとうに 幸せです。(中略)わたしたちは 声高らかに 叫びます。偉大な 指導者 毛主席 万歳! 万万歳!」。
以下、「第十四課 赤軍のわらじ」「第十五課 上海工業展覧会」「第十六課 人民公社へ行く道で」と表題を挙げただけでも“革命的な内容”が想像できるだろう。
四冊目になると、たとえば日本文の中国語訳の問題を見ても、「われわれは青年をマルクス・レーニン主義、毛沢東思想で教育し、断固として労働者、農民と結びつく道を歩むようはげまさなければならない」とか、「社会主義制度を樹立、強化し、発展させるには全国人民を団結させ、プロレタリア階級独裁のもとでの継続革命を長期にわたって堅持しなければならない」など、急激に難易度が増す。
当時、中国で「革命のために 日本語を習」った人々は、今頃はどうしているだろう。まさか日本人に向かって、「プロレタリア階級独裁のもとでの継続革命を長期にわたって堅持しなければならない」などと熱く語り掛けてはいないと思うが。
文革も幕を閉じ、鄧小平の剛腕によって対外開放が進み、経済を軸に日中交流の裾野が大いに広がる。やがて「世界の工場」を脱し、「世界最大の消費市場」へ。

















