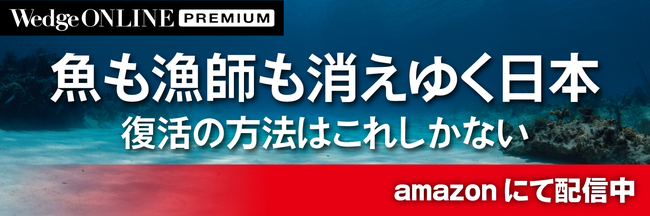科学的根拠なき捕獲拡大
捕獲の拡大は、本来的には業界関係者が最も喜んでしかるべきものである。事実、捕鯨操業会社からは歓迎の声が上がっている。ただ、これについては、本来捕鯨をこれまで最も強く推進している関係者のなかから、異議を唱える声が上がっている。
元水産庁幹部で国際捕鯨委員会に長年出席し、反捕鯨国やNGO相手に歯に衣着せぬ物言いで交渉に当たったことで知られる小松正之・生態系総合研究所代表理事は「拙速だ。科学的な調査が公表されておらず、判断できない」「手続き的におかしい」と批判している。また、これまで最も捕鯨を推進してきたある関係識者からも「国民を愚弄している」などといった激しい言葉を私自身聞いたことがある。
こうした奇妙な反応が上がる理由はなぜか。それは、これまで踏襲されてきた手続きから逸脱しており、このクジラの捕獲を是とする科学的な知見がほぼ何も提供されていないからである。
これまで捕獲の対象とされてきたクジラの捕獲枠については、いずれも推定資源量がIWCから公表されており、日本は自らが過去に実施した調査と合わせるかたちで推定資源量を算出し、IWCで採用されている捕獲枠算定方式(「改訂管理方式(RMP)」と呼ばれている)を若干修正するかたちで算定している。また、外国からの科学者も招聘したレビューパネルを設置、ここでの検討結果も適宜取り入れるというかたちがとられてきた。
現在、捕獲の対象とされているイワシクジラは年間で25頭の枠しかついていないが、これは、当初案ではこの種が1つの系統群から構成されているとの前提が採用されていたところ、レビューパネルで3系統群である可能性があるとの勧告を受け、資源確保のために枠を下方修正させた結果である。積み上げられてきた科学調査やデータをベースとし、段階を踏んだうえで、最後の段階で水産政策審議会という水産庁の諮問機関に諮ったうえで決定している。
これに対して、今回新たに捕獲対象となることが予定されているナガスクジラは、IWCのウェブサイトにも水産庁のサイトにも、また水産庁の関係機関でありわが国で漁獲される水産資源などの評価を担っている水産研究・教育機構のサイトにも、どこにも推定資源量が公表されておらず、このことは水産庁の捕鯨担当責任者も認めるところである。ナガスクジラについては、IWC科学委員会で合意された推定資源量はなく、また水産研究・教育機構や日本でクジラを長年研究しIWCに日本が加盟していた際に調査捕鯨を担ってきた「日本鯨類研究所」でも、ナガスクジラの捕獲を正当化する十分な科学的蓄積があるとは聞かない。データがどこにも明らかにされていないのである。
日本では総漁獲枠(Total Allowable Catch: TAC)を決定する際、水産研究・教育機構で資源調査と評価が行われ、およそどれだけの資源があるのか、そこから鑑みてどの程度の捕獲枠が既存の漁獲枠算定ルールに照らすと妥当なのかが算出される。そしてこれは同機構のウェブサイトから公表され誰でも見ることができる。
調査と評価を積み重ねたうえ、その評価結果が公表されてから数カ月後に、ようやく最終段階として水産政策審議会に諮られる。ナガスクジラの捕獲枠の決定のありかたは、通常のわが国における漁業資源の漁獲枠算定のあり方からも逸脱している。
最終的に諮られる水産政策審議会資源管理分科会は、主として漁業団体の代表によって構成されており、学識経験者としては現在4人がメンバーに加わっている。しかし鯨類学者は一人もいない。「何もわからない素人集団に諮って錦の御旗にすることが妥当と言えるのか」との批判が本来捕鯨を推進するはずの側の一部識者から聞こえてくる。
水産庁によると「鯨類を含むすべての水産資源は、科学的根拠に基づき持続的に利用すべき」というのが「鯨類の利用に関する我が国の基本的立場」とされている。これまで捕獲対象としてきたクジラの場合やその他の総漁獲枠を管理している水産資源とも全く異なる。何の科学的根拠もこれまで示していない今回のナガスクジラの事例は、この原則に反するのではないのだろうか。非科学的との誹りを免れないのではないのだろうか。だからこそ、捕鯨推進を求めてきた一部の識者から、強い批判の声が上がっているのである。