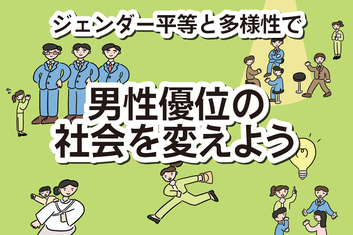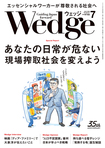レイチェル・ニューワー
日本中に存在するコンビニエンス・ストアで、大量の食べ物が廃棄されている。ニューヨークを拠点とするフリーランスの科学ジャーナリスト兼作家のレイチェル・ニューワー氏は東京で、この現状を変えようとする活動家たちに会った。
東京で高校を卒業したばかりの森永理子氏は、週末の夜を友達と過ごすことが多い。しかし今年の2月3日は違った。この土曜日は、日本人が冬から春への変化を祝う「節分」の日だった。そして、とりわけ大量の食品が廃棄がされる日でもある。
節分になると毎年、日本中の店が「恵方巻」という祝いの巻きずしを店頭に並べる。そしてその日の夜には、数十万本の恵方巻がごみになる。
「お店は常に、お客さんが欲しいものを提供します。つまり、いつでも陳列棚がいっぱいになっている必要があります」と、森永氏は言う。「これが食品ロスの問題につながっています」。
今年の節分の日、森永氏を含む数十人のボランティアは、日本各地のコンビニ101店舗を訪れ、午前9時以降に陳列棚に残っていた恵方巻の数を数えた。結果は衝撃的な数だった。森永氏が渋谷駅近くのファミリーマートに午後9時6分に立ち寄った時、恵方巻は72本残っていた。午後9時18分に訪れたセブン-イレブンには、93本残っていた。
森永氏らが集めたデータをもとに、食品ロス問題のジャーナリスト、井出留美氏が調査結果を取りまとめたところ、日本の5万5657軒のコンビニエンス・ストアが、7億~8億円相当の恵方巻、94万7121本を廃棄したとの推計が出た。井出氏は、この隠れた問題に対する認識を高めるため、ニュースサイト「ヤフージャパン」に、この結果を掲載した。
恵方巻は単発的な問題にとどまらず、日本における幅広い食品ロス問題を象徴するものとなっている。また、この国のいたるところにあるコンビニエンス・ストア、略して「コンビニ」が、いかに食品ロス問題に特に大きくかかわっているかを、浮き彫りにしている。
日本では多くのコンビニが年中無休で営業しており、寿司やサンドイッチ、弁当など、新鮮な食品をいつでも手に入れることができる。そして「コンビニエンス」つまり「便利」の背景に、「消費者が知らない、大量のごみ」が積みあがっているのだと、井出氏は言う。
私は東京で、井出氏と森永氏と一緒に、夜のコンビニをいくつかめぐった。陳列棚にはいつも通り、おにぎりやサンドイッチ、サラダ、電子レンジで調理する食べ物や甘味類が並んでいる。このうちのいくつかは、夜が終わるまでに誰かのものになるだろうが、遅い時間なだけに、多くの食品がごみ箱に捨てられる可能性が高いと、森永氏は言う。
「食べ物を捨てることが当然になってしまった。それが問題の一部です」
コンビニにおける食品ロスの正確な規模を測るのは難しい。どの企業も通常、廃棄する食品の量について公表していないからだ。大手のセブン‐イレブンとローソンは「BBC.com」の取材に対し、店舗から出る食品ロスの量は開示していないと回答した。
ファミリーマートは公式サイトに、「2022年度においては、店舗から日常的に排出される廃棄物量が26万587トン、うち食品廃棄物が5万6367トン」だったという検証結果を掲載している。
日本の公正取引委員会は2020年9月、大手コンビニチェーンについて、1店舗につき年間平均468万円相当の食品を廃棄しているとの推計を発表した。全体では、約2600億円超に達するという。
「日付が変わる直前に、たくさんの恵方巻が売れ残っていて、それを捨てています。こんなことはおかしい」と井出氏は言う。
しかも日本は、食料の63%を海外からの輸入に頼っているのだ。食品ロスの影響は金銭や資源の無駄遣いだけではない。製造や流通、そして廃棄の各段階で排出される温室効果ガスが、気候変動に寄与している。日本では、ごみは基本的に焼却処理されている。
国連が定めている「持続可能な開発目標(SDGs)」の一環として、日本は2030年までに食品ロスを、2000年の980万トンから490万トンまで半減させるとしている。そして、状況は改善へと進んでいる。可食部の食品廃棄は、2012年の最大640万トンから2021年には523万トンに減少した。しかし、一部の活動家たちは、日本はまだ十分に対応していないと話す。たとえば、食品ロスと廃棄に関するSDGでは、各国は2015年のレベルに基づいて目標を設定すべきだと規定されている。2000年、つまりロスが多かった時期にさかのぼることで、日本政府は「ごまかしの手口」を取っていると、井出氏は指摘する。
井出氏をはじめ複数の人が、コンビニの食品ロス対策を重要な第一歩に据えた、さらに本格的な改革を求めている。この問題に必要な解決策の一部は日本特有のものだが、他の国でも応用できる対策もある。
コンビニ側のコスト
井出氏が食品ロスの深刻な問題に気付いたのは2011年、東日本大震災が起きた時だった。井出氏は当時ケロッグ・ジャパンで働いており、寄付された援助物資を避難所に届ける仕事を上司に任された。そこで井出氏は、避難所に運ばれた食料が、必要な人の手に渡るどころか、ごみ箱行きになることが多いことにショックを受けた。
ボランティアがたくさんの弁当や冷凍パン、加工食品を届けたが、「同じ食品だけどメーカーが違うから、平等ではないので配らない」、「避難所の人数にちょっと足りないから(平等に配れないので)配らない」など、杓子定規なお役所仕事や形式的な「平等」が重視され、非常時の食料が配布できず、だめになった。これについて井出氏は、「被災者の人が、1個のおにぎりを4人で分け合ったりしているときに、こんな理不尽な理由で食品がだめになるのは理解できなかった」と話す。
この出来事をきっかけに、井出氏は問題に深く切り込もうと決めたという。自分の見聞きしたことに憤慨した井出氏は、ケロッグを退職し、食品ロス問題の解決に専念するようになった。それから10年以上がたち、今や日本ではこの問題に関心を持つほとんど誰もが、メディア出演や著書、記事、全国各地で開催されるセミナーを通じて井出氏を知っている。森永氏が言うように、「井出さんはとても有名な人」なのだ。
しかしコンビニ関係者にとって、業界批判を重ねる井出氏は「日本で最も嫌われている人物の一人」なのだと、セブン-イレブン・ジャパンの本部社員で、コンビニ関連ユニオンの委員長を務める河野正史氏は言う。
しかし、この問題をなんとしても解決しようと取り組んでいるのは、井出氏だけではない。井出氏は、問題を懸念して仕組みを変えようと同じように意欲を燃やす、多くの市民や業界関係者と協力している。不透明な業界慣行がどうやって食品ロスにつながっているのか、大勢が協力して解明してきた。
森永氏と同様、高校を卒業したばかりの金城さくら氏も、井出氏に協力する一人だ。金城氏は、食品ロスに関心を持ち、大阪にある大手コンビニチェーンの小さな店舗でアルバイトを始めた(金城氏は、勤め先を明らかにしないよう求めている)。金城氏によると、閉店の約1時間前から、店員は陳列棚から食品を下げ始める。通常は1日に当たり50~70点で、寿司や弁当、おにぎり、サンドイッチ、スイーツ類などだ。
まだ捨てる必要がないものをごみとして扱うことについて、「食べたくても十分に食べられない人がいることを思うと、心が痛む」と、金城氏は話した。
陳列棚から下げた食品は全てごみ箱に行くが、まだ完全に食べられる状態だ。これは、顧客に新鮮な食品を届ける戦略として、消費期限ではなく、製造から消費期限までの期間の3分の2を過ぎた段階で廃棄すると決まっているからだという。
「中には、消費期限の3~4日前に捨てる商品もあります」と、金城氏は言う。
従業員は廃棄予定の食品を食べてはいけないし、持ち帰ってもいけない。なぜなら、店側は従業員にも食品代を払ってほしいからだ。
廃棄のための追加コスト
食品を棚から早めに外すため、消費者は二重の負担を強いられていると井出氏は言う。早期廃棄に当然伴う損失を補うため、価格は高く設定されているし、地域のごみ焼却には税金も使われるのだと。
「食品廃棄に対し、食料品価格と焼却費用の税金と、二重に負担して損していると消費者が認識すれば、考え方や行動は変わるのではないでしょうか」と井出氏は言う。
食品ロスが自分個人の経済活動にどう影響するのか、ほとんどの消費者にとっては分かりにくいことかもしれない。しかし、コンビニのフランチャイズオーナーにとっては大きな問題だ。
加盟店は本部から食品を仕入れ、廃棄品の処理費用の大部分を負担している。セブンイレブンの広報担当は、加盟店が食品廃棄物の処理費用の85%を負担し、本部が負担するのはわずか15%だと認めた。コンビニ関連ユニオンの河野氏は、加盟店は仕入れたすべての商品の代金を本部に支払うため、商品が売れようが捨てられようが、本部は利益を得るのだと付け加えた。
このいわゆる「コンビニ会計」の仕組みが、日本のすべてのコンビニチェーン店に導入されている。そして井出氏によると、この仕組みがあることでコンビニ本部としては加盟店に過剰発注を促した方が得になるし、それが食品ロスを助長する。河野氏も、「本部が店舗に多くの食品を供給すれば、それが無駄になるかどうかは別として、本部の利益は増える」と述べた。「本部の立場からすれば、ロスも利益の一部だ」。
(編集部注:公正取引員会は「コンビニエンス・ストアのフランチャイズ契約においては、売上高から売上原価を控除して算定される売上総利益をロイヤルティーの算定の基準としていることが多く、その大半は、廃棄ロス原価を売上原価に算入しない方式を採用している。この方式の下では、加盟者が商品を廃棄する場合には、廃棄ロス原価を売上原価に算入した上で売上総利益を算定する方式に比べて、ロイヤルティーの額が高くなり、加盟者の不利益が大きくなりやすい」との見方を示している)
これに加えて、店舗オーナーは日常的な商品の過剰発注や、年々増加する季節商品の販売増というプレッシャーに直面していると河野氏は言う。河野氏によると、セブンイレブン本部が昨年12月、全フランチャイズ店舗に対し、節分に向けて前年の1.5倍の恵方巻を注文するよう促す通知を送ったのだという。また、日本では通常12月24日か25日に食べるクリスマスケーキについても同様だという。
「本部は毎年、(クリスマスケーキの)目標数を前年より高く設定します」と河野氏は言う。「そして、目標は達成されなくてはなりません」。
一部の加盟店は、目に見える無駄を最小限に抑え、目標を達成するために、季節限定商品の売れ残り品を店側が個人的に買い取っているのだと、河野氏は説明する。ある組合員は河野氏に、恵方巻約100本を買い取る羽目になったと言い、また別の組合員はクリスマスケーキ25個を持ち帰ったと、河野氏に話したのだという、
セブン-イレブン・ジャパンの広報担当者は、フランチャイズ店に対するノルマの存在を否定する。
これについて河野氏は、加盟店が本部からの指示に従う法的義務はないという見解に同意しながらも、実際にはほとんどの加盟店が従っていると話す。「これは権力構造の問題です。本部が何か言えば、加盟店はほとんど従わざるを得ないので」。
だが一部のコンビニは、これまでと違うやり方に取り組んでいる。
店舗での実験
東京都豊島区に、ほかの店舗とは一味違うコンビニがある。一見するとローソンなのだが、よく見ると何かが違うことに気づく。
私が訪れたのは雨の降る春の日だったが、この店舗では、ローソンのトレードマークの鮮やかな青と白のロゴが、国連が掲げるSDGsの目標ごとに色分けされた虹色のまだら模様に置き換えられていた。ガラスのドアをくぐると、店内の陽気なロボットが日本語で説明してくれた。ここは「グリーンローソン」の旗艦店で、廃棄物の削減を目指す実験店舗なのだという。
「私たちは、コンビニがSDGsの達成にどう貢献できるのか示したい」と、ローソンコミュニケーション本部広報部のシニアマネジャー、杉原弥生氏は言う。杉原氏のチームは、こうした目標を達成するためにさまざまな対策を導入しており、中には思い切ったアプローチも含まれているという。
たとえば、従業員が棚に陳列する生鮮食品の量や種類は、天気予報や時事問題、過去の売上実績といった要素を使った予測アルゴリズムを持つ人工知能(AI)システムによって決定される。このAIは、売れ行き不振の商品を棚から移動させるために割引時期も決定する。
技術に頼らない対策もある。この店では、通常のオープンタイプの冷蔵庫や冷凍庫を使わず、ドア付きの設備で冷気を逃がさないようにしている。さらに、余った食用油をリサイクルし、生ごみを地元のバイオガス会社に提供している。また、顧客がマイカップを持参すると、少額の割引を受けられる。
来店者が自宅で不要になった紙袋を持ち込み、それを店側店側が店頭で回収し「お買物袋」として再利用してもらう取り組みも実施している。さらに、各家庭で使わない生鮮食品ではない未使用食品を店頭で回収して、フードバンク団体や子ども食堂など、経済的に困窮する人たちのために提供する「フードドライブ」活動も行っている(ただし、寄付用の容器に店自体が食品を入れることはしてない)。
立ち上げ当初には問題もあった。杉原氏によると、レジ袋や使い捨てカトラリーを無料で提供しないことに不満を感じる顧客もいるという。代わりに使い捨ての竹製カトラリーを購入できるが、店内にある多くの商品と同様、これもプラスチックで包装されている。AIシステムは、食品ロスの削減と、魅力的な品ぞろえを実現するために必要な寿司やサンドイッチの十分な在庫確保のバランスを取るのに苦労することもある。
「人は空いた棚を避けるので、うまくいかないことがあります」と、杉原氏は言う。
特に客に強く支持されているというわけでもないため、ローソン本社は今のところ、グリーンローソン店舗を増やそうとしていない。しかし杉原氏は、他の店舗でも、冷凍食品の品ぞろえを増やす、消費期限内ながら販売期限が切れた食品を割引販売する、消費者に棚の一番手前に陳列された食品を選ぶよう促す政府主催キャンペーンに参加するなど、食品ロス削減に向けたさまざまな取り組みを行っていると付け加える。杉原氏によると、ローソンではこれらの方法を含め、さまざまな取り組みにより、2018年から2022年にかけて食品ロスを全体で23%削減した。
井出氏は、ローソンは日本のコンビニチェーンの中で最も進歩的だと考えている。他の企業は変化への対応が遅いものの、いくつかの前向きな動きもある。セブン-イレブンの広報によると、同社では有効期限が近い食品の値引きを加盟店が行うことを認めた。これは、ほとんどの値引きを禁止していた従来のポリシーからの大きな転換だ、と河野氏は言う。
立法においても、前向きな動きがいくつか見られる。2019年には、井出氏によるロビー活動もあり、政府や地方自治体に食品ロス対策を模索するよう求める「食品ロスの削減の推進に関する法律(食品ロス削減推進法)」が成立した。しかし、これは完璧な法律というわけではない。
たとえば、この法律で期限切れの商品をフードバンクに寄付することを企業に奨励している。しかし、寄付した食品で誰かが体調を崩した場合、企業は法的責任を負うことになるため、寄付をためらう企業が多い。この問題を回避する方法の一つとして、金城氏はアメリカで1996年に制定された食品寄付者を保護する「ビル・エマーソン法」の日本版制定を提案している。
金城氏は今年4月に大学の法学部に入学したが、すでに日本を同様の法改正へと導く具体的な一歩を踏み出した。フードバンクや食品会企業、市役所、弁護士、政治家などに働きかけ、この問題について話し合う作業部会を結成するよう呼びかけている。
コンビニの食品ロスに関する経済状況を変えることで、ごみ自体の削減にもつながる可能性があると、井出氏は言う。しかし、ローソンとセブン-イレブンの担当者はBBC.comの取材に対し、「コンビニ会計」方式を変える予定はないと回答した。
それでも河野氏は、フランチャイズオーナーが力を合わせれば、この変更を迫ることができると楽観的だ。河野氏は成功例として、2020年に加盟店が結束して営業時間を独自に設定できる権利を獲得し、本部から24時間営業を強制されなくなった事例を挙げた。
河野氏は、「コンビニ会計」の撤廃が次の目標になるかもしれないと語る。そして、この希望を裏付ける、小さいながらも重要なデータがある。セブン-イレブンの加盟店は交渉の末、2024年の恵方巻の販売目標を前年比95%にした。目標が前年を上回らなかったのは、これが初めてだった。河野氏は、「力を合わせれば、状況を改善できる」と語る。「革命のようなものです」と。
(レイチェル・ニューワー氏の日本での取材は、米社会科学研究会議(SSRC)と日本財団ニューヨーク支部が運営する「安倍フェローシップ・プログラム」の助成金が支援した)
(英語記事 Japan has an excess sushi problem. These food waste activists put it in numbers)