医師の偏在は、表面的な施策で解決できるほど単純ではない。そこには、根深い構造的な問題が横たわっている。
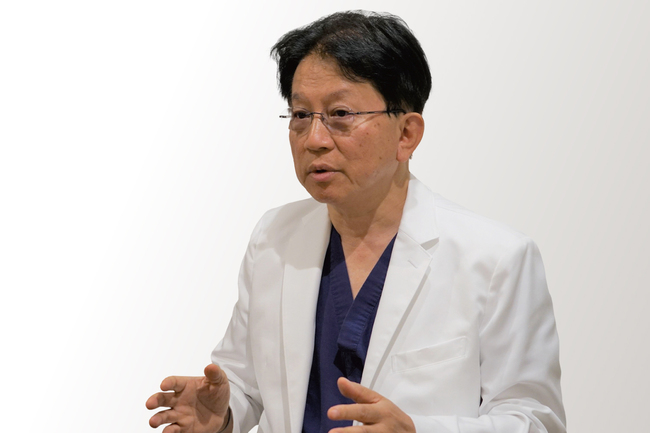
心臓血管外科医 ニューハート・ワタナベ国際病院総長
1958年、東京生まれ。金沢大学医学部卒業後、同大学第一外科に入局。89年より独ハノーファー医科大学胸部心臓血管外科に留学。帰国後、富山医科薬科大学(現・富山大学医学部)に移り、2000年より金沢大学心肺・総合外科の主任教授に就任。05年より、東京医科大学心臓外科教授を兼任。14年にニューハート・ワタナベ国際病院を設立し、現職。
「人生において何を優先するか」という価値基準は時代とともにシフトし、若者たちは一見、自律的に進路を選んでいるように映る。しかしその背後には、しばしば「親」という見えざる力が存在する。
かつて、医師を志す動機は「世のため、人のため」という公益性に根ざしていた。私自身、親から「人のためになりなさい」と言われ、命に直結する「心臓外科」を選んだ。だがいつしか、医師は「高収入で安定した専門職」という認識が強まり、こうした職に子どもを就かせたいという親の意向が色濃く出るようになった。そして、いざ医師となった後も、「大変な診療科を選んで大丈夫?」といった暗黙の誘導が続く。もはや親が子を思う〝善意〟という名の見えない〝呪縛〟だ。
今、特に医師不足が顕著な小児科、産婦人科、外科は、いわゆる「大変」な科だ。だが、医師としてのやりがいは本来、大変さと表裏一体にあるはずである。やりがいや生きがいとお金が天秤にかけられ、前者を取る人が減ってしまったことは嘆かわしい。
ただ、医師の「やりがい」が揺らいでいる背景には、医師がかつてのような社会的尊敬を享受できなくなったという現実もある。医学部の大幅な定員増や新設によって、人口あたりの医師数は増加し、医師は希少な存在ではなくなった。加えて、裏口入学や不正入試などの不透明な選抜の実態が明るみになり、医師の質そのものに疑念の目が向けられるようになった。
こうした価値観の問題に加えて、制度そのものにも偏在を助長する深刻な欠陥があると感じている。
その一つが、研修医が2年間かけて複数の診療科を回る初期臨床研修制度だ。いわば〝モラトリアム〟の期間が生まれたのである。
たとえ志が高くとも、現場に直面すれば「本当にこの道でよいのか」と迷うのが人間というものだ。私たちの時代は、勢いのまま入局した感も否めないが、結果的にはそれが正解だったと思っている。
〝他人〟を助ける
医師が持つべき資質
日本では「偏差値の高い者が医師になる」という感覚が根強いが、医師の資質は学力だけで測れるものではない。
体力、忍耐、協調性など多様な能力が求められる中で、私が最も重視しているのは「優しさ」だ。
医師は、家族でも知人でもない〝他人〟を治す仕事である。困っている人を目の前にし、たとえ一瞬でも「助けたい」と思えないなら、その職に就くべきではない。診療科の選択も、知名度や難易度ではなく、「自らの得意分野」に即して考えるべきだ。
私は手先の器用さを生かし外科を選んだ。「会話」が得意なら、それを武器にできる診療科がある。自分の強みを最大限に生かすことが、自らにとっても社会にとっても最も価値を生む。
職業は人を育て、その姿が次世代へと継がれていく。私はこれからも、人のために生きていきたい。
渡邊 剛
あさ出版 1540円(税込)
血管の老化について、心臓疾患におけるロボット手術のスペシャリストである渡邊剛氏がその中を流れる〝血液〟の整え方から徹底解剖する




















