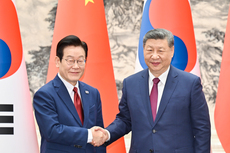賃上げを単年度の業績で判断すれば、それはどうしても「景気対策」になる。世の中の流れに合わせて上げ、厳しくなれば抑える。合理的ではあるが、そのやり方では社員にとって賃金は常に不安定なものになる。
一方で、賃上げを「この会社で働き続けることの前提」として捉えるなら、判断の基準は変わる。価格設定、投資の優先順位、成長のスピード――すべてを、人を抱え続ける覚悟から逆算する必要が出てくる。
春闘の数字は、その違いまでは映し出さない。だが26年春闘は、賃上げを「景気の結果」として扱う経営と、賃上げを「経営の意思」として引き受ける経営とを、はっきりと分ける節目になるだろう。
賃上げとは、環境が良いから行うものではない。どの時間軸で会社を続けるのか――その覚悟が数字となって表れているにすぎないのである。
「いい会社をつくりましょう」という覚悟
この問いに、長年にわたって真正面から向き合ってきた企業がある。寒天メーカーの伊那食品工業だ。同社が掲げる社是は「いい会社をつくりましょう ~たくましく そして やさしく~」である。
ここでいう「いい会社」とは、業績が良い会社のことではない。社員、家族、取引先、地域社会――会社を取り巻く人たちが、日常会話の中で「いい会社だね」と語ってくれる存在であること。その中心に据えられているのが、社員一人ひとりの幸せを追求することだ。
この理念を具体的な経営のかたちに落とし込んだものが、同社のいう「年輪経営」である。木が1年に一層ずつ年輪を重ねるように、無理な成長を求めず、着実に基礎体力を積み上げていく。売上や規模の拡大よりも、社員の成長、組織の成熟、信頼の蓄積を優先する。伊那食品工業にとって、賃金はその年輪の一部であり、削って調整する対象ではなかった。
多くの企業では、賃上げは「儲かったからできること」として語られる。業績が良ければ上げ、苦しければ見送る。短期的には合理的だが、その判断を繰り返せば、賃金は常に不安定なものになる。
伊那食品工業は、この考え方を取らなかった。不況期であっても安易な賃下げを行わず、賃金を経営の調整弁にしなかったのである。
その背景にあるのは情緒論ではない。社員が安心して働き続けられなければ、良い仕事も、良い商いも生まれないという、きわめて現実的な経営判断だ。