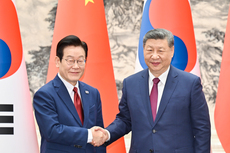同社の評価軸は明確である。短期の売上や利益よりも、社員が長く働き続けられているか。現場に改善と学びが積み重なっているか。無理な拡大によって、組織に歪みが生じていないかである。
賃金は、こうした評価軸の結果として位置づけられている。「頑張ったから上げる」のではない。「頑張り続けられる状態をつくる」ために、賃金を守る。この順序の違いが、年輪の厚みとなって会社に刻まれてきた。
年輪は一朝一夕では太くならない。しかし、削らずに守り続けた年輪は、企業が揺らいだとき、確かな強度となって表れる。伊那食品工業の賃金観は、そのことを物語っている。
賃上げを前提に経営を組み替えてきたか
伊那食品工業の事例に触れると、こう感じる経営者もいるだろう。「立派だが、うちとは条件が違う」「業種も規模も違う」というその感覚は、決して間違っていない。同社の経営を、そのまま自社に当てはめられる企業は多くない。
しかし、問うべきは「同じことができるか」ではない。問われているのは、賃上げをどう位置づけてきたかである。
賃上げを、業績が良ければ行う「成果配分」と考えてきたのか。社会要請への「対応策」として捉えてきたのか。それとも、経営の前提として「引き受けるもの」として扱ってきたのか。
その違いは、日々の意思決定に表れる。価格を上げるべき場面で、顧客の反応を恐れて先送りしてこなかったか。付加価値を高める投資より、短期的なコスト削減を優先してこなかったか。人を「調整できる資源」として扱ってはいなかったか。
賃上げが難しい理由は、往々にして「原資がないから」ではない。賃上げを前提に、商いの構造を組み替える決断をしてこなかった結果である。
春闘の数字が高水準で推移しているのは、景気が良いからだけではない。人が集まらず、人が定着しない。その現実が、企業に選択を迫っているのだ。
賃上げは、経営者にとって避けて通れない負担である。同時にそれは、どんな会社を未来に残したいのかを示す宣言でもある。その宣言を、あなたは自分の言葉で語れるだろうか。
今の余力の結果ではなく
どんな未来を
選ぶかで決めるものだ