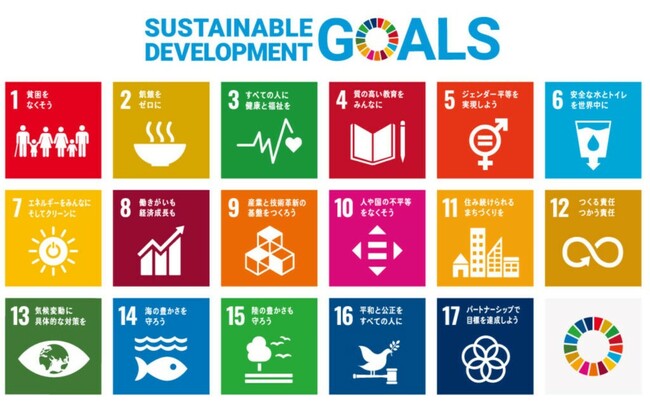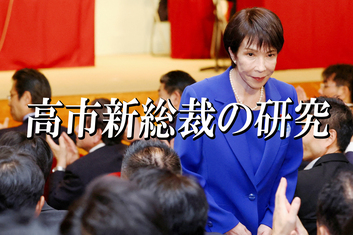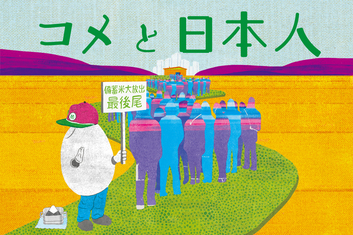一方で、表示をしてトレースすればメリットがあります。それは、品質事故等があった場合に、非が無いことを証明したり、ロットを分けて被害を最小限にしたりといったことができるからです。しかし、日本の場合はあえて隠すわけです。そもそもの発想が違うので、これではトレースが進むはずがありません。
やらなくてはならないトレーサビリティ
日本で不正な水産物を流通させないようにすることは可能です。そのためには、国産品をバーコードなどでトレーサビリティを徹底させること。輸入品においては「漁獲証明」を要求することの2点が必要になります。すでに写真で示しましたが、ノルウェーなどの北欧からは、輸出側が進んでトレースしています。
国産水産物は、漁業法改正(20年〜)により、今後、漁獲可能量(TAC)、個別割当(IQ)魚種が増えることで、資源管理が強化されて行く見通しです。その際の逃げ道を断つことが不可欠です。国内での密漁を含むIUU漁業は、資源に悪影響を与えています。トレーサビリティによりそれらを完全にブロックするのです。
EUなどでは、IUU漁業の輸入排除を徹底しています。そのおこぼれが、管理が甘い日本に輸出されるのを遮断することは、SDGsを採択している国として当然のことです。
ちなみに、IUU漁業による水産物の流通は日本に限ったことではありません。しかしSDGs14のターゲットではそれを終らせようとしています。筆者が世界のあちらこちらで見て来た日本の姿勢との大きな違い、それはトレーサビリティによって悪循環を止めていることです。
不正な水産物を排除し水産資源を守るために、日本の対応が急がれます。

『Wedge』2022年3月号で「魚も漁師も消えゆく日本 復活の方法はこれしかない」を特集しております。
四方を海に囲まれ、好漁場にも恵まれた日本。かつては、世界に冠たる水産大国だった。しかし日本の食卓を彩った魚は不漁が相次いでいる。魚の資源量が減少し続けているからだ。2020年12月、70年ぶりに漁業法が改正され、日本の漁業は「持続可能」を目指すべく舵を切ったかに見える。だが、日本の海が抱える問題は多い。突破口はあるのか。
特集はWedge Online Premiumにてご購入することができます。
四方を海に囲まれ、好漁場にも恵まれた日本。かつては、世界に冠たる水産大国だった。しかし日本の食卓を彩った魚は不漁が相次いでいる。魚の資源量が減少し続けているからだ。2020年12月、70年ぶりに漁業法が改正され、日本の漁業は「持続可能」を目指すべく舵を切ったかに見える。だが、日本の海が抱える問題は多い。突破口はあるのか。
特集はWedge Online Premiumにてご購入することができます。