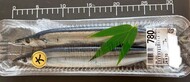-
 2026/02/13 片野 歩
2026/02/13 片野 歩シシャモが大漁です。日本ではなく、アイスランドのカラフトシシャモです。日本がほとんど水揚げされなくなっている中、アイスランドやノルウェーでは漁獲量が多く、魚価も日本が30倍以上となっています。なぜなのか?
-
 2026/01/27 片野 歩
2026/01/27 片野 歩世界情勢を見ていて強く感じることがあります。水産物に限らず日本での生産を回復させるMADE IN JAPANへの回帰が必要ということです。
-
 2025/12/24 片野 歩
2025/12/24 片野 歩イクラがサケの大不漁で史上最高価格になっている。温暖化による資源の減少が原因とされるが、世界に目を向けると、サケの資源管理について根本的な違いがあることが分かる。現実を直視してみましょう。
-
 2025/11/28 片野 歩
2025/11/28 片野 歩日本の食卓に浸透しているノルウェーサバの価格に異変が起きている。資源管理のために漁獲量を減らしたためで、日本は国産でまかなうこともできない厳しい状況となっている。
-
 2025/10/02 片野 歩
2025/10/02 片野 歩秋の風物詩サンマは近年、不漁が続いていたが、今年は近年になく好調で、48時間の休漁も行われた。なぜ漁が上向いているのか? その理由を理解していないと、また獲れなくなる事態を繰り返してしまう。
-
 2025/08/18 片野 歩
2025/08/18 片野 歩秋の味覚サンマ。生サンマの刺身を味わう機会はめっきり減ってしまいました。おいしさの指標である脂ののり具合が今一つで、安くておいしい大衆魚から、細くて高い高級魚に変わってしまったサンマは今後どうなっていくのでしょうか?
-
 2025/07/30 片野 歩
2025/07/30 片野 歩「失われた30年」と日本の漁業について、共通の問題があります。それは「事実や問題の本質」が社会に正しく伝わっていないということです。日本で魚が減っている本当の理由を知り、伝えることが必要です。
-
 2025/06/26 片野 歩
2025/06/26 片野 歩人口増加により水産物の需要が世界的に増え続けてる中、漁業を成長産業にしている国々は資源管理をしているため、漁獲量の増加はあまり期待できない。需要を補うのは養殖物。中でも、環境に配慮された陸上養殖に注目が集まる。陸上養殖は供給を補うのか。
-
 2025/05/28 片野 歩
2025/05/28 片野 歩日本の漁獲量減少の原因を「黒潮大蛇行の影響」が挙げられている。環境要因を責任転嫁するのは簡単だが、もっと広い視野で日本の海の周りを眺めると、黒潮大蛇行の影響と漁獲量の関係で様々な矛盾が浮き出てくる。
-
 2025/04/30 片野 歩
2025/04/30 片野 歩魚売り場、外食などで提供できる魚の種類も量も減り続けています。日本の生産量(漁業と養殖)が減り続け、世界の水産物の需要が増加して輸入量も減少しているからです。そして、水産物の生産量が驚くことに、韓国に抜かれそうなのです。
-
 2025/03/31 片野 歩
2025/03/31 片野 歩北太平洋漁業委員会(NPFC)が開催され、サンマの北太平洋全域での漁獲枠を2025年は現行から10%削減で合意した。資源回復へ向けた動きではあるが、資源管理としても、日本としても大きな問題をはらむ。解説していきたい。
-
 2025/02/28 片野 歩
2025/02/28 片野 歩マサバが獲れない状態が深刻化しています。水産庁が来シーズンの漁獲枠を8割減らすことも伝えられている。これは資源量の実態に合った漁獲枠でなかったことが、本質的な問題で、幼魚に至るまで過剰な漁獲が進み、激減してしまっている。
-
 2025/01/28 片野 歩
2025/01/28 片野 歩世界全体で水産物の生産量が増え続けているのに対し、日本では減っている。理由はTACの意味や効果が関係者に正しく理解されていないからだ。TACは設定されても実際の漁獲量より多く、資源管理に効果がないという事態が起きてしまっている。
-
 2024/12/27 片野 歩
2024/12/27 片野 歩年末を迎え、売り場にたくさん並ぶズワイガニのパックに貼られている「バルダイ種」との表示に気づいた人もいるのではないか。ズワイガニの一種なのだが、その表示には深い意味がある。また、日本でも今、たくさん獲れており、好機を生かす必要がある。
-
 2024/11/13 片野 歩
2024/11/13 片野 歩冬の味覚、日本海のズワイガニ漁が11月6日に解禁されました。資源管理が功を奏し、8年ぶりの高水準になっているとも言われていますが、本当に回復しているのでしょうか?大きくズワイガニの資源量を増加させているノルウェーと比較してみましょう。
-
 2024/10/07 片野 歩
2024/10/07 片野 歩日本では大型クロマグロの分類を30キロ以上とし、100キロもあれば大物と思われるが、ノルウェーで水揚げされたマグロは、小さくても168キロ、大きいものは396キロもある。なぜ、ここまで差があるのか。
-
 2024/08/22 片野 歩
2024/08/22 片野 歩2024年8月10日に漁が解禁され、今年もサンマの季節が来た。毎年のように大不漁が伝えられていたが、水揚げが増えていると報道されている。ただ、その値段は1尾18円の店もあれば、1尾7万円で落札する卸しもある。どういうことなのか、解説します。
-
 2024/07/23 片野 歩
2024/07/23 片野 歩土用の丑の日が近くなると、ウナギの話題が出てくるが、日本のウナギ・二ホンウナギは絶滅危惧種に指定されており、資源激減のため、価格の高騰が続いている。「完全養殖」の技術向上が伝えられているが、解決できるのか?その前にできることがある。
-
 2024/06/19 片野 歩
2024/06/19 片野 歩6月に解禁となった北海道南部のスルメイカ漁の初水揚げが函館であり、前年の6分の1のたった200キロでした。“記録的不漁”といった言葉が、漁業では、資源管理制度の不備で枕詞のように毎年繰り返されるようになってしまっています。
-
 2024/05/09 片野 歩
2024/05/09 片野 歩日本人が大好きな魚・サバ。そのサバ資源が危機に瀕しています。しかしながら不漁とはいえゼロにはならず、どこかでサバが水揚げされており、その実感は今一つないのかもしれません。知られていないサバ資源の話をしましょう。
|
|
|