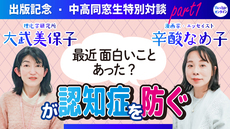人生100年時代に突入している人間に歩調を合わせるかのように、ペットの寿命も延びている。
ペットフード協会の調査では、犬全体の平均寿命は2022年現在、14.76歳、猫全体の平均寿命は15.62歳。1990~91年の調査では、犬の平均寿命は8.6歳だったというから、30年間で6歳以上。犬は人の4~7倍のスピードで歳を取るので、人に換算すると30歳近くも寿命が延びたことになる。
長生を寿ぐ(ことほぐ)という意味で「長寿」というが、人も犬も、長く生きることはめでたいことばかりではない。健康上のアンラッキーで大きいのは「がん」の増加だ。
早期発見が難しい犬のがん
なんと犬のがん罹患率は人間の8倍と言われており、死因のトップでもある。
また、犬は自覚症状があっても言葉で訴えることができないため、しこり、嘔吐、急激な体重減少、血尿等の症状から、飼い主が異変に気づいた時にはがんは相当進行してしまっているケースが少なくない。しかし、決して不治の病ではなく、早期発見して適切な治療につなげることができれば、完治も、天寿のまっとうも不可能ではない。そこも人間のがんと一緒と言える。
だが現状、犬のがんの早期発見は人間よりも難しい。
理由の第一には、早期発見を目的とする「がん検診」が行われていないことが挙げられる。大切な家族の一員といえども、動物病院へ連れて行くのは予防接種の時ぐらい。獣医師から「お変わりありませんか」と尋ねられても、嘔吐や血尿・血便等の症状がない限り、「はい、変わりありません」と答えてしまう。
特に老犬の場合は、食欲がない、痩せてきた、うずくまっていることが多いなど、がんの初期症状に見られる異変も、「老いのせい」と思いこみ、見逃してしまいがちだ。
さらに、諸々の検査にかかる経済的・(ペットに対する)身体的負担の重さも、飼い主にとっては心理的なネックになっている。ペットには公的な健康保険制度がないため、人間であれば軽い負担で済む触診、血液検査、超音波検査、レントゲン検査といった簡易的な検査でも普通に1万~2万円はかかる。
その上、「がんの疑いあり」ともなれば、部位や進行度を特定するためのCTやMRIによる検査に進むわけだが、人間と違って全身麻酔が必要で、犬の身体への負担は非常に大きなものになる。内臓機能、肝機能、血圧の低下や、心不全、呼吸困難などの副作用があり、小型犬や10歳以上の高齢犬は死に至ることもある。費用も5.5~8.5万円と、人間以上に高額となる場合もある(アニコム損保調べ)。