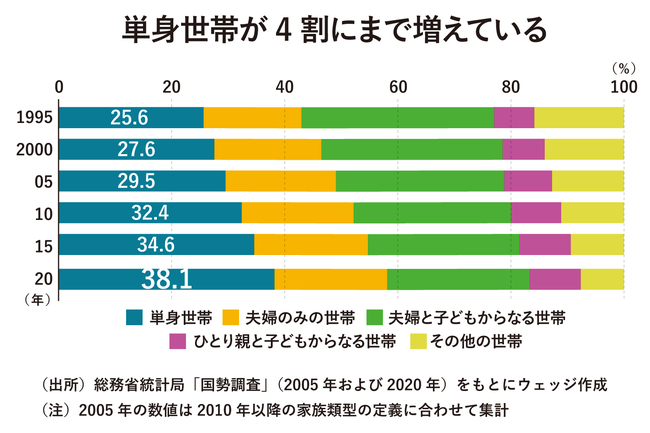かつて日本は農業を中心とした村落共同体が広がり、そこには強いつながりがあった。しかし戦後、都市への一極集中が始まる。高度成長期にコミュニティーの役割を引き受けたのは会社組織だ。社葬や社宅などの制度はその典型だろう。ただ、バブル崩壊後、会社はその役割を担う余裕を失っていく。働き方や人間関係も流動的になり、地域社会も機能しなくなり、日本社会の共同体は空洞化していった。
これまで社会問題を取材してきた立場からすると、昨今生きづらさを訴える人が多いことに気づかされる。もちろん、いつの時代も生きづらさを抱える人々はいたはずだ。けれども、令和はどうも事情が違うようだ。誰もが孤立し得る、「一億総生きづらさ時代」が到来したのではないか。孤独死はその最終形態とも言える。しかし問題は死そのものではなく、そのずっと手前にある。やっかいなのは、個々人が抱える「生きづらさ」はそれぞれバックボーンが異なるという点だ。
全世代が抱える
生きづらさとの向き合い方
私は同世代であるロスジェネ世代の取材を精力的に行ってきたが、印象的だったのはある40代の女性派遣社員の言葉だ。かつてブラック企業で働いていた彼女は「正社員になるのが怖い」と涙ながらに語った。雇用の調整弁として、ぼろ雑巾のように使い捨てられた心の傷は深く、今もなお流動的な働き方しかできていない。中年を迎え、老いが迫る私たちの世代は、将来の不安も相まって大きなリスクを抱えている。
若者たちの生きづらさも深刻だ。弟の孤独死をきっかけにLINEで見守り活動をしているNPO法人「エンリッチ」の紺野功さんは、私に衝撃的なデータを見せた。紺野さんが若者向けに利用動機のアンケートを取ったところ、「孤独死しても誰も頼れる人がいません」「天涯孤独です」という声が殺到したのだ。
SNSの世界は華やかだ。「いいね」「映え」を求めて虚像を作り出す。ただその一方で、本音や自らの孤独を吐き出せる相手はスマホの向こう側にいる顔の見えない「誰か」だったりする。それは令和の生きづらさを現してはいないだろうか。
そんな不穏な時代。でも、人々は新たな「つながり方」を模索しながら懸命に生きている。私はそこにささやかな希望を見出してもいる。
ある60代の男性は、派遣など職を転々としていたが、どれも長続きしなかった。心療内科ではうつ病と診断された。そのため失業保険が切れる頃に、生活保護を決意する。しばらくはカーテンを閉めて、誰とも会話しない日が続いた。
だが、転機が訪れる。それは冬の日に、大雪が降ったことだ。その日を境に勇気を出して、目と鼻の先にある公園の清掃を始めたのだ。ひきこもりの彼にとっては、公園で挨拶をする程度の関係性が心地いい。やがてその輪は広がり、公園の警備員とも親しくなり、いつしか自宅で月1回カレーの会を開くようになっていく。彼は他者との「ちょうどいい距離」を見つけたのだ。