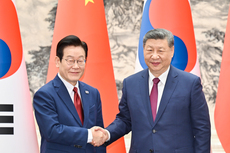④著名人たちの覚悟
私のこの体験は、決して特殊なものではない。先に挙げた著名人たちの選択も、この「覚悟」の表れとして読み解くことができる。
(1)稲盛和夫 ― 経営者の悟り
稲盛氏は「敬天愛人」という強固な哲学を経営の柱としてきた。彼は65歳で得度を決意したが、奇しくもその直前に胃がんが見つかった。京セラのオフィシャルサイトによれば、彼はこれを「仏が与えた試練」と捉え、手術の日を「俗世との訣別の日」と定めたという。そして手術後、臨済宗の僧として過酷な修行に入った。
経営という世俗の頂点を極めた人物が、最後は「個」としての魂の完成を求めたのである。彼が晩年に語った「死を恐れぬ心をつくることが、生を真に輝かせる」という言葉は、まさしく、がんによって死が具体化して初めて得られる、凄みのある境地である。
(2)瀬戸内寂聴 ― 俗を愛した尼僧
瀬戸内寂聴氏は、作家としての名声と愛憎の業(ごう)のさなかにあった51歳で出家した。彼女の場合、がんの発見は出家からずっと後の晩年であったが、その生き方そのものが「生病老死」との対峙であった。
彼女は俗世を離れながら、誰よりも俗世の人間の苦悩を愛し、書き続けた。「この世を愛し抜くことが修行」と語った彼女にとって、がん治療の痛みすらも、その修行の一部であったのだろう。彼女の生き様は、病や老いですらも人生を極めるための糧とし得ることを示している。
(3)高須克弥 ― 医師としての自覚
高須クリニックの院長である高須氏もまた、がんを患い、臨済宗で得度している。医師として多くの患者の「死」を見てきた彼が、自らも「がん患者」となった。彼は医療の限界、すなわち科学や合理性だけでは割り切れない「死の受容」という問題に、当事者として直面したのである。
彼の得度は、西洋医学の最前線に立つ医師が、それとは異なる東洋思想の「受容」や「心の治療」を自身に取り込もうとする、ハイブリッドな試みであったと私は見ている。
(4)香田晋 ― 名声を離れた静寂
人気演歌歌手として脚光を浴びた香田氏も、体調不良とがんの診断を契機に芸能界を離れ、得度した。世俗的な価値観の最たるものである「名声」の渦中にいた彼が選んだのは、僧名「晋照」としての静寂な道であった。
彼の事例は、富や名声がいかに「病」と「死」の前で無力であるかを象徴している。がんという病は、人生の優先順位を強制的にリセットする。彼が選んだ「静寂」は、華やかな舞台の上では決して聞こえなかったであろう、内なる声に耳を澄ますための必然の選択であった。
⑤得度は死の準備ではなく、「生の刷新」である
がんを告知されたとき、人はまず恐れと不安に支配される。昨日まで当たり前にあった「未来」という時間軸が、突如として不確かなものに変わる。身体の主導権は医師に預けられ、自分ではコントロールできない流れに乗せられる。
この不自由さの中で、唯一、人間に残された自由。それは「心のあり方」をどう定めるか、である。得度とは、この「心のあり方」を自ら選び直す、能動的な行為である。それは「生の刷新」であり、「魂の再構築(リブート)」でもある。
俗世を離れるとは、必ずしも財産や地位を物理的に捨てることではない。それらへの「執着」を手放すことである。私が得度したからといって、経営者でなくなったわけでも、家族を捨てたわけでもない。しかし、私の心の中での優先順位は劇的に変わった。
得度によって、私は「がん患者の中村繁夫」という、病に振り回されるだけの存在から解放された。「釈智着」という法号は、私が病に支配されるのではなく、病と共に生きる主体であることを宣言する、精神的な鎧(よろい)でもあった。
世間では、がん患者が得度するというと、「死に備える儀式」と誤解されがちである。しかし、私自身の体験からも、先に挙げた著名人たちの生き様からも分かるように、実際には全く逆である。
得度とは、死に備えるためではなく、死を受け入れながら「生を整える」ことを意味する。恐れの対象であった“死”を、「自然な帰路」として静かに捉え直す思想である。稲盛和夫氏の言う「生を真に輝かせる」とは、まさにこの「刷新」を経た後の、覚悟に満ちた生のあり様を指すのである。