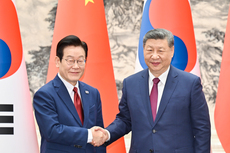⑥病と悟りの交差点 ― 無常観の体得
がんを患うと、時間の流れ、その密度が変わる。それまで気にも留めなかった朝の光、家族の笑顔、看護師の何気ない言葉。その一つひとつが、かけがえのない「生の証」として、鮮烈な色彩をもって心に飛び込んでくる。これこそ、仏教の根幹をなす「無常観」の体得である。
「すべては変化し、すべては移ろい、永遠なるものはない。だからこそ、今この瞬間が尊い」
健康な時には観念的な知識でしかなかったこの「無常」が、がんによって、全身を貫く強烈な「実感」へと変わるのだ。私にとって、それは手術後の集中治療室で迎えた夜明けであった。様々な計器につながれ、身動き一つ取れない暗闇の中で、窓の外が白んでいく。その時、「ああ、今日も生きていた。明日が来ることは、奇跡の連続なのだ」と、心の底から理解した。この強烈な実感こそが、病が私に与えてくれた小さな「悟り」であった。
得度の儀式において、髪を剃り、僧衣をまとい、法号を授かる。これはまさに「第二の誕生」である。人は生まれたときに親から名(俗名)をもらい、この世での生をスタートさせる。そして、死を前にして、あるいは生と死の狭間で、仏から名(法号)をもらう。この二つの名の間に、その人の一生が刻まれる。
がん患者にとって、この「第二の誕生」は極めて重要な意味を持つ。それは、残された人生を「余生」や「おまけの人生」として消極的に生きるのではなく、仏弟子としての「新しい生」として、最期の一瞬まで主体的に生き抜くための、精神的な再起動なのである。
⑦生きながらにして得度する ― がんが教える最後の自由
現代において、得度は必ずしも山奥の寺に籠り、社会と完全に断絶することだけを意味しない。私のように、俗世で仕事を持ち、家庭生活を営みながら、心において仏弟子となる「在家得度」という道が広く開かれている。
「生きながらにして得度する」
それは、日常のただ中に修行を見出すという考え方である。がん患者にとって、闘病生活そのものが修行である。手術の痛み、抗がん剤治療の倦怠感に耐えること。検査結果に一喜一憂し、乱れそうになる心を鎮めること。死の恐怖と向き合い、それでも「今日一日」を大切に生きようとすること。その一日一日の格闘こそが、まさに「執着を手放す」という仏道修行そのものである。
病に屈するのではなく、むしろ病を通して生を見つめ直す。がんという耐え難い苦しみを、魂の浄化と成熟の糧へと転じる。そこに、現代における得度の精神が生きている。瀬戸内寂聴氏が遺した言葉がある。
「死ぬことは怖くない。生ききれなかったら、それが怖いの」
この言葉は、得度した者の死生観を凝縮している。死という事実は、誰にとっても平等に訪れる。それを恐れることにエネルギーを使うのではない。怖いのは、与えられた生を不完全燃焼のまま終えることだ。
がんは肉体を蝕むかもしれない。しかし、魂を深める機会を与えてくれる。得度とは、がんという病が突きつけた「お前はどう生きるのか」という問いに対し、「私はこう生きる」と主体的に答えを出す行為である。それは、病によって奪われた自由を取り戻す、「最後の自由」の行使であり、人生の最終章を自らの手で整える勇気の表れである。
人は死ぬために得度するのではない。最期まで自分らしく「生きる」ために、得度するのだ。
〈結び〉
がんと得度。一見、死に向かう二つの言葉のようでいて、その本質は「生を極めるための旅」である。人は「生病老死」という四苦、特に「病」という強烈な体験を通じて、ようやく自分の心と真剣に向き合い、人生の根本とは何かを問う。
私自身、振り返ってみれば、12年前にがんという師に出会わなければ、得度することはなかっただろう。病は私から健康という絶対の自信を奪ったが、同時に「生病老死」という人間存在の根本と向き合う、静かで濃密な時間を与えてくれた。
得度とは、その恐れを超えた先に見出す「平安」であり、残された人生を生き抜くための「覚悟」である。それは、がんに敗れることではない。がんを師として、がんと共生し、自己の人生を完成させる道である。私の法号「釈智着」は、「智(智慧)を身に着ける」という意味である。がんは私に、順風満帆な時には決して得られなかったであろう、死を見つめることで初めて得られる「生の智慧」を教えてくれた。
その智慧を胸に、私は今日も「がんファイター」として、そして一人の仏弟子として、与えられた生を歩んでいる。