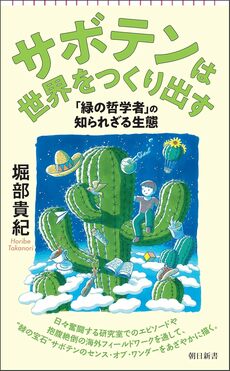痛みの言語化は難しい
しかし、痛みの言語化はやはり難しい。そこで頭木さんが提案するのが「文学の力」を借りることである。例えば詩人のリンダ・マーチンソン(線維筋痛症の慢性疼痛)は自らの痛みを、鋭い歯と爪を首筋に食い込ませている小動物に喩(たと)えている。
―― 一般的な文学的表現といえば、比喩やオノマトペ(擬音語、擬態語)ですよね?
「僕も大腸炎の手術の前に、“お腹にナイフが刺さったような(痛み)”と書きましたが、なかなかピッタリの言葉が見つからない。オノマトペはかなり自由で使い易いけど」
痛みのオノマトペは、ちくちく、きりきり、しくしく、ひりひり、ぴりぴり、ずきずき、ずーん、ずきんずきん、とたくさんあるが、「当てはまらない痛みも数多い」そうだ。
「例えば血管痛について“血管の中をガラスの粉が流れているようだ”という表現がありますが、こうした五感次元の言葉がいいんですね。文学的な模索は、別に気取っているわけではなく、自分の痛みを何とか伝えたいという切羽詰まった思い、実用的な言葉探しの極致なのではないかと感じています」
ところが痛みは精神力で克服すべし、という言論も根強い。信仰上の苦行や通過儀礼で、断食や自分への鞭打ち、滝での修行など自らを痛めつけることで意識の変容を図る体験が社会で認知されているからだ。頭木さんは精神力による乗り越えを「困難克服物語」と呼ぶ。
―― フランスの詩人アランは『幸福論』で、“本当の苦痛を迎える状況でも、上機嫌でいてくれ”と書いてますね。ドイツのカントやロシアのトルストイにも似たような発言があります。
「だから僕は、それはおかしいと反対の立場です。足の折れた人に、“痛みは気の持ちよう”なんて言いますか? なのに、内臓の悪い人には平気で言う。痛みの実態も知らないのに、“克服して(生まれ変われ)”と。健常者に対しては、そんな立派な人になれなどと絶対言わないのに、病人に向かってはなぜ軽く言ってしまえるのか。不可解です」
痛い人の本音は、痛くない人にとっても重要、と頭木さんは本書で記している。なぜなら、今は痛くない人も人生の途上ではいつか心身の痛さを感じることになるし、周囲には必ず「痛い」と言っている人がいるからだ。
「本書への反響で予想以上に多かったのが女性たちからの経験談です」
と、頭木さんは振り返る。
「本にも書きましたが、男性社会において、女性の痛みは軽視されがちです。何度も言うと叱られる。真剣に訴えても“たかが生理痛だろ”など軽視されたりします。心ない態度に心ない言葉が伴っているため、業務や仕事上の人間関係にも影響を与えます」
―― 個人的なものと思われてきた痛みが、軽視によって社会的な影響も出てくる?
「そうです。例えば、無痛分娩。痛くない方がいいに決まっているはずですが、今なお“産みの苦しみ”への過大評価がある。中には女性であっても“母性を得るためには”と困難克服物語を選んでしまう人もいます」
今も現在進行形で苦痛を抱えている頭木さんは、「痛みにより人間として成長する側面はある」と認めながら、でも「痛みは少ない方がいい」「できれば皆無がいい」と言う。
「苦痛を乗り越えて何かを成し遂げる、という道より、僕自身はボーッと生きる道の方がいいと思います。落語に出てくる若旦那のように、脳天気に生きて行く方が人間としてずっと幸せではないでしょうか?」
「なぜ自分がこんな目に」と考え続けた末の願いが、「落語の若旦那」なのだ。
イギリスの小説家ヴァージニア・ウルフは述べている、「人は手持ちの痛みでしか、他人の痛みを推測できない」(『痛みについて』)
日本の小説家村上春樹は記す。「人の心と人の心は調和だけで結びついているのではない。それはむしろ傷と傷とによって深く結びついているのだ」(『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』)。