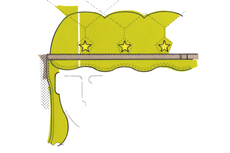獣はどこから現れるのか?
緊張感に包まれる現場
一方、この日のタツマは田中さん含めて7人。午前7時、セコと別れを告げ、タツマとともに険しい山道へと足を踏み入れた。
急峻な斜面が延々と続く。周囲を警戒しながら登り始めておよそ1時間後、タツマも3班に分かれた。岩下幸一さん(66歳)と田中さんを追いながら、48歳の記者は、後を歩いた。足元の土は滑りやすく、油断すれば、今すぐにでも転げ落ちそうな急斜面である。傾斜は目測で45度前後だろうか。もはや「登る」というより「這い上がる」感覚に近い。何度も息が荒くなり、全身から汗が噴き出すのを感じていた。
午前9時。てっぺん付近に到着した。射撃ポイントを特定すると、田中さんはライフルを取り出し、静かに獣の気配を探り始めた。
時折、鳥のさえずりが聞こえるが、周囲は驚くほど静まり返っている。静寂というより「無音」の世界と言っても過言ではない。
否応なく鼓動が高まった。
「獣はいつ現れるか予測できず、山の上下左右、全方向に神経を研ぎ澄ませる必要があります。それでも、この音のない世界では、クマやイノシシが近付けばすぐに分かります。『ガサガサッ』という笹や落葉の中を駆けるかすかな音が、この静寂を破って徐々に迫ってきますから」
セコが「動」ならば、タツマは「静」である。じっとその場で、獣が姿を現すその瞬間を待ち続ける。この日の天候は晴れ。だが、山の中の空気は冷たい。記者は軍手を二重にしていたが、指の腹はふやけたようにしわが寄り、感覚が徐々に遠のき始めていた。
午前11時20分過ぎ。近くから「バーン」という耳をつんざく数発の銃声が響き渡った。山岸さんがクマを仕留めた瞬間だった──。
この日、残念ながら田中さんと記者の前に獣は姿を見せなかった。だが、どこから獣が現れるか分からないという緊張感こそ、狩猟の本質なのかもしれない。
急斜面を下山途中、セコ、タツマに同行した記者たちは何度も足を滑らせ、転倒を繰り返した。狩猟の現場がいかに過酷で、特に高齢者には厳しい環境であるかを、身をもって痛感させられた。
この仕事は決して簡単にできるものではない。険しい山登りはもちろん、孤独や緊張感に耐え、命と向き合う覚悟もいる。経験や勘も必要だ。ハンターの養成は机上で考えるほど容易ではない。そのことを実感した取材となった。
もとの集合場所に戻ったのは午後2時30分過ぎ。全身の筋肉が悲鳴を上げ、立っているのもやっとだった。
そんな中、楢原さんが「どうだったか」と、やさしく声をかけてくれた。その瞳は、朝の厳しさとは打って変わって、穏やかだった。同時に、山に向き合うハンターたちへの深い敬意と感謝の念が込み上げてきた。楢原さんのようなベテランたちの高齢化が進む中、次代を担うハンターの養成は待ったなしの課題だ。