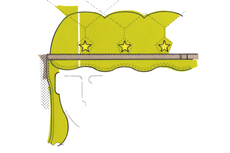どこまでを親が教えて、
どこからを学校が教えるのか
上記は極端な例かもしれないが、未婚のAさんも「結婚して今の働き方は考えられない。生徒が自分の子どものような存在」と話す。仕事を取るか、家庭を取るか。その選択に迫られてしまう真面目な教員もいる。
教員はどこまで生徒の成長に責任を持たなければならないのか。どういった接し方が必要なのか。答えがないから難しい。Aさんはこうも言う。
「社会に出ていくときに『大人の世界は怖くないよ』ということを、きちんと教員が教えたいです。だからこそ、『教員はどんなことをしても(生徒を)見捨てない』という風に生徒に常に思わせておかなければいけない」
「場合によっては親からも守ってあげるのが仕事。どんな親も基本的には子どもを愛していますが、それが子どもに誤解されていない親の方が少ない。自分の高校生時代を振り返ってもそうではないですか? だからこの時期は特に、教員が『大人ともやっていけるよ』っていうことを教える役割でないといけないと思っています」
Aさんの言うことはもっともだし、こんな先生に教わることができる生徒は幸せだと思う。しかし同時に、すべての教員が同じ志を持てるわけではないし、それを求めるのも酷だろう。
小中学校や高等学校だけではなく、保育園や幼稚園でもしばしば議論になるのは、「どこまでを親が教えて、どこからを学校が教えるのか」。その線引きは曖昧だからこそ、教員がどこまで仕事に懸けるべきかが自己判断となってしまう。
本連載では、現役の教師の方や、教師経験のある方へのインタビューを通して、現在の教育現場が抱える問題点を明らかにし、これからのあり方について考えていきたい。教師にとっても、生徒にとっても好ましい教育の場を目指すことは可能なのだろうか。
![]()
![]()
![]()
▲「WEDGE Infinity」の新着記事などをお届けしています。