希少種の保護という“正義”のもとに、島に毒餌をばらまき、大量の捕食者を殺すことは許されるのか?
容易に答えの出ない、重い問いを本書は投げかかる。著者のウィリアム・ソウルゼンバーグは、捕食者の大量殺戮を「大規模な野生動物救出作戦」といい、「聖戦」と褒め称える。はたしてそうであろうか?
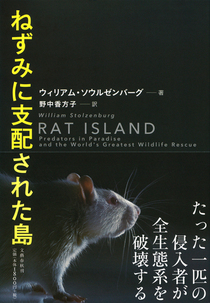 『ねずみに支配された島』(ウィリアム ソウルゼンバーグ 著、野中香方子 翻訳、文藝春秋)
『ねずみに支配された島』(ウィリアム ソウルゼンバーグ 著、野中香方子 翻訳、文藝春秋)
著者の言葉を借りると、地球の陸地の5パーセントに過ぎない島々に絶滅危惧種の半数が棲んでいる。それら保護されるべき貴重な生き物を脅かすのが、ネズミ、ネコ、イタチ、ブタ、ヤギなど、ヒトが持ち込んだ新参者だ。「島に侵入した捕食者たちは、無防備な先住者たちを襲い、その環境を破壊し続けた」。
危機に瀕した野生生物の楽園を元に戻すべく、「ザ・ネイチャー・コンサーバンシー」といった自然保護団体や「自然保護の賢人」たち、「生物保護のプロ、罠猟師、狙撃手、パイロット、動物の権利の擁護者」らが、800件を超す根絶作戦を展開してきた。
ニュージーランドやベーリング海、メキシコ沖、カリフォルニア沖の島々で繰り返された銃や罠や毒による殺戮である。その一部始終を、本書は詳細に伝える。
「整然たる殺戮」による生態系保全
たとえば、アリューシャン列島では海鳥をキツネから守るために、毒薬を混ぜた餌や、シアン化物(青酸カリ)を入れたカプセルにおいしそうな匂いを染み込ませたものをばらまき、足かせ罠を仕掛け、ライフルで撃ち殺した。5万個の毒餌をヘリで島一面に投下した年もあった。
そもそも島にキツネを放ったのはヒトだった。アメリカ合衆国がアリューシャン列島を国立野生生物保護区に指定したとき(1913年)も、海鳥繁殖地の保護と、ホッキョクギツネなど毛皮動物の繁殖という、二つの矛盾する目的があった。しかし、1930年代の大恐慌でアリューシャンの毛皮バブルは終わりを告げ、キツネは置き去りにされた。その結果が、キツネによる島の「支配」だったのである。

















