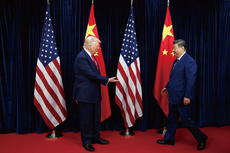日本はビートルズに最も傾倒した国
浜野 そういう60年代の日本で、ビートルズは若者文化シーンをまさに席巻するんだけど、その後自分なりに外国の様子を知るようになると、あれは特に日本に目立った現象だった。
諸外国では、案外まだ「しょせん若者の流行り音楽だろう」ぐらいに思っているところがあったように思うんですね。それと比べたとき、日本の当時の受容度というのは、あれは徹底的。
石坂 そうですね。ビートルズに最も傾倒したのは日本でしょう。その証拠に、調べつくして、書き物にして、まぁ僕もそれを少しやりましたが。文献の量たるや、日本が世界で一番ですよね。
それに次ぐのは、アメリカなんだけど、アメリカといったってニューヨークを中心とする東海岸と言ったほうが正確。『Village Voice』誌、あるいは『Rolling Stone』、『DownBeat』といった雑誌が体現していたような。
日本には、ファン雑誌ではあるけれども『ミュージック・ライフ』、もう少し解説書っぽい『音楽専科』、のちには、中村とうようさんが興した、1969年創刊の『ニューミュージック・マガジン』。それから、時として『スイングジャーナル』。
というように、論評誌のしっかりしたのが揃っている国においては、理屈込みの流行り方になったんです。事実、立派な評論家が日本にはいます。
ビートルズの音楽は、楽しい。楽しけりゃそれでいいんだ、っていう傾向は、日本の場合1967年ぐらいまでです。
わたし自身も、理屈をつけないといけないって思いましたね。
浜野 といいますと。
石坂 ビートルズでいちばん好まれる作品は、概してバラッドになる。メロディがきれいで、ポール・モーリア楽団が演奏してもはまるような。イエスタデイ、レット・イット・ビー、ヘイ・ジュードなどですね。
浜野 いまじゃ中学校の音楽教科書にも載っている。
石坂 そうです。しかし、彼らが本当に問題提起したくて書いた曲は、いわばレコード盤の溝に埋まっているんであってね。シングルカットされてなくて、アルバムに何気なく入っている曲。それを世に知らしめなくては。「これを、聴け」っていうような発信をしてました。
例えば、「Baby, you are a rich man」とかね。「I Am The Walrus」.「I Am The Walrus」が、Ugly is Beautifulというメッセージになって、ヒッピー文化のテーゼにつながったと言われていますね。様々な連想を可能にする、イメージとファンタジアが共にあるような曲ですよ。それらを伝えるには、一定の理屈が必要だな、とね。
(構成・谷口智彦)
石坂 敬一(いしざか・けいいち)
ユニバーサル ミュージック合同会社会長。
慶應義塾大学卒業後に入社した東芝音楽工業株式会社で、ビートルズやピンク・フロイド等、洋楽アーティストの担当ディレクターとなる。英語の原題を大胆な日本語訳にアレンジしたり、音楽批評家と連携してリスナーに音楽の理論的土壌を提供したりと、日本の音楽シーンを改革しヒットに結びつけ、70~80年代にかけて洋楽ブームを巻き起こした。
邦楽アーティストとの親交も知られており、RCサクセションを率いた忌野清志郎をはじめ自社に移籍させたBOØWYや矢沢永吉、松任谷由実など、人脈は幅広い。
2007年からは日本レコード協会会長も務め、若年層等に対する著作権教育と著作権意識の啓発に貢献、2009年には藍綬褒章を受章した。