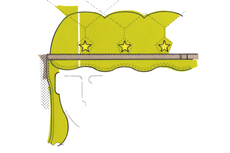雨が長いこと一滴も降らない。数年、あるいは数十年に一度の干ばつに襲われると、アフリカの土地は地割れを起こしたような無数のヒビが入り、いくら土を掘っても、指先に湿り気ひとつ感じることができない。
やせ細った人々は日陰に身を横たえ、飢えをしのぎ、雨が来るのを、あるいはどこからか援助物資が届くのをひたすら待ち続ける。そして、焼けこげるような炎天下、ひとりふたりと弱い者から死んでいく。
そんな干ばつの中、自転車の電灯をつけるダイナモや、ゴミ捨て場から拾ってきたモーターや歯車を利用して風力発電を起こした少年がいた。
2000年代初頭、南部アフリカの旧英領、マラウィで実際にあった話を、その少年がジャーナリストとともに2009年、一冊の本にまとめた。
「風をつかまえた少年 14歳だったぼくはたったひとりで風力発電をつくった」(文春文庫、ウィリアム・カムクワンバ、ブライアン・ミーラー共著)。こう題された本は、日本を含め全世界でベストセラーになった。それを受け、ナイジェリア系英国人の人気俳優、キウェテル・イジョフォーが監督、脚本を手がけ、少年の父親役として出演する映画「風をつかまえた少年」(英、マラウィ製作、113分)を18年に完成させるに至った。
2001年、家が貧しく中学も中途で辞めざるを得なかったマラウィの14歳の少年が飢餓寸前の暮らしにひたすら耐え、ついに畑にポンプで水をもたらす風力発電機を独自に作り上げる。
そんな「奇跡」から18年、実話を基にした映画が日本で公開されるのを前に、「奇跡の少年」ウィリアム・カムクワンバさんが来日した。
「少年が発電に成功した」という噂は国中に、そして世界のメディアに広がり、カムクワンバさんは07年にタンザニアで開かれた、科学者、発明家らの集まりTED会議に招かれる。奨学金の申し出もあり、南アフリカのエリート養成大学アフリカリーダーシップアカデミーの高校に進学。10年には米ダートマス大学に入学し14年に卒業。現在は米国で母国への支援や技術者養成のためのプロジェクトに取り組んでいる。
苦境はアフリカに限った話ではない。要はどこでも、ごく少数ながら、現状から抜け出し、自分を、そして周囲を向上させることがができる人たちがいるということだ。では、その素質はどこから来るのか。
それについて聞くと、カムクワンバさんは英語でとつとつと「好奇心」について語り出した。
「私は幼いころから、物がどうして動くのかに、とても好奇心がありました。大人に『車はどうして動くの』と聞くと、『ガソリンを入れエンジンをかけ、運転すれば動くんだよ』とは答えてくれましたが、私はなぜエンジンが動くのかを知りたかったのです」
いわゆる「ラジオ少年」だった。
「4歳くらいのころ、ラジオの中に小さな人が入っていると思うとたまらなくなって、ラジオを分解しては壊して、両親にしかられていました。それも『とにかく知りたい』という好奇心です」
カムクワンバさんは試行錯誤の末、ラジオの仕組みを独自に理解し、10歳のころには、村でラジオ修理を一手に引き受けるほどになった。
14歳になって風力発電に取り組んだのは好奇心に加え「必要に迫れたのが大きい」。
授業料が払えず中学に通えなかったが、図書館には出入りできるようになり、そこで「エネルギーをつくる」という本を目にする。表紙には風車が描かれていた。
「読み始めると『風車はポンプを動かし水を汲み上げる』とあり、そこに引き込まれました。もし風車をつくれば、汲み上げた水をトウモロコシ畑にまくことができ、年に何度も収穫ができる。それで家が潤えば、自分はまた中学に戻れるかもしれない、とそこまで考えが及び、すぐに始めたのです」
とは言っても、ダイナモもなく、風車をスムーズに回すためのベアリングやビスがあるわけでもない。交流、直流や変圧など、電気のこともまだよく知らなかった。
「それでも諦めず学び続けたのは祖母の影響が大きいです。私が2歳か3歳のころ、祖母は赤土をこねて一人でレンガを作り、家を建てていました。マラウィでは当時、家を作るのは男の仕事と決まっていましたが、祖母はそんなことを気にせず、時間をかけて立派な家を作りました。祖父は朝から晩まで仕立ての仕事で忙しかったのです。彼女は私にこう言いました。『畑の作物に火がついたら、火消し専門の人が来るまで待つのかい? まずは自分で消すだろ』。自分の問題はまず自分で解決しないと、ということです。風車を作る際、周りに笑われ、からかわれましたが、祖母の姿勢が私を支えてくれていました」
映画ではさらっと描かれているが、少年に常に従う飼い犬、カンバへの愛情にカムクワンバさんの人間性があらわれている。
原作でカンバの死はこう描かれている。
干ばつの末、ろくな食べ物も与えられずやせ細り弱ったカンバを森に捨てに行こうという話になる。チャリティという名のいとこが言い出したためだ。
<「どうしてこいつの苦しみを取り除いてやらないんだ?」と彼は言った。「家の裏に連れていって、大きな石で楽にしてやろう」。僕は聞こえないふりをした。翌朝、外に出て、カンバが眠っているのを見ていると、チャリティが庭に姿を現わした。心臓が早鐘を打ちはじめた。チャリティが口を開くよりさきに立ち上がった。「ぼくが連れていく」「ええ?」「ぼくが森に連れていく」。チャリティが肩をすくめて言った。「石の方が手っ取り早い」。「ぼくがそうしたいんだ」>(原作から引用、一部略、以下同じ)
<「さあ、いくぞ!」。カンバはよろけながら立ち上がった。ぼくの心は腹の底まで沈み込んだ。カンバはぼくたちのうしろを苦労して歩いていた。「おいで、カンバ」とぼくは言った。のどに熱いものがこみ上げてきた。それを呑み込んだ。チャリティがぼくのほうを向いて言った。「そんなにくよくよするな。たかが犬だろうが。「うん」とぼくは言った。「たかが犬だ」>
しばらく歩き、二人はカンバを丘の上の木に結ぶと、その場を後にする。
<思いきって振り返ると、ぼくの犬は押し曲げられた長い草の中に横たわっていた。脇腹からあばら骨が突き出ていた。チャリティは何も言わず、森の外へ歩きはじめた。ぼくもそのあとに続こうとすると、カンバが頭をもたげ、くんくんと鳴きはじめた。弱りきった体は声にならない声しか出せなかった。が、それでも慌てた様子で、体の奥深くから哀願するような声をしぼり出していた。カンバにはわかったのだーーぼくがもう二度と戻ってこないことが。数歩歩いて、振り返るという過ちをぼくは犯した。カンバはまだぼくを見つめていた。そのあと顔を伏せた。「恐ろしいことをした」ぼくは自分につぶやき、足を速めた。吐いてしまいそうだった>
翌日、戻ってみるとカンバは死んでいた。
<ひもをやみくもに引っぱった形跡はなかった。もがき苦しんだあとは見られなかった。恐ろしい考えがいきなり頭に浮かんだーーカンバはぼくが行ってしまうのを見て、生きることをあきらめたのだ。このぼくがカンバを殺したのだ>
そこがアフリカだろうが、アジアだろうが関係ない。こうした感受性を備え、そしてそのときの気持ちがいつまでも記憶の奥に貼りついている人がある一定数いる。カムクワンバさんは単なる発明家ではなく、そんな繊細な感受性を備えた人なのだろう。犬の話を持ち出すと彼は少しつらそうな顔になりこう言った。
「本当に自分にとってとてもつらいときでした。そのときは、『犬が生きるのをあきらめたから死んだんだ』とは思わなかったのです。ひどい病気だったし、弱っていたからだと。でも、後になって間違いだったと気づきました。捨てられたという思いがカンバの死を早めたのだと思います。本当のカンバの内面はわかりませんが」