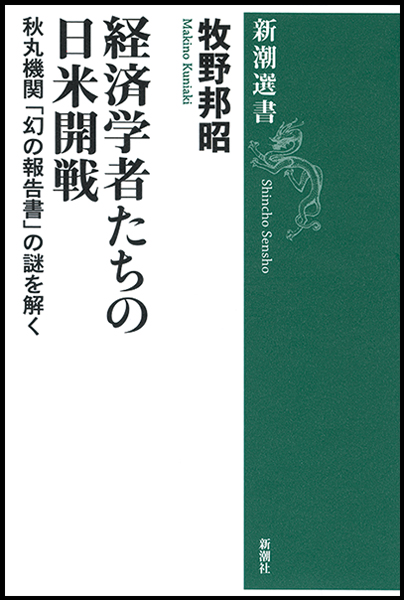
秋丸機関「幻の報告書」の謎を解く
牧野邦昭 新潮選書 1430円(税込)
昨年、とくに暮れは日米開戦から80年となるため、それに関する多くの情報が現れたが、残念ながら新しいよい研究成果はほとんどなかった。これまでの研究でわかっていることと新しく明らかにされたことが何かとを明示するという基本スタイルをわきまえていないものが多くなっている結果のような気がする。
(百武三郎侍従長の日記が一部のメディアに公開されたが、そこで強調されていた、1941年秋に天皇が日米開戦に傾いたことなどは近衛文麿の記述(「今日、開戦の不利なることを申し上げると、それに賛成されていたのに、明日午前に出ると<中略>少し戦争の方に寄って行かれる。又次回にはもっと戦争論の方に寄っておられる。<中略>唯一の頼みの綱の陛下がこれではとても頑張りようがない。」(冨田健治『敗戦日本の内側』<古今書院、1962年、196頁>)などからすでに早くから知られたことであり、既成の研究成果との違いが判然としていない報道は疑問であった。この日記の意義は全文が公開されないとはっきりしないと思う。)
その中で、例外的に、これまでの確実な研究の蓄積の上に発表された優れたものが二つあった。一つが本書をもとにした牧野邦昭「日本はなぜ米国と開戦に突き進んだか」『週刊新潮』(2021年12月16日号)であり、もう一つが森山優「避決定の不貫徹が招いた『亡国』」(『Voice』1月号)である。この二つを見ていくことにしたい。
正確な実証に基づき日米開戦の謎を解いた書
牧野氏の本書は正確な実証に基づき、斬新な方法に拠って日米開戦の謎を解いた近来にない著作である。(なお、その内容はNHKの12月25日7時25分から「開戦80年 生かされなかった情報」でも報道されており、『デイリー新潮』で読むこともできる(日本が“無謀にも”米軍と開戦した理由に迫る 日本陸軍・謀略機関の「極秘報告書」を発掘 | デイリー新潮 (dailyshincho.jp)))。
それでは日米開戦問題を本書はどう解いているのだろうか。
日本の真珠湾攻撃で始まった戦争であるから、問題はどうして日本は攻撃を仕掛けたのかということに尽きるが、とりわけ日本と米国の国力差が圧倒的なことは明白なのにどうして日本は戦争を始めたのかということになる。
その場合、この圧倒的な国力・経済力の差を日本の指導者たちは知らなかったという見方がある。しかし、開戦の決定をしたリーダーたちは本当にこれくらいの判断すらできない「暗愚で非合理的な」リーダーたちだったのか。この視点に立ち、開戦の適否判断の根拠となる国力=物量・経済の立場から真実を明らかにしたのが本書である。
著者は開戦決定の際の判断のもとになるデータを扱う陸軍の経済力調査機関を調査した。その結果、陸軍は有沢広巳という第二次人民戦線事件で検挙され保釈中のマルクス主義経済学の元東京大学教授をリクルートして調査機関(秋丸機関)の中枢に据えていたことがわかった。
有沢は、戦後「自分の作った調査報告では、日本は米国に負けるという結論だったので陸軍に都合が悪く採用されず焼却された」という趣旨のことを言っていたのだが、著者はその発言を突き崩している。
1941年の夏に米国と日本の国力差を20対1とすることを基本にした報告書が出されているが、それは焼却されてはおらず大部分は残っており、著者により初めて発見されたのだ。驚くのはその内容の大部分は当時の雑誌などにも掲載されており、秘密でも何でもなかったということである。それらは誰にでも見ることができたのである。
総力戦研究所というところから出たこうしたレポートを唯一無二のように書いた人がいるが間違いだったわけであり、これや有沢レポートの破棄を追認する内容のものがあればそれらは疑問なのである。
日本が開戦を選んだのはなぜか
ということは、当時の日本の指導者は誰でも国力差を知っていたのであるから、問題はその認識を共有していながら、なぜ開戦に傾いたのかということになる。「開戦すれば高い確率で日本は敗北する」からこそ「低い確率に賭けてリスクを取っても開戦しなければならい」という思考になって行ったのだと著者はいう。「必ず3000円払わなければならない」か「4000円払わねばならない可能性が8割あるが、1円も払わなくてもすむ可能性が2割ある」という選択肢の時、多くの人間は堅実な前者よりも損失回避性志向から後者を選択するという。
これは、行動経済学のプロスペクト理論というものによるのだが、「合理的」に考える多くの人間が行うことであり、日本の指導者たちもそうしたのにすぎないと、著者は言う(プロスペクト理論の適用については慎重を期さなければいけないこともあるようだ(猪木武徳『経済社会の学び方』<中公新書、80~83頁参照>))。
詳しくは本書をぜひ読んでもらいたい。企画院事件、独ソ戦、南進論・北進論の対立、近衛ルーズベルト会談構想、ゾルゲ事件など日米開戦に至る昭和史上の重要事件がこの問題の考察に絡んで考察されていて飽かせず読ませてくれる。本書のような正確で清新な成果を多くの研究者に期待したいものである。

















