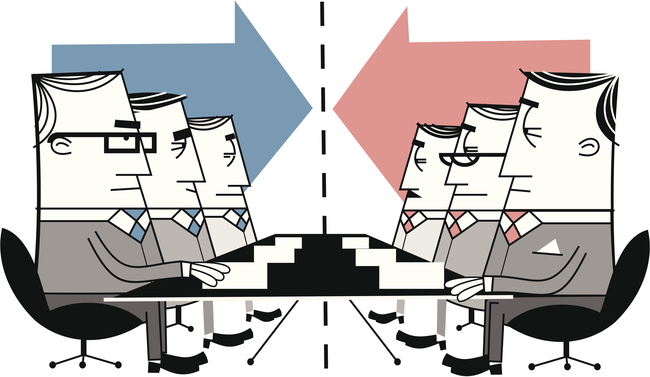現在、投資界隈を賑わせているのが“物言う株主”、別名アクティビストと呼ばれる投資家の存在だ。アクティビストが投資した株価は上がることが多く、アクティビストの提案に他の投資家が賛同しやすくなったのではないかともいわれている。一方、企業側は、株主との向き合い方についてどう考えていけばよいのか。2021年7月16日に掲載した『アクティビストとの積極的な対話が求められる日本企業』を再掲する。
今年の3月期決算企業の株主総会はこれまでと様相が違った。「物言う株主」と呼ばれ、別名ではアクティビストと呼ばれる投資家が、上場会社側に対して経営方針や人事について独自の議案を突き付けるなど、これまでにない権利行使が目立った。不祥事に揺れた東芝の6月の株主総会では、取締役会議長を含め2人の取締役の再任が否決されるなど、「物言う株主」の存在感が大きくなった。
「日本はブルーオーシャン」
アクティビストの活動に詳しいコンサルティング会社アイ・アールジャパンの古田温子取締役は「アクティビストの多くは欧米企業ではやりつくした感じだが、日本企業はブルーオーシャン(未開拓)なので、これから、攻勢を強める余地が十分にある。彼らの提案は以前に比べて真っ当なものが増えてきており、会社側もアクティビストに対抗するロジック(論理)で対応せざるを得なくなっている」と指摘、こうしたやり方に慣れていない日本企業は、アクティビストによる予想していない追及にあって厳しい対応を迫られそうだ。
具体例を見てみよう。6月25日に定時株主総会を開いた東芝は、11人の取締役選任案の採決を行った結果、永山治取締役会議長(中外製薬名誉会長)ら2人の再任案が反対多数で否決される事態になった。永山議長は56%の反対、もう一人の取締役は74%もの反対票を集めた。綱川智社長兼最高経営責任者(CEO)は再任されたが、議長を含めた取締役の2人がこれだけの反対票を集めたことは、東芝経営陣に大打撃となり、アクティビストを含めた多くの投資家が東芝に対して経営の出直しを突き付けた形となった。中でも74%という反対票は大半の株主が反対票を投じたことになり、これまで安定株主と思われていた機関投資家の多くも反対票を投じた可能性が大きいとみられる。
「サード・ポイント」対ソニー
これといった不祥事がなくても、アクティビストは狙いを定めて経営陣に対して独自の要求を主張してくる。米国の代表的なアクティビスト「サード・ポイント」が2013年ごろからソニーに仕掛けてきたケースをみてみよう。「サード・ポイント」はダニエル・ローブ氏が1995年に設立したヘッジファンドで、日本ではソニーのほか、セブン&アイ・ホールディングスやIHIなどにも投資してきた。米国ではインテル株を取得して経営方針の転換を求めたほか、この数年はアマゾン・ドット・コムなどハイテク株にも投資先を拡大しているようだ。
「サード・ポイント」は2013年以降にソニー株を買増して一時は筆頭株主になり、経営陣に対してエンターテインメントや半導体部門の分離独立を強く要求し続けてきた。これに対して平井一夫CEOは一貫して「サード・ポイント」の要求を拒否、自社の路線を貫いた。結果的には、エンターテインメントと半導体の両部門が業績に大きく寄与して株価もアップした。
市場筋では「サード・ポイント」は株価上昇に満足してソニー株をすべて売却して、かなりの値上がり益を得たのではないかとみている。ソニーの事例にみられるように、アクティビストは狙いを定めて買った(投資した)以上は、株価が上がって投資利益が出るまでは、株を手離さないことが多い。
アクティビストが投資した企業の株価は上がることが多い。アクティビストが株を買ったという情報が流れると、イベント・ドリブンを狙う機関投資家は何かが起きるという思惑から追随して買うこともあり、個人を含む一般投資家も連想買いすることもあるという。最近では一般投資家もアクティビストの情報をできるだけ早く入手しようとし、株価の面でもその存在は無視できなくなりつつある。