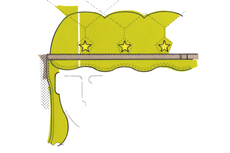われわれは、「電気があるのが当たり前」の社会を生きている。そのためか、日常の中で、電気のスイッチを押したその先にどんな世界があるのかを意識することは少ない。
だが、明治から昭和の歴史をひも解くと、電気を自分たちのものとすべく、現代では想像もつかないほどの激しい暴力事件や刃傷沙汰があった。それはまさに、電気を〝私物化〟しようとする電灯(電気)会社や政府などの国家権力に対する民衆の知られざる戦いでもあった。
例えば1913(大正2)年には「赤穂騒擾事件」というすさまじい事件が起こっている。
長野県赤穂村(現・駒ケ根市)では当時、村営の公営電気事業を目指し、自分たちの手で村の電気を供給しようとしていた。全国でも市町村営、都営の電気事業が増えていた時代であり、赤穂事件発生当時の公営電気事業数は19あり、35(昭和10)年には、123にも上った。
赤穂村にはそれができる経済力もあった。だが、政府は認可をしなかった。しかも、調査や文書照合さえもされなかった。一方で、政友会の大物議員が経営し、赤穂村に供給区域を広げようとしていた長野電灯会社はあっさりと認可を受けた。
長野電灯会社への反感と憎悪が募った村民たちは暴徒化し、やがて1000人を超える群衆が長野電灯会社と契約した村民に対する焼き討ち事件へと発展していくことになる。
また、昭和初期には、電灯料金の値下げを要求する「電灯争議」が全国各地で繰り広げられた。
富山県中新川郡西水橋町(現・富山市水橋町)では、富山電気の度重なる電灯値上げに怒った人々が電灯料金不払いという行動に出る。富山電気側はこれに断線消灯で対抗。すると町民らは電柱の下に座り込み、張り番をするという事態に発展した。
やがて村民たちは、家の電球を外し、棺の中に1400個あまりの電球を納め、富山電気に向けて〝電球の葬列〟を行い、「あなたたちの電気は使わない」という事実上の宣戦布告をするのであった─。
こうした歴史に埋もれた電気の事件史をさまざまな資料から丹念に追いかけたのが、田中聡著『電気は誰のものか』(晶文社)、その続編となる『電源防衛戦争』(亜紀書房)である。著者の田中氏に、国民一人ひとりが電気を自分事として捉えるために必要なこととは何かを聞いた。
編集部(以下、──)本書執筆のきっかけは何だったのですか?
田中 もともと電気の歴史には関心があったのですが、東京電力福島第一原発事故が起き、本格的にやろうと決意しました。調査を進めていくと、赤穂騒擾事件や電灯争議など、需要者と供給者の激しい対立などがあったことが分かり、自分の中で「電気はいったい誰のものか」という疑問がふつふつと湧き上がってきたんです。結果的に歴史に埋もれた事実を調べることで、この本のテーマ、骨格が固まっていきました。

1962年富山県生まれ。富山大学人文学部卒業。同大学文学専攻科修了。膨大な資料をもとに、歴史に埋もれた事柄をあぶり出すノンフィクションを数多く著している。著書に『身の維新』(亜紀書房)、『妖怪と怨霊が動かした日本の歴史』(笠間書院) などがある。
──電灯(電気)会社と政府との癒着ともとれる動きや、主導権争いは現代社会にも通じます。
田中 当時、電気が広く普及し、人々の暮らしになくてはならないものとなったことで、電気の公共性を誰もが認めるようになりました。民間企業からすれば、人々が電気の価値が分からなかった時代からさまざまな苦労を経て、電気のある社会をつくってきたという自負があったのでしょう。だから、赤穂村のような公営電気事業に抵抗するのは分からなくもない。
ただし、それによって、自分たちの言うことが正しい、自分たちが電気を供給して(やって)いる、料金値上げは素人が口出しするものではない、といった過度な自信や慢心が見られるようになりました。それらが需要者側の反感を買う結果にもなった。その意味で、前提条件は違っていても、現代社会でもこうした構図は残っているといえるでしょう。