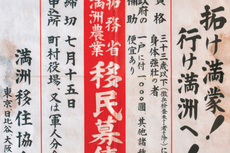「西の大阪」と称される大阪府では老朽化の進行が早く、腐食のおそれの大きい管渠は119キロ・メートルと全国で最も長い。
流域下水道と公共下水道を含めた日本の下水道の総延長は49万キロ・メートルに達する。そのうち、耐用年数50年を超えた管は約3万キロ・メートルに及び、10年後には9万キロ・メートル、20年後には20万キロ・メートルと、総延長の約4割に達する見込みである。老朽化による陥没事故は2022年度に約2600件発生しており、15年の約3300件と比較すると減少している。この背景には、15年の下水道法改正による「維持修繕基準」の導入がある。
この基準では、下水道管を以下の3段階に分類している。
I(重度):速やかに措置が必要
Ⅱ(中度):5年以内に対策を検討
Ⅲ(軽度):5年以上の延長が可能
八潮市の下水道管は、耐用年数50年には達しておらず、Ⅱ(中度)に分類されていた。点検が行われていたにもかかわらず事故が発生したことは、下水道インフラの管理の難しさを如実に示している。
先進国に共通する
上下水道の課題
上下水道施設の老朽化は、先進国共通の課題である。米国の水道事業は、老朽化・漏水事故の多発・資金不足といった深刻な問題を抱えている。 日本と比較して漏水事故の発生件数は圧倒的に多く、年間24万件に達し、日本の約12倍である。今年2月には、デトロイトで直径約140センチ・メートルの水道管が破損し、約400世帯に影響を及ぼした。漏れ出した水が地下室を浸水させ、水没した自動車が凍結する事態となった。米国では水道管の予防的修繕に消極的であり、「壊れたら直す」という対応を繰り返しているが、放置による被害はあまりにも大きい。
英国では、上下水道事業の財政難を民営化によって改善しようとした。しかし、近年ではインフラの老朽化が進み、更新の遅れが顕著になっている。その結果、水漏れや下水の未処理排出などの問題が深刻化している。特に、大手のテムズ・ウォーター社は多額の負債を抱え、未処理の下水を河川に流出させるなどの問題を引き起こしている。
民間企業は利益を優先し、インフラ投資を後回しにしてきたため、水道管の老朽化が進行した。その結果、水漏れが多発し、貴重な水資源が失われている。このような状況から、水道事業に対する国民の不信感は根強く、規制の見直しや運営体制の改革が進められる可能性が高い。
ドイツでは、「シュタットベルケ」と呼ばれる地域インフラ管理者が重要な役割を果たしている。これは、自治体がほぼ100%出資する民間企業で、地域の基礎インフラを総合的に管理する組織である。シュタットベルケは、エネルギー事業などの黒字を活用し、赤字になりやすい上下水道や公共交通を支えることで、市民生活を安定させる仕組みを構築している。シュタットベルケの経営においては、以下の3つの要素のバランスを取ることが求められる。
・利益の確保:事業の継続には安定した収益が不可欠である。
・技術品質の維持:サービスの安定供給を実現するためには、高い技術力が必要である。
・市民負担の適正化:利用者が支払える範囲の料金設定が求められる。