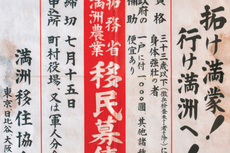トライアルが、老舗スーパーの西友を買収するというニュースは、様々な観点から日本の流通史の中に位置づけることができそうだ。まず、徹底したコスト削減など、新しい経営ノウハウで事業を拡大中のトライアルが、遂に首都圏市場に参入するという意味合いがある。また、トライアルの有名なレジカートなど新しいテクノロジーの応用がさらに拡大するという観点から見ることもできるだろう。それとは別に、セゾングループの中核企業だった西友の経営が新たな段階を迎える中で、セゾンの歴史が遠くなるという見方も可能だ。
けれども、アメリカの視点から見ていると異なった評価も可能になってくる。まず強く印象づけられるのは、ウォルマートの西友買収が最終的に失敗し、今回の株式譲渡が完了することで、完全撤退になるということだ。これはアメリカの流通産業にとって大きな事件と言える。
ウォルマートが日本で成功しなかった理由
ウォルマートはアメリカの企業であり、全世界に約1万店を有する巨大流通企業である。一方の西友は1998年のセゾングループ解体後は、住友商事との提携で経営の改善を進めていたが、2002年にウォルマートの資本を受け入れ、徐々にその傘下に入っていった。ウォルマートは自信満々であり、世界共通の「ウォルマート方式」を強引に導入することで、経営を一気に改革しようとしたが、結果的には失敗となった。
原因としては、同じ外資でもアマゾンのように流通を全て支配することができなかったこと、生鮮食品に関するノウハウが欠落していたことが主因とされている。だが、それ以前の問題として、ウォルマート方式、つまり各商品カテゴリに関して品揃えを簡素化して、著名な全国ブランド数社と独自PB(プライベートブランド)に絞るやり方が日本の目の肥えた消費者に総スカンを喰らったことが大きいとされている。
例えば、かつお節であるとか、ほうじ茶などについて、消費者は高級品から普及品、また産地のローカル色のあるもの、大手による全国ブランドなど最低でも7から8種あるいはそれ以上の品揃えがないと、そもそも売り場を貧弱と思って寄りつかない。そのくせ、どの商品も価格競争が激しく利幅は少ない。
消費者の全体としては前世紀のような分厚い購買力があるわけではなく、家計を引き締めているので価格選好が厳しい。けれどもその一方で、品質へのこだわりは高いし、数多くの選択肢を要求する。
ウォルマートは、本気になって「圧倒的な商品力のあるPBを付加価値のあるストーリー性を付けて徹底訴求」すれば勝者になれたかもしれない。けれども、反対に「薄利多品種の市場」「購買力は低いのに識別眼が高くコスパ追求に並々ならぬ意欲を持っている謎の消費者」という環境に音を上げて敗北していったというのが真相だろう。