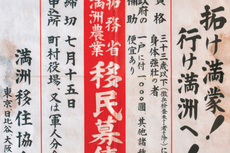アメリカだけでなく、バブル期の日本企業などもそうであったが、独善に陥って各国の市場特性を舐めてかかり、一方的な思い込みで世界標準を押し付けるという経営をしてしまったのだった。
そのウォルマートは、本国アメリカでも決して輝いてはいない。ウォルマートが絶頂だったのは08年のリーマンショックに始まる大不況後であった。
経済の先行き不安が拡大する中で、少しでも安い商品を求めて高収入層まで幅広い顧客層を獲得し、スケールメリットを活かして利益率の向上にも成功していた。けれども、その後はコロナ禍における宅配対応をコロナ禍後に定着させるのには失敗し、会員制「まとめ買い」業態ではコストコに敗北、その一方で欧州勢によるディスカウントスーパーの躍進で市場を侵食されつつある。
そんな中で、全く文化も環境も異なる日本において20年を超える試行錯誤をこれ以上続けることは不可能という判断に至ったのだろう。
多いウォルマートとトライアルの共通点
実は、今回、ウォルマートに代わって西友の経営を担うこととなったトライアルは、経営姿勢においてそのウォルマートと共通点が多い。もちろん、世界最大の規模を誇るウォルマートと、トライアルでは規模が全く違う。例えば、年商ベースで比較すると、ウォルマートが5000億ドル(75兆円)に対してトライアルが5300億円、つまり150分の1という途方もない差がある。けれども、そのウォルマートは西友の経営に失敗しているわけで、共通点の多いトライアルとの比較にはある程度の意味はあると考える。
まず両者の共通点といえば、立地戦略が挙げられる。基本的に両者共にモータリゼーションを前提に、道路の便の良いところに出店するのだが、その立地は必ずしも一等地ではない。交通量の多いバイパス沿いだとか、既存のメガモールにテナントで入るということは少ない。
むしろ商業地区としては未開発の大規模物件を安く入手して出店、商圏の開発は自社ブランドの吸引力を使って立ち上げるという点も似ている。ブランドの持つ、安さ、便利さというイメージを活かしつつ、出店コストを抑える経営戦略は見事にソックリだ。
テクノロジーの導入やコスト削減については、トライアルの方が先進性を感じるが、その戦略については、これも両者は似ている。例えば、トライアルが導入している買い物カートにタブレット端末とスキャナーを搭載するスキップカート(通称:レジカート)、そしてポイントと決済が一体となったプリペイドカードのシステムについて目的は明らかだ。省人化によるコスト削減というよりも、プリペイドつまり前金制は、圧倒的に優位なキャッシュフローを実現する。またクレジットカードの高率な手数料とも無縁だ。
ウォルマートの場合は、例えばアメリカではクレカによるキャッシュレスが普及しているので、さすがに前金のプリペイドカードほどのキャッシュフローは実現できていない。またクレカの手数料をゼロにする対策もしていない。けれども、超大手チェーンであるにも関わらず、アップルやGoogleのタッチレス決済は拒否しており、スマホの独自アプリによる決済を模索している。つまり、決済時のファイナンスを何とか独自化してキャッシュフローや手数料で、少しでも優位に立とうという姿勢は両者が非常に似ている部分だといえる。