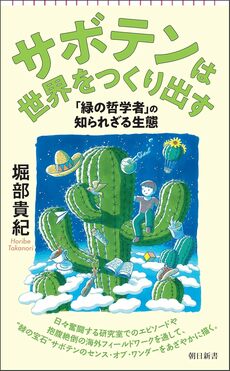こうした状況に嫌気がさしたタイムールは以後繰り返し退位の意向を表明するようになり、オマーンを離れインドに滞在するようになる(当時は両国とも英国の支配下にあった)。英国政府やタイムールの長子であり事実上の後継者であったサイードは、タイムールに翻意するよう説得を試みたものの、タイムールの意思は固く、1932年2月にタイムールからサイードへの生前譲位が実現する。退位後、タイムールは亡くなる1965年までのほとんどの期間をインドで過ごしており(1936年に日本人女性と結婚したことから、神戸で生活を送っていた時期もある)、政務・公務からは完全に遠ざかっていた。
 iStock
iStock
オマーンの事例は、本稿冒頭で宮内庁が天皇制を不安定化させる懸念の一つとして挙げた君主による恣意的な退位に当てはまろう。退位後に30年も存命だったことから分かるように、タイムールは君主として職務の遂行ができなくなるような健康状態だったわけではない。言わば本人の希望以外に退位を正当化するさしたる根拠がないわけだが、こうした生前退位が時の君主の意向によって相次ぐようであれば、君主制そのものが不安定化する恐れがあるという指摘は的を射ている。
他方、生前退位を制度上可能にすることで、実際に君主が次々に辞めていくという事態が発生する可能性は小さいのではないかとも考えられる。当時のオマーンは生前退位どころか王位継承に関する法制度そのものが存在しなかったわけだが、それでもタイムールの事例が例外的なケースとして残るのみである。サイードは王位継承時に若干21歳であったが、1929年から閣議を主宰するなど、王位継承前から政務の多くを担っていた。タイムールの生前退位が国内外において認められたのは、こうした後継者の存在が確認できたからであり、そうであれば意欲のない国王の統治を継続するより、新たな国王の下で政治を行う方が良いという判断があったと考えられよう。
生前退位を巡るいずれの問題も、対応を誤れば制度そのものを瓦解させかねない危険性があることから、決して過小評価できるものではない。しかし、その脅威を現実的にどこまで懸念すべきかについては、その国の君主の役割や権能、そしてその社会の置かれている状態によって変化するものであろう。日本の天皇制のあるべき姿について論じる際にも、こうした諸外国の事例を参考に思考実験を重ねていくことが望まれよう。
![]()
![]()
![]()
▲「WEDGE Infinity」の新着記事などをお届けしています。