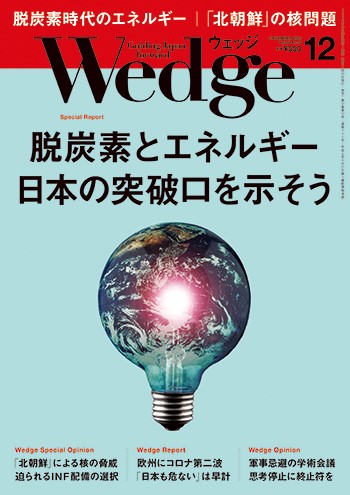同志社大学法学部政治学科卒業。新聞記者、フリーライターを経て2004年『ハゲタカ』(講談社文庫)でデビュー。主な著書に『ベイジン』(幻冬舎文庫)、『神域』(毎日新聞出版)などがあり、ドラマ化も多数。
「電気は無尽蔵にある」と錯覚している日本人も多いだろう。だが、第二次世界大戦やオイルショックの歴史から分かるように、島国の日本では、何かの拍子でエネルギー供給が途絶えるリスクを常に抱えている。2006年に小説『マグマ』(角川文庫)を執筆したのは、その「もしも」をフィクションの世界で表現し、読者に「エネルギーとは日本の命脈そのものだ」と実感してもらいたかったからだ。
窓が開かない高層マンションでは、換気すら、電力を用いた空調設備に頼らざるを得ない。そんな社会を作っておきながら、未だに水力以外の、海外資源に頼らない発電オプションを十分に持っていない国が日本だ。太陽光・風力発電も進めるべきだが、国が真剣に電力の安定供給・エネルギー資源の確保を「国家プロジェクト」として考えるならば、自らの足元に眠っている「地熱」という資源に自然と目が向くはずだ。
小説『マグマ』では原子力が政治的な理由で停止を余儀なくされ、その代替手段として国を挙げて地熱発電を開発する道を選んだが、11年に起きた東日本大震災での福島第1原発事故によって、まさに「もしも」の世界が現実のものとなった。
10年経っても未だに政府の危機感は足りていないように思う。先日、小泉進次郎環境相から国立公園内での開発規制緩和の方針が打ち出されたが、ただ規制を緩めても、地元住民への説明を開発業者任せにし、国が矢面に立たない姿勢を変えなければ、開発はなかなか進まないだろう。
「エネルギー政策は票にならない」と言う政治家もいる。だが、本当に国の将来を憂うのならば、その重要性を国民に伝え、説得し、民意を啓蒙することこそが政治の本来の役割であるはずだ。
聞き手・構成 川崎隆司(Wedge編集部)
■脱炭素とエネルギー 日本の突破口を示そう
PART 1 パリ協定を理解し脱炭素社会へのイノベーションを起こそう
DATA データから読み解く資源小国・日本のエネルギー事情
PART 2 電力自由化という美名の陰で高まる“安定供給リスク”
PART 3 温暖化やコロナで広がる懐疑論 深まる溝を埋めるには
PART 4 数値目標至上主義をやめ独・英の試行錯誤を謙虚に学べ
COLUMN 進まぬ日本の地熱発電 〝根詰まり〟解消への道筋は
INTERVIEW 小説『マグマ』の著者が語る 「地熱」に食らいつく危機感をもて
INTERVIEW 地熱発電分野のブレークスルー 日本でEGS技術の確立を
PART 5 電力だけでは実現しない 脱炭素社会に必要な三つの視点
PART 6 「脱炭素」へのたしかな道 再エネと原子力は〝共存共栄〟できる
![]()
![]()

▲「WEDGE Infinity」の新着記事などをお届けしています。