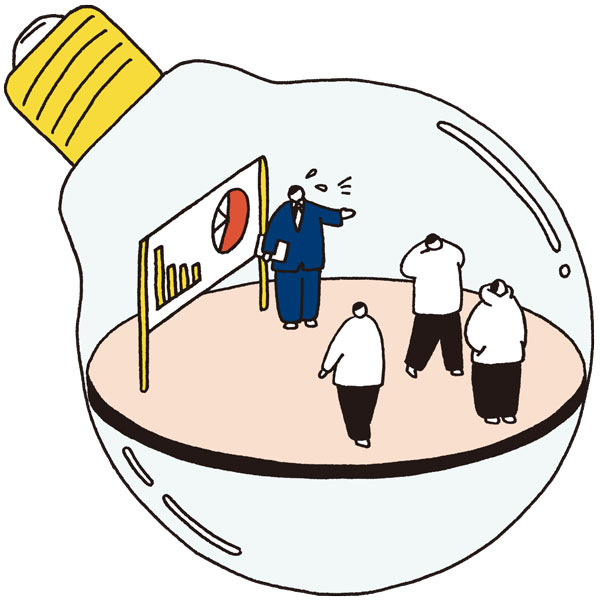日本の地球温暖化対策が、大きく動き出そうとしている。菅義偉首相が10月26日、温室効果ガス排出の実質ゼロを2050年までに目指すことを所信表明演説で発表した。「実質ゼロ」の目標時期について、政府はこれまで「今世紀後半のできるだけ早期」と明言を避けてきた。それは、問題の難しさの反映だった。
日本の電気の7割以上は化石燃料を燃やす火力発電で作られている。ガスや石油を直接使う場合も含め、冷暖房、スマホなどのIT機器、車などの移動手段─日々の暮らしは、化石燃料が支えている。化石燃料への依存を極端に減らす脱炭素社会の実現には、経済構造の根本的な変革が求められる。
こうした暮らしに密着した問題では、「科学」だけで是非が判断されない難しさがある。「地球温暖化は人類が排出する二酸化炭素(CO2)が引き起こしているのか」といった問題は科学的に判断されるべきだが、なかなか単純にはいかない。
筆者は15年から3年余り、ワシントン特派員として地球温暖化を疑う米国の人々を取材し、そんな現実を実感した。共和党と民主党の二大政党が拮抗する米国では、地球温暖化に対する姿勢が、政治的な立場によって異なる。18年の米ギャラップ社の世論調査によると、「人類の活動が地球温暖化の原因だ」と答えた人の割合は、民主党支持者は89%だったが、共和党支持者は35%にとどまった。科学的な質問だが、答えは政治の色に染まる。
さらに問題を深刻にするのは、学歴が高いほど、あるいは、科学の知識が豊富であるほど、こうした党派間のギャップが広がることだ。ここでは、エール大学のダン・カハン教授の研究を紹介したい。「人間活動が地球温暖化の原因かどうか」についての回答と科学的知識の有無などとの関係を分析した結果、知識が少ないグループでは支持政党による違いは目立たなかったが、知識が増えるほど支持政党の違いに応じた考え方のギャップが際立った。
「人は自分の主義や考え方に一致する知識を吸収する傾向があるので、知識が増えると考え方が極端になる」。カハン教授はそう指摘する。「見たいものだけ見える」あるいは「見たくないものは見えない」ということだ。難しい言葉でいうと「確証バイアス(confirmation bias)」と呼ばれる。