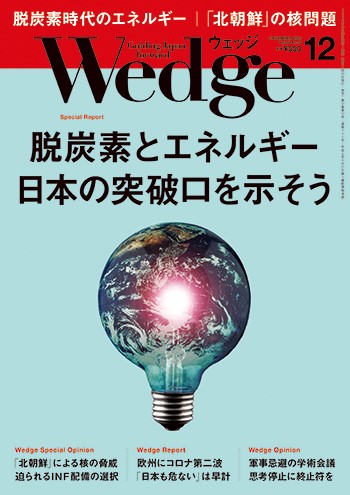元経済産業審議官
東京大学法学部卒業。1982年通商産業省(現経済産業省)入省。米ミシガン大学で応用経済学修士号を取得。産業技術環境政策局長、通商政策局長などを経て、経済産業審議官。2017年退官後、米国I-Pulse副会長に就任。
2050年にCO2排出量のネットゼロを目指すためには、長期戦略の下で、原子力発電と再生可能エネルギーの導入を進めることが必要だ。再エネは、現時点では、他電源と比べ、コストが高く、現状のままで急速に導入すれば、国民負担が増える。技術革新が必要だ。太陽光や風力発電は、日本の地形や気候の特性上、主力電源になる規模まで導入できるか不確実である一方で、技術革新が世界的に進んでおり、蓄電池を含めたコストが下がった時点で一気に導入することが合理的だ。技術戦略はエネルギー政策へのインパクトが大きく、かつ、日本が強みを発揮できる分野に重点化するべきであり、地熱発電は非常に重要な分野だ。
現在の地熱発電は、地下に豊富な熱資源があっても、発電に使う蒸気をもたらす十分な熱水が存在することが必要であり、これが、地理的・コスト的に地熱開発の大きな制約となっている。この制約を解決するのが、米・欧州・豪などで実用化が進められている「地熱増産システム(EGS)」と呼ばれる技術だ。EGSでは、地下の高温の岩体を掘削し、長細い管や細かい亀裂を人工的に造る。そこに地上から水などを注入し、蒸気を得る。十分な熱水が存在しなくても、熱資源があればどこでも発電できる。米エネルギー省は、米国には7km以浅に5157GW(㌐ワット)(百万kWの原子力発電所5157基分。米国の総発電能力の5倍)のEGS発電資源があるとし、戦略的な技術開発を進める。日本では、EGSにより、3km以浅かつ確度の高い地点に限っても、現在の地熱発電の70倍の38GWの発電が可能との試算もあり、地熱を主力電源とできる可能性がある。
日本でEGS技術を確立できれば、エネルギー政策の突破口となり、日本のソフトパワーも高まるだろう。
聞き手・構成 川崎隆司(Wedge編集部)
■脱炭素とエネルギー 日本の突破口を示そう
PART 1 パリ協定を理解し脱炭素社会へのイノベーションを起こそう
DATA データから読み解く資源小国・日本のエネルギー事情
PART 2 電力自由化という美名の陰で高まる“安定供給リスク”
PART 3 温暖化やコロナで広がる懐疑論 深まる溝を埋めるには
PART 4 数値目標至上主義をやめ独・英の試行錯誤を謙虚に学べ
COLUMN 進まぬ日本の地熱発電 〝根詰まり〟解消への道筋は
INTERVIEW 小説『マグマ』の著者が語る 「地熱」に食らいつく危機感をもて
INTERVIEW 地熱発電分野のブレークスルー 日本でEGS技術の確立を
PART 5 電力だけでは実現しない 脱炭素社会に必要な三つの視点
PART 6 「脱炭素」へのたしかな道 再エネと原子力は〝共存共栄〟できる
![]()
![]()

▲「WEDGE Infinity」の新着記事などをお届けしています。