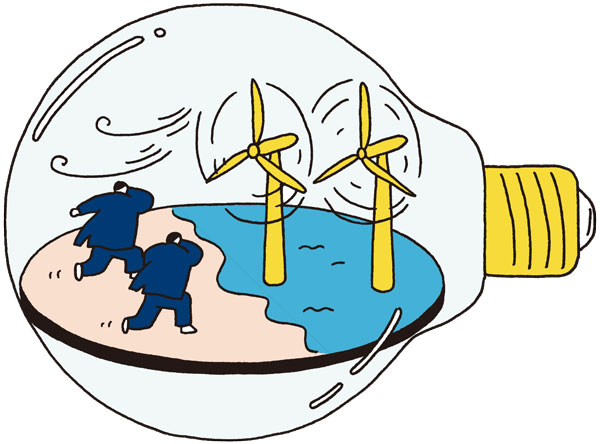2050年に温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすると宣言した菅義偉首相。既に、欧州連合(EU)やイギリスも同様の方針を示しており、日本も追従した形だ。実現のためには水素利用、二酸化炭素(CO2)の吸着・貯蔵、蓄電池開発などエネルギーに関連する新技術の大規模な商業化が必要となるが、目標達成までの道筋をどう描くのか。
日本政府は、安全性を前提に経済性、安定供給、環境の三点から、中長期的なエネルギー需給に関するエネルギー基本計画を定めている。18年に策定された第五次計画を見直す議論が10月に開始されたばかりだが、15年に定められた30年時点のエネルギー・電源構成の数値についても議論が行われる予定だ。
現行の30年電源構成比率は、再生可能エネルギー22~24%、原子力20~22%とCO2を排出しない非炭素電源で44%程度、石炭火力26%、液化天然ガス(LNG)火力27%、石油火力3%程度と目標値が定められているものの、実現に向けた政策は再エネ以外担保されていない。
たとえば、20~22%の原子力比率の達成には、現在ある原発すべてを60年運転に延長し、加えて建設中の原発の稼働も必要になるが、政策の裏付けはなく、目標を実現するための道筋は見えてこない。
欧米諸国のエネルギー政策に目を向けると、政策で誘導可能な再エネを除いて、電源構成の目標値を設定せず、市場に委ねているため、政府の意向が反映されないこともある。トランプ政権は石炭の復活を打ち出したが、市場原理によってLNGに敗れ、大きくシェアを落とした。また、数値目標の設定がないため、政策も柔軟に実行できる。EU諸国は、再エネについては30年目標を設定し、地球温暖化対策を考えながら、経済性、安定供給を達成することを狙っている。そこには政治の意思が見てとれる。大きな目標を掲げ、実現のための方策については、試行錯誤を厭わない、したたかな現実主義を映している。
一方で、東日本大震災以降、日本のエネルギー政策の議論はさまよっている。具体的な数値を掲げていても政策を実行する意思が見えない日本は、市場経済の中ではガラパゴス化しているのかもしれない。