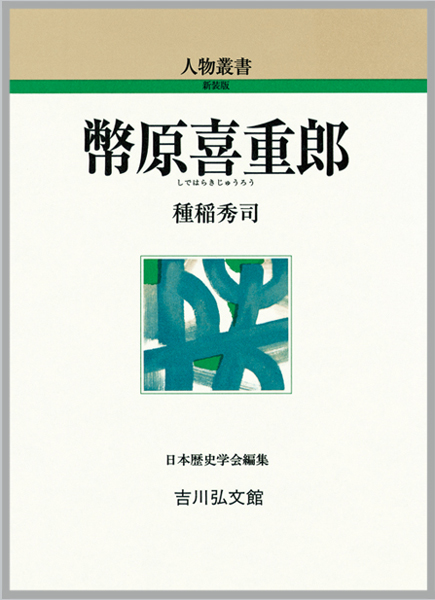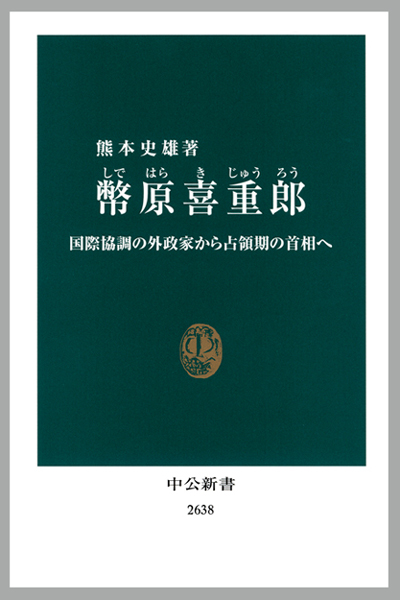「幣原外交」という(日本で初めて)固有名詞で呼ばれた外務大臣として知られ、戦後は首相となり憲法9条の発案者とも言われる幣原喜重郎の評伝である。
両著ともよく調べられた労作である。ただ、当然のことながら読み比べると、一長一短のある内容となっている。種稲著は非常によく調べられており詳しいが、読みやすいとは言えず時としては詳しすぎて全体像が見えにくくなるところがある。それに対し、熊本著は平明で読みやすくあまりこの方面に詳しくない人でも入り込みやすいという長所があるが、時として文学的表現に近すぎるところがあるとも言えよう。
種稲著の考証が丹念な点は随所に見られるが、例えば英国の駐米大使ジェームズ・ブライスとのことがある(以下引用は要旨)。幣原が駐米大使の1913年頃、差別的なパナマ運河通行税問題に対してブライスは英国大使として米国政府に激しく抗議していた。ところが、その法律案が米上院を通過すると抗議をもう一切しないという。怪訝に思って聞くと、「抗議を続けるには結局は戦争をする腹がなければいけない。それもなく続けるのは有害無益だ。英国は米国と戦争しないことが国是となっている。つまらない面目や一部の利益のために大局の見地を忘れてはならない」と答えた。
そして、当時日本からの移民の土地所有を米国が禁止しようとしたため日本の対米世論が強硬になったので抗議していたことをとりあげ、ブライスは幣原に向かい、「アメリカと戦争する覚悟があるのですか」と言い、あるなら大変な間違いだし、「日本の存亡興廃をかけるような問題ではないでしょ」と言った。
さらに、米国の歴史を見ると外国に不正なことをしても時期を置くと必ず矯正する復元力が働く国だからそれを待つべきだと教えた。果たして2年後に米国はパナマ運河通行税を廃止した。
数年後、再会した時、パナマ運河通行税問題は予言が的中したが、日本に関してはまだだと言うと、ブライスは「あなたは国家の運命が永遠であることを認めないのですか。国家の永い生命からすれば5年や10年は問題じゃありません。功を急いで紛争を続けていては、しまいには二進も三進も行かなくなります。今少し長い目で、国運の前途を見つめ、大局的見地をお忘れならないように願います」と言ったのだった。こうして幣原は外交の要諦というものを教えられたという。まさに日本はその後「功を急いで紛争を続けて」破滅の日米戦争に進んだのだった。
これは幣原の『外交五十年』という自伝に出て来る「長期的視野」の必要性を認識させられ外交・とくに対米外交のあり方を教えられる忘れられないエピソードである。
ところが種稲はこのエピソードを紹介した後、ブライスの駐米大使の任期と外交文書からしてこのエピソードには幣原の記憶違いが混ざっている可能性があるという。このエピソードにいたく感動した評者はいささか虚を突かれた思いであった。おそらく大筋はこれに類することがあったのであろうが、種稲の綿密な考証に自伝の取り扱いに対する慎重さの必要性を改めて認識させられたのであった。
幣原外交と田中外交をどう見るか
幣原外交と田中外交をどう見るかという問題は近現代日本外交史を研究するものにとっては一つの試金石である。かつては、田中外交は侵略的で幣原外交は米英に親和的な協調外交だったと言われたこともあった。しかし、私も『満州事変はなぜ起きたのか』(中公選書)で指摘したところだが、最近の研究によってその認識はあらためられつつある。熊本著はこの点、最近の研究を踏まえ、両者の基本的同質性を指摘している。
すなわち、①満蒙権益の重視、②対英米協調路線、➂通商政策進展、④中国内政不干渉の4点にわたって両者は同質的であるという。
とくに②④は誤解されていることが多いが、1925年の五・三〇事件、第二次南京事件の後、英国が共同出兵を要請してきたのを幣原は断ったため、英国は孤立して困らせられたのに対し、その後田中義一は出兵したので英国から高く評価された。すなわち、幣原外交の方が結果的に対英非協調となった面があり、田中外交の方が英国に歓迎された面があったという。また、田中は出兵したからといって、あくまで居留民保護が目的で中国の内政に干渉する意図はなかった。熊本によれば、田中の問題は陸軍の関東軍などの急進派をコントロールできなかったことである。
そして両者の相違は、人的ネットワーク・下僚の差配の点にあったという。田中は陸軍内部を母体に権力基盤を獲得したが、幣原は通商政策局に数少ない幣原派を築いたにすぎず、それは北京関税会議において外務省内部で機能せず、第二次幣原外交でそれはさらに顕在化した。満州事変時外務省内部で力が強かったのは強硬派の亜細亜局の谷正之らであり、それに幣原は押し切られていったという。幣原は外務省内部を支配する政務局出身者を掌握していなかったから、そうなったのも当然でこのように幣原は人的ネットワーク・下僚の差配は巧みでなかった。そして、その根底には田中外交と同質的な満蒙観が存在したという。この辺り、熊本著はよく論点が整理されており問題提起的内容が多い。今後の議論を期待したいものだ。
ただ、熊本著は文学的表現になりすぎた点が時折感じられる。短的にあらわれているのは終戦の時の描写である。終戦の日、幣原は詔勅を「ただ静かな心持ちで聴いた」、その時いた「倶楽部になどもう居る気もしない」「戦争は終わったのだ、ただそのことだけを、ぼんやりと反芻しながら、幣原は倶楽部を出た」と書かれている。さらに、手帳には「『ポツダム』宣言受諾」とだけ書かれているとした後、以下の叙述になる。幣原は「落胆も昂揚も怒りも悲しみもない、それらをすべてそぎ落とし、あらゆる感情を流しきったかのような、そんな心境でもあった」。
これは幣原が終戦をどう受け止めたのかを知るための重要な箇所だが、証拠となる資料は提示されていない。資料があるのだろうか、著者の類推ならオーバーにすぎるだろう。種稲著にはこの点の記載はなく、帰りの電車で出会った「泣き叫ぶ男」の話になっている。
両著とも不正確なところもある。幣原の学歴に関することである。幣原が1883年、大阪中学校に入学したという点は同じだが、その後が問題だ。幣原が在学した学校のその後についての両著の記述と学校史に基づく史実とを並べておこう。
種稲著―1886年4月「高等中学校として再スタート」、88年8月京都移転。
熊本著―1886年4月、「第三高等中学校になり京都に移った」。
学校史―1885年7月、大学分校と改称、1886年4月、第三高等中学校と改称、89年9月
京都新校開校式(神陵史編集委員会編『神陵史―第三高等学校八十年史』三高
同窓会、1980。京都大学百年史編集委員会編『京都大学百年史』【資料編2】
[第2編:百年の出来事]「第1章:舎蜜局から第三高等学校へ」、京都大学
後援会,2000)。
種稲著は、大阪英語学校が大阪中学校に改称したと書いてあるが、『神陵史』『京都大学百年史』には大阪英語学校は1879年に大阪専門学校に改称し1880年に大阪中学校に改称したとあるから、これも間違いである。
前に出た服部龍二氏の幣原評伝には、大阪中学校に入った後、京都の第三高等中学校に入学した、と両者を別の学校として書いてあったので、『外交50年』(中公文庫)の解説の際に、訂正を求めたがその後増補版が出たときに訂正されていたということもあった。
細かいことにこだわるようだが、近代日本の高等教育史では、この時の第三高等中学校の大阪から京都への移転は、東京の第一高等学校・東京帝国大学に匹敵する高等教育機関がなぜ大阪にできず京都にできたのかという点で研究史上重要な問題なのである。この後、第三高等中学校は第三高等学校になり、その結果、西の帝国大学も京都に設置されることになる。一旦大学分校となり設置の可能性のあった帝国大学を大阪はこの移転のために京都に取られ、東の一高・東大、西の三高・京大という構図が固まってしまったのだ(詳しくは、竹内洋『学歴貴族の栄光と挫折』講談社学術文庫51頁~56頁)。そのあたりの認識が足りないといえよう。幣原は第三高等中学校在学中、浜口雄幸・伊沢多喜男などと知り合っており、とくに浜口とは後に首相・外相という関係になるのだから重要だ。
外交史研究者は、外交官養成の基礎となるその国の高等教育制度の歴史をきちん勉強しておかなければいけないだろう。英国外交を理解するにはパブリック・スクールというものをよく知っていなくてはならない。