いわずと知れた民俗学者、宮本常一の著作で、しかも昨年8月の初版発行ではあるが、どうしても今ご紹介したく、とりあげた。
というのは、本書に収録された「飢餓からの脱出」と「日本人の食生活」という2本の原稿のうち、「飢餓からの脱出」は、「書きかけのままで残されていた未完の原稿」であり、未発表の作品だからである。
さらに、「未発表・未完原稿」という貴重さにも増して、今ふたたび宮本常一の“仕事”を振り返りたくなったのは、「日本中をくまなく見て歩いた宮本ならではの、各地に例を挙げた考察」が、情報のあふれる現代社会においてひときわ光彩を放つからである。
宮本常一を想起させた
斎藤真一の「使命感のようなもの」
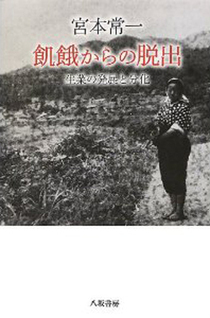 『宮本常一 飢餓からの脱出―生業の発展と分化』 (宮本 常一 著、田村 善次郎 編集)
『宮本常一 飢餓からの脱出―生業の発展と分化』 (宮本 常一 著、田村 善次郎 編集)
実は、本書を手にとったのは、ある絵画との、雷に打たれたような邂逅がきっかけだった。
先月、山形県天童市を訪れた折、市内の出羽桜美術館とその分館「斎藤真一 心の美術館」に立ち寄った。恥ずかしながら、画家でエッセイストである斎藤真一(1922~1994)の仕事にじかにふれたのは、初めてだった。
斎藤は、岡山県倉敷市生まれ。画文集『斎藤真一さすらい記 ―なつかしき故里をもとめて―』によると、フランス留学中に欧州を放浪し、ジプシーなどをテーマに「さすらい」シリーズを描いた。1961年からは、津軽や越後を旅して「越中瞽女日記」を連作した。
盲目の旅芸人「瞽女(ごぜ)」に惹かれ、十年以上ひたすらに追いかけて描いた絵と言葉は、圧倒的な力で見る者を打ちのめす。
斎藤の描いた瞽女を通して、現代の私たちは、生きることに精一杯だったかつての日本人の輝きと哀しみをわがものとする。

















