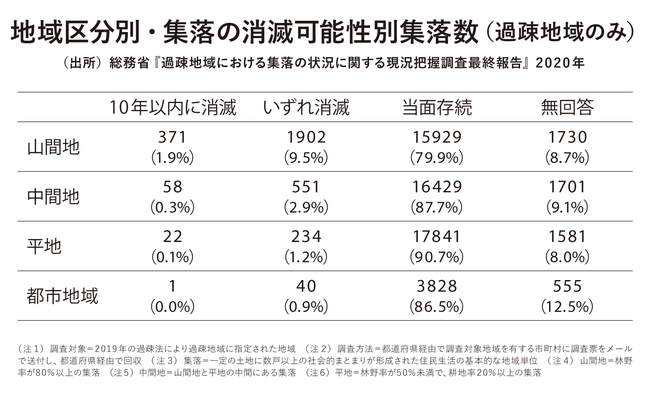時々、明るいニュースを聞くこともあるが、過疎化が進む山間地域の現状には依然として厳しいものがある。山間地域を車で走れば、空き家、廃屋、放棄された耕地がいくらでも目にとまる(写真①)。河川区域はさておき、平らな場所が雑草で深く覆われていたら、十中八九、放棄された耕地と考えてよい。
では、国勢調査の人口、常住人口(常に住んでいる人の人口)がゼロになった集落は、どうなっているのか。その問いへの答えを起点として、「活性化による常住人口の維持が難しい集落(常住人口あり)」の長期的な生き残り策について考えたい。
厳しい過疎地の維持を考える上で避けることができない「財政の問題」についても言及する。
人がいないように見えない
無住集落の「リアル」
ここでは、国勢調査の人口(常住人口)がゼロになった大字(「おおあざ」と読む、江戸時代の村の範囲を指すことが多い)を「無住集落」と呼ぶこととする。
無住集落と類似した用語に「廃村」というものがある。インターネットで「廃村」の画像を検索すれば、廃屋が並ぶ「不気味な画像」が多数ヒットするはずである。しかし、そのような風景は現実のごく一部にすぎない。
無住集落の大半は、「①よく見られる集落(常住人口あり)と見分けがつかないような無住集落」「②よく見られる集落とは言いにくいが、何らかの形で活用されている無住集落」「③深い緑で覆われた無住集落」のいずれかである。
筆者の地元である石川県の事例を紹介する。なお、石川県内の無住集落(ダムで水没した場所などは除く)の数は、2015年の時点で33カ所、20年の段階で44カ所である。5年間で11カ所も増えたことになる。