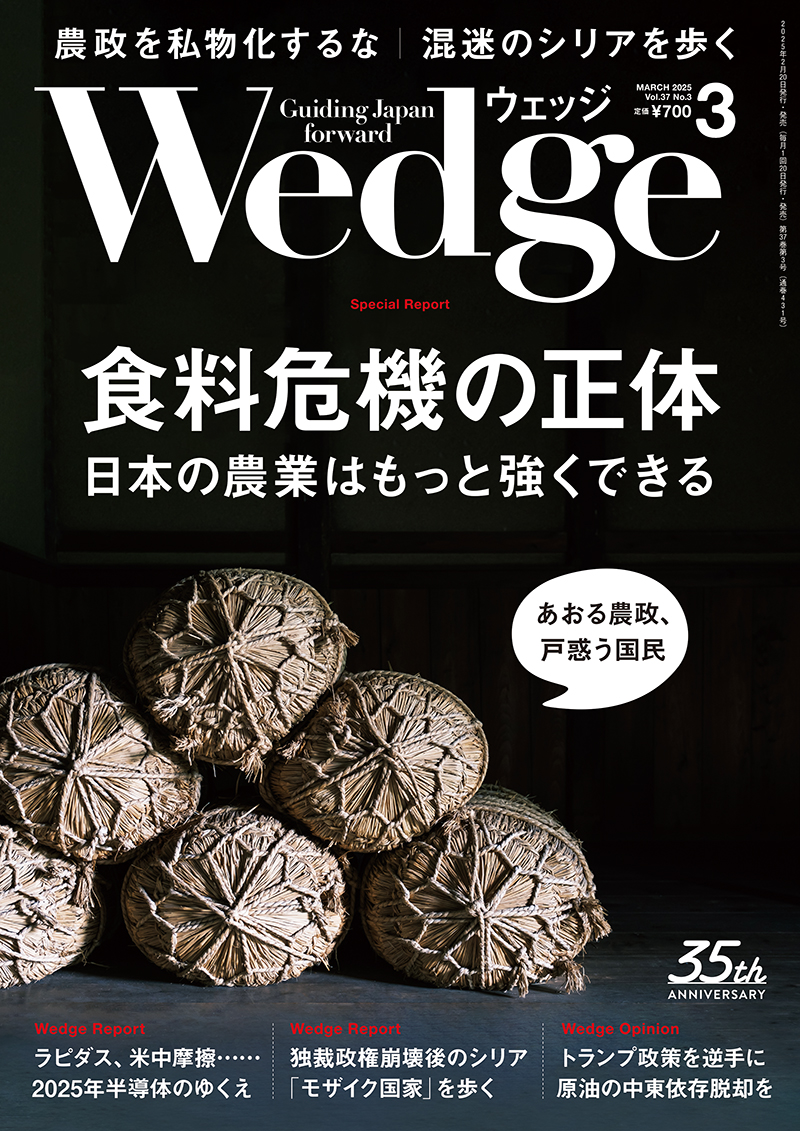農家を支える方法は
原料輸出だけではない
マーケットは中国ばかりではない。しかも、和食ブームを追い風に、日本は先進国として、コメの原料輸出だけにこだわらず、弁当などの「加工品」輸出にも取り組んでいくべきである。
参考になるのはイタリアの取り組みだ。イタリアは世界最大のパスタ輸出国であり、ブランディングして展開している。1960年代までは原料小麦の輸出が中心だったが、小麦不足からデュラム小麦の輸入を増やす一方で、パスタとして輸出し、国内農業・農家を支えてきた。農林水産省「イタリアの農林水産業概況」によると、イタリアは2018〜22年の直近5年間でも、毎年700万トン前後の小麦を安定的に生産している。
パスタはコメに比べ、様々な料理にも使える点や世界的な認知度でも利点があるのは承知している。だが、世界で和食の存在感が高まっている。それを追い風に日本の食文化であるお弁当やおせち料理、チャーハンやおにぎりなどを冷凍食品にして輸出すれば、日本のコメ農家ばかりでなく、食品加工会社などにも経済効果は波及する。イタリアのワイン同様、日本酒も立派な加工品の一つだ。
コメではないが、日本にもそのような考え方を実践している企業がある。「ポテトチップス」や「じゃがりこ」で有名なカルビーだ。同社の商品が売れることによって、北海道の加工用馬鈴薯が売れ、生産を伸ばし、その結果として農家が支えられている。
つまり、国主導の政策ではなく、民間主導で「出口戦略」を持ち、農業をリードしていくという考えだ。それは十分に可能だし、そのことを理解し、応援してくれる消費者の存在によって、日本の農業はもっと持続可能で、もっと多様性に富んだ成長産業にしていくことができると思う。
私は、かねてより農業問題とは「(役人・農協などの)農業関係者問題」あるいは「農業関係者の居場所づくりのために創作されてきた問題」であることを訴え続けてきた。それでも、現状を変えることは容易ではない。貧農史観に基づく政策によって日本の農業が滅びるようなことがあってはならないし、若者がうんざりするような政策をいつまでも続けてはならない。
現状維持を続ければやがて〝どん詰まり〟になることは避けられない。そうなれば、農業経営者や民間企業が実践する「現実」が先に進み、日本の農業を変える突破口になる可能性は十分にある。そういう未来の選択肢があってもいいのではないか。(談)