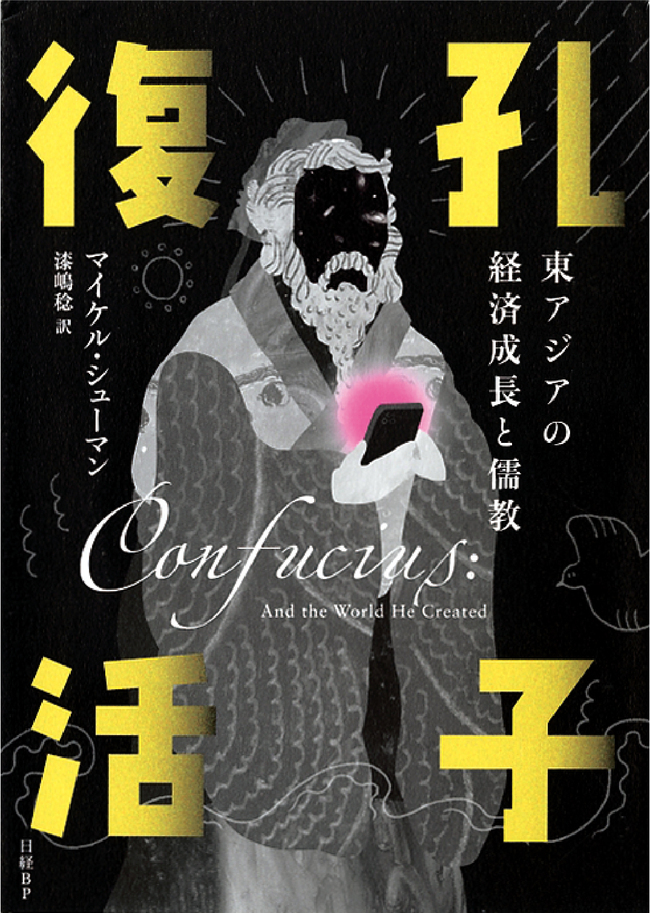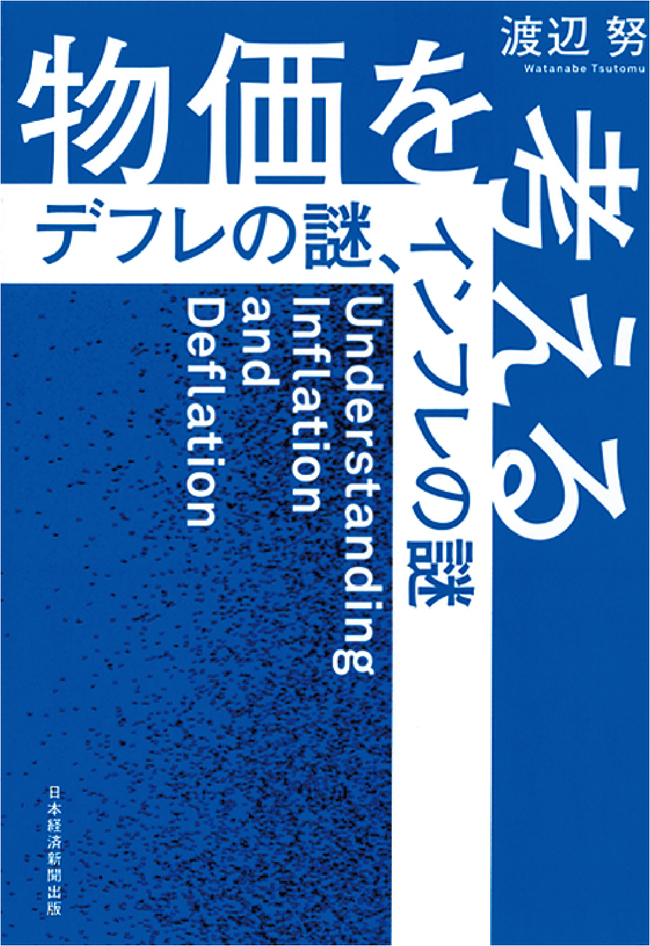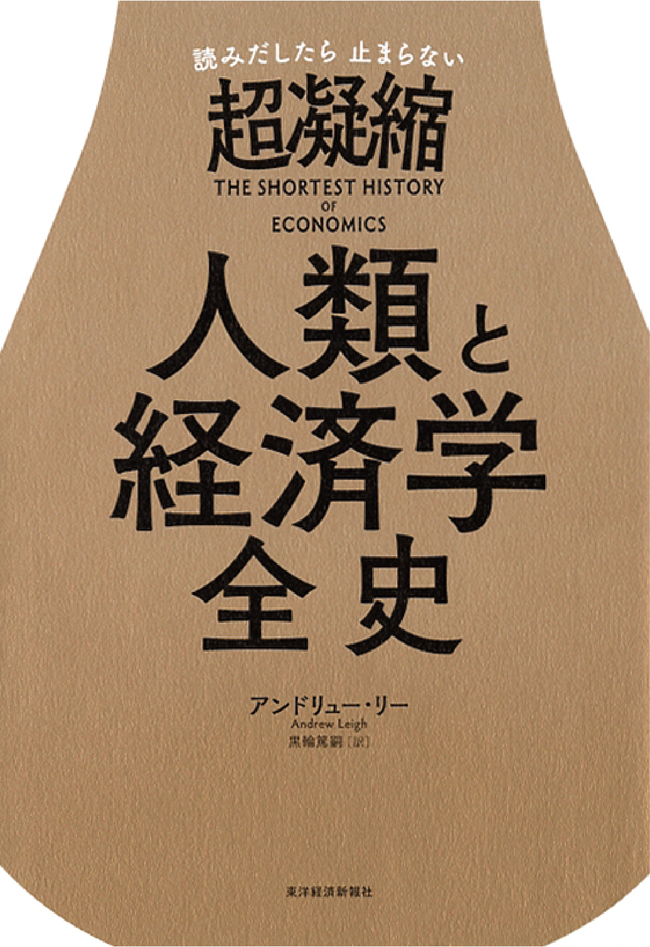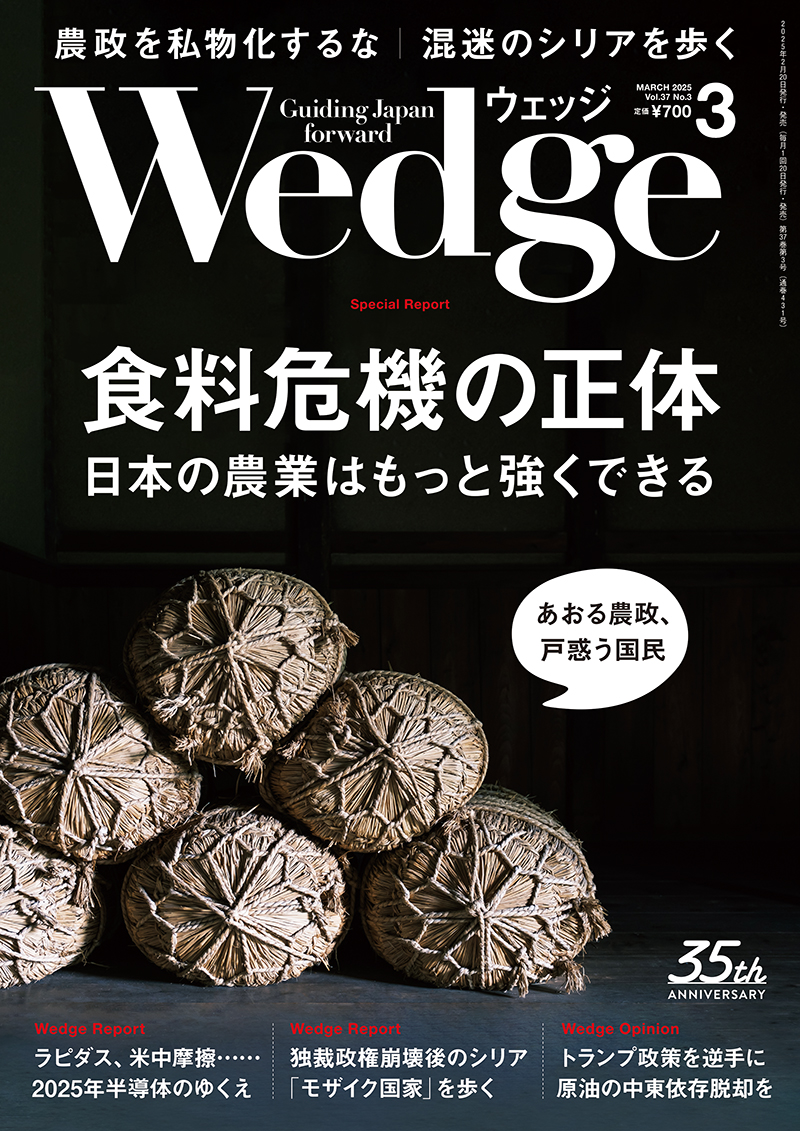孔子をとらえ直す
孔子復活 東アジアの経済成長と儒教
マイケル・シューマン(著)、 漆嶋 稔(訳) 日経BP 3300円(税込)
著者は、ウォールストリート・ジャーナル紙とタイム誌の特派員としてソウルや北京での取材経験が長い。その中で感じ取ったのが、儒教、孔子の存在だ。本書は、孔子=論語を通じて、東アジアを理解しようとする試みである。論語の解説に加え、時代の変遷で、孔子像も変化してきたことも分かる。例えばマックス・ウェーバーは、守旧的な儒教からは資本主義は生まれなかったと論じたが、第二次世界大戦後、日本と「四小龍(韓国、台湾、香港、シンガポール)」で経済成長が起きたことから、むしろ儒教の向学心、倹約精神が、その成功につながったとして評価されるようになったのだという。
日本経済の謎が解ける
物価を考える デフレの謎、インフレの謎
渡辺 努 日本経済新聞出版 1980円(税込)
コロナ禍によって、30年にもわたる停滞の波がさらに揺るがされた日本経済。物価と賃金が変わらない「慢性デフレ」の現象は、日本人の「価格は据え置かれる」という消費者の硬直性にあった─。2022年春以降に起こったインフレについて著者は、健全な経済循環に戻っただけの物価の正常化だと指摘する。その原因について、コロナ禍での「社会規範=ノルム」を例に述べるなど、経済と生活をつなぎ合わせて解説してくれる。
経済の力が人々に与えた影響
読みだしたら止まらない 超凝縮 人類と経済学全史
アンドリュー・リー(著)、 黒輪篤嗣(訳) 東洋経済新報社 2200円(税込)
かつて高級な乗り物だった旅客機は、飛行速度の向上とワイドボディ機の登場で一度に多くの人を運べるようになり大衆化した。乗客が空港でチケットを購入するようになると、乗り遅れが発生しないよう決済速度の早いクレジットカードが開発されたという。経済発展の裏側には格差拡大など、様々な問題もあるが、人々を豊かにしてきたことは間違いない。世界経済の歴史を事例とともに解説する本書は、経済学の初心者でも楽しく学べる一冊だ。