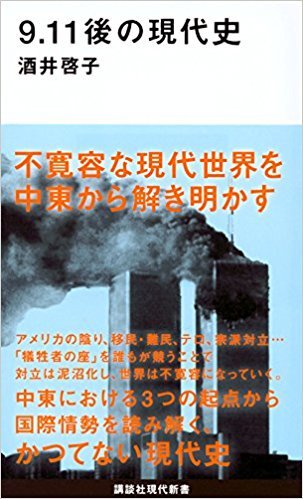また、1924年にはカリフ制が廃止されました。カリフ制とはイスラーム国家システムの根幹にあった統治体制です。イスラーム教が成立した7世紀には、イスラームは宗教にとどまらず、法体系でもあり、軍事、政治的共同体でした。20世紀に入ってヨーロッパ諸国に国境線を引かれ、西欧起源の国民国家制度を押し付けられた中東各国には、第一次大戦で敗北しイスラーム国家システムを失ったことへの鬱屈が長く残りました。
その後80年もの間、中東諸国の間でナショナリズムやイスラーム主義などの台頭があって、ヨーロッパのくびきから離れて独自の国作りを模索するさまざまな努力が繰り返されるわけですが、それもかいなく、2003年にはイラク戦争が勃発し、イラクにアメリカやヨーロッパの軍隊が駐留することになった。再び本格的に「外敵」が中東にやってきた、というわけです。イラクのフセイン政権は内政干渉ともいえるような形で外国によって転覆させられてしまった。時間的には隔てていますが、かつてヨーロッパにバラバラにされた第1次世界大戦前後のことを再現するような戦争だと、中東の人たちはイラク戦争を受け止めた。だからこそ反米感情が高まり、ISのように、もとを辿ればヨーロッパが勝手に国をつくったからいけないのだ、と主張する勢力が生まれたのです。
――酒井先生はイラクがご専門です。イラク戦争前後で現地を訪れてみて変わったな、と感じるのはどんなところでしょうか?
酒井:イラク戦争前後では何もかもがガラッと変わりましたね。イラク戦争後の03年7月に訪れたときは、治安はそこまで悪化していませんでした。イラク国内には、独裁政権のフセイン政権が倒れ、安堵の空気が広がり、これから戦後復興をするんだ、という期待に満ち溢れていました。しかし、その後すぐに、戦前には考えられなかったほどに治安が悪化していきました。
同時に、他のアラブ諸国、ヨルダンやエジプトを訪れると、イラク戦争のようにアメリカは徹底的な武力行使をしてまで自国の政権を転覆させるのか、という衝撃が大きかったように感じました。
――フセイン政権による独裁政治では、そんなに締め付けがひどかったのですか?
酒井:イラクは、1980年代にイラン・イラク戦争を、90年代には湾岸戦争を戦い、国連による経済制裁を受けました。それだけ戦争ばかりして国際社会から排除されたのはフセインがいたからだという反省は、イラク人の間にはあります。確かに80年代は、フセイン政権下で政治的な不自由や国際社会からの厳しい視線もあり、物言えぬ息苦しさがありました。しかし、食事に困ることはありませんでした。フセイン政権への反発が強まったのは、90年代以降は経済制裁が拍車をかけて、物を食べることさえもできなくなってしまったためです。
――第1次世界大戦以降、イスラーム世界はヨーロッパに勝手に国をつくられてしまった。反欧米感情や活動はISが出現する以前から強かったのでしょうか?
酒井:そこまであったわけではありません。ヨーロッパの侵略や思惑で国がつくられてしまったというフラストレーションがある一方で、欧米に学ばなくては、というリベラルな発想の知識人たちが多かったのも事実です。欧米に追いつけ追い越せ、という思いと、欧米への怨みという両者のせめぎあいで揺れ動きますが、20世紀の前半、70年代までは欧米に追いつけ追い越せ型、近代化路線が主流でした。
――だからこそ、ドバイのような都市ができたわけですね。
酒井:ドバイが発展したのはもっとあと、20世紀の終わりではありますが、基本的に欧米近代の技術や知識を真っ先に取り入れようという意識が、20世紀前半くらいから中東にはあります。イラン研究者が言うには、イランが核開発にこだわる理由は、軍事的に核を持ちたいというよりも、最先端の核開発技術を持ちたいという科学的な追求心が強い側面もあるそうです。それだけ中東での科学技術信仰は強いものがあります。
それと同時にヨーロッパの植民地主義に不満を抱えていますから、政治体制としては、西欧ではないヨーロッパを倣って社会主義へ傾斜しました。特に顕著だったのは1960年代から70年代です。ただ、社会主義も西欧近代が生み出したものですから忸怩たる思いがあった。そこで、社会主義ではなく、第3の道として70年代以降、西でも東でもない、と主張するイスラーム主義が台頭してきました。